このページを印刷される方はこちらのバージョンをご利用下さい。図がより精細・鮮明に印刷できます。
冷凍・低温技術の歴史
1.冷凍・低温技術の歴史
ここでは低温を実現する技術の歴史を概観します。
(1)16〜18世紀
16世紀
イタリアで硝石に水を加えると、その溶解の際に周囲の熱を奪って水が冷やされることが発見されます。1607年には塩と氷りを混ぜることにより水を凍らせることができることが発見された。
1702年
ギヨーム・アモントンが空気温度計を用いて初めて絶対零度を計算し−240 ℃とする。この温度で体積と圧力がゼロに達すると理論化する。別稿「絶対温度とは何か」2.(3)も参照されたし。
1755年
スコットランド、グラスゴーのウィリアム・カッレン(W.Cullen 1712〜1790年)は揮発性液体を蒸発させることで氷りが作れることを報告している。彼は論文で「空気の温度が約43°Fのときのエーテルについての実験で、エーテルの入った容器を水の入った他の大きな容器の中に入れておいた。この容器を数分間真空中においたところ(真空ポンプで引いてエーテルを沸騰させる)、エーテルの容器のまわりに厚くて固い氷りの殻がついて、水の大部分は凍ってしまった。」と報告している。
1761年頃
カッレンの弟子であるジョセフ・ブラック(J.Black 1728〜1799年)は融解・蒸発の潜熱の理論を発表した。これは、物質の相が変化するとき、熱がどのような働きをするのかを考察した最初です。
1774年頃
ジョセフ・プリーストリ(英 J.Priestley 1733〜1804年)はアンモニアと二酸化炭素を発見。後に冷凍用冷媒として重用される。ブラックもプリーストリも蒸気機関の改良で有名なワットの友人です。ちなみにワットの蒸気機関の改良は1764年です。
当初の冷凍機関の発展は蒸気機関の発展と表裏一体で、蒸気機関の技術者だったオリヴァー・エヴァンス(Oliver Evans 1755〜1819年)は1805年に、またリチャード・トレヴィシック(Richard Trevithick 1771〜1833年)は1828年に冷凍サイクルの考えを発表している。
1784年
フランスのガスパール・モンジュ(Gaspard Monge 1746〜1818年)は初めて二酸化硫黄の液化に成功。ちなみに二酸化硫黄は常温度では4〜5気圧程度に圧縮すると容易に液化する。
1799年
オランダのファン・マイム(M. van Marum)はアンモニアでボイルの実験をしているときに7気圧近くまで圧縮するとアンモニアが液化する事をみつけた。
(2)19世紀前半
1823年
マイケル・ファラデー(Michael Faraday 1791〜1867年)が塩素の液化に成功。逆U字管に塩素化合物をいれて密封した後、塩素化合物がある方を過熱して塩素を発生させた。圧力が上がって冷却されたもう一方に液体の塩素が溜まることを発見した。[On Fluid Chlorine Phil. Trans.
R. Soc. Lond. January 1, 1823 113:160-165;]
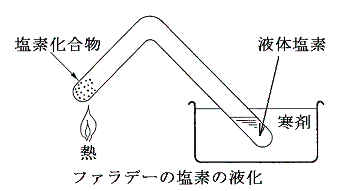
彼は同様な方法で亜硫酸ガス、硫化水素、二酸化炭素、アンモニアなどを液化した。ただし、この実験は気体が発生するときの圧力を利用して液化するもので、極めて危険な実験でした。実際、ファラデーもたびたびガラス管の爆発事故に遭いかなり危ない目にあったようですから、決してまねはされないようにして下さい。
1845年になるとファラデーの液化装置も進歩して、液化しようとする気体を圧縮ポンプで40気圧の高圧にしたのち、それを寒剤で冷やす方法になった。寒剤として固体二酸化炭素[1834年のティロリエ参照]とエーテルの混合物を用い、それを減圧容器の中に置いて-110℃を得た。その方法によりエチレン、ヨウ化水素、臭化水素などの液化に成功した。[On the Liquefaction and Solidification of Bodies Generally Existing as
Gases Phil. Trans. R. Soc. Lond. January 1, 1845 135:155-i;]
1824年
フランスのニコラ・レオナール・サディ・カルノー(Nicolas Leonard Sadi Carnot、1796〜1832年)は、熱力学創始のきっかけとなる画期的な著作「火の動力、および、この動力を発生させるに適した機関についての考察」を出版する。これは、後にクラウジウスやトムソンにより取り上げられて、熱と動力(仕事)との関係を明らかにし、絶対温度とエントロピー導入の基礎となった有名な論文です。
訳本がありますので是非読まれることを薦めます。サディ・カルノー著、広重徹訳解説「カルノー・熱機関の研究」みすず書房(1973年刊)
1834年
ジャン・ペルティエ(仏 J.C.A.Peltier 1785〜1845年)は二つの異なった金属をつないで電流を流すと、その繋ぎ目で電流の向きにより熱が吸収されたり放出されたりする現象を発見(ペルティエ効果)。これは温度差により電位差が生じるゼーベック効果の逆の効果です。ちなみにゼーベック効果の発見は1821年です。もう少し詳しい説明は別稿「熱機関の効率(冷凍サイクル)」6.を参照。
1834年
ヤコブ・パーキンス(米 Jacob Perkins 1766〜1849年)は下図の冷凍機を設計して特許を出願した。
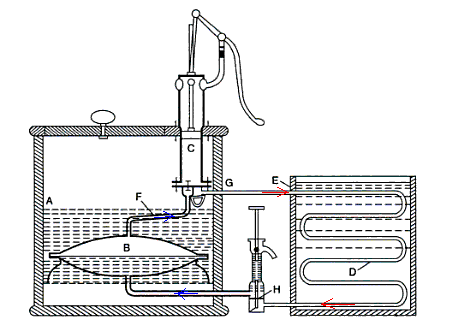
作動原理はエーテルや他の揮発性流体の蒸気ををポンプCで高圧に圧縮する。そのとき温度が上がるがそれを水槽Eに浸けた螺旋管D内で冷却して液体に凝縮させる。これを荷重弁H(重りの重さで凝縮器Dと蒸発器Bの間の圧力差を保つ一種の減圧弁)を通して低圧の蒸発器Bに導入する。そこはポンプCにより吸引されて低圧になっている。ちなみにジエチルエーテルの1気圧の基での沸点は34.6℃だが、例えば60mmHgに減圧すると-21.7℃で沸騰する。低圧下でエーテルは沸騰・蒸発して、そのときの気化熱で周囲Aを冷却する。気化したエーテルは再び圧縮ポンプCに吸引されてサイクルが終了する。荷重弁Hの上の小さなポンプはエーテルなどの冷却剤を装置に注入するためのものです。
下図は彼がイギリスに渡った後に、彼のアイディアに基づいてジョン・ハーグが作った試作機です。これは旨く動いて、動力を用いて氷を作る最初の機械となった。その後、パーキンスはイギリスの特許をとり製氷機を利用する事業を興したが商業的には成功しなかった。そういった氷を大量生産し、流通させる社会状況がまだ整っていなかったのです。[拡大図]
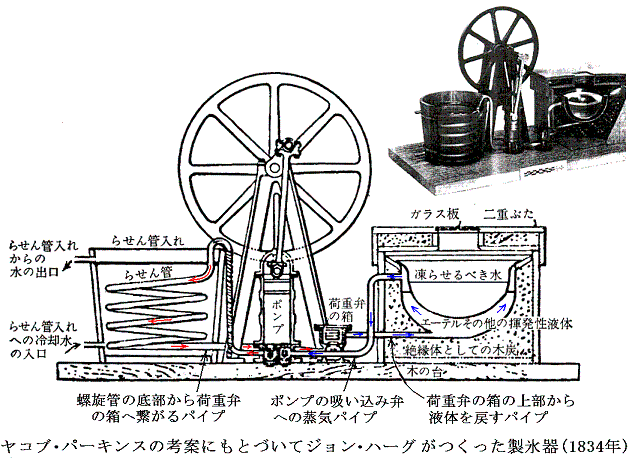
1834年
フランスのチャールズ・ティロリエ(Charles Thilorier)は密閉した容器の中で炭酸水素ナトリウムに硫酸を作用させて得た二酸化炭素を圧縮して高圧にし、別の容器中に放出する事により液体の二酸化炭素を得た。その液体の二酸化炭素を急に空中に拡散することにより雪状の固体二酸化炭素(ドライアイス)を得た。これは今日でも大量のドライアイスを工業的に作るときの方法です。
授業でも、同じ方法でトライアイスを作って見せます。下はその時の様子を示す写真です。
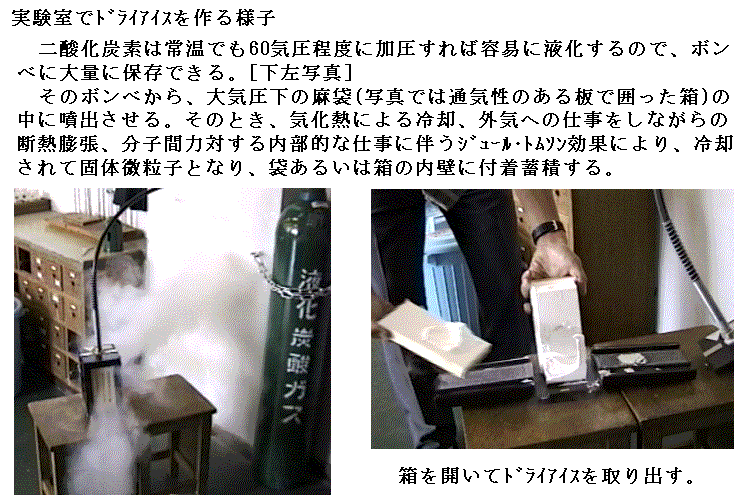
ただし、このとき利用する二酸化炭素は、冷たく重いので実験室の床に滞留します。そのため、教室の窓を開けて十分換気する必要があります。
ジュール・トムソン効果の本質が理解されるのは1852年ころですが、この効果自体はティロリエなどの技術者には早くから知られていて利用されていたということです。
1844年
アメリカ人の医者ジョン・ゴーリー(John Gorrie 1803〜1855年)は黄熱病の患者を救うために氷をつくって空気を冷やすことが必要だと考えた。そのために1844年頃製氷機械を考案し、アメリカの特許を申請して1851年に認められた。彼の造った空気冷却機械の一つがイギリスに送られ、それの詳しい記述が「大英帝国民間技術者報」に載った。この報告は世界中の技術者によって読まれ、彼の空気冷凍機は後の空気サイクル冷凍機設計の基礎となった。この型の装置はその後何年も使われ、後に、その熱力学的過程が良く理解されて改良されて完全なものとなった。
ゴーリーの冷凍機は空気が外部に仕事をしながら断熱膨張することで冷却する効果を利用するもので、下図の様な構造をしていた。[拡大図はこちら]
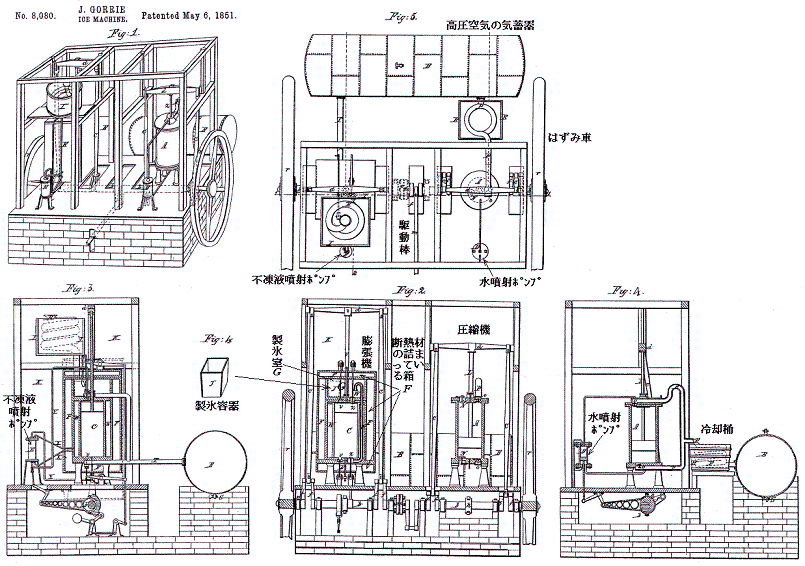
両端の輪 r がはづみ車(fly-wheel)で、その中心に駆動軸 b が通っている。その軸についているクランク f で圧縮機 A が駆動される。その動力は左側の膨張機Cからクランク f’ を通して得られる駆動力と、装置の中程にある駆動棒 m を通じて外部の動力機械から供給される動力によりまかなわれる。
まず内側に開くバルブ N を通じてシリンダー A に外気を取り入れる。空気はピストンにより圧縮(約8気圧程度か?)されるが、その最後の過程の高圧・高温になった状況で小型のジェットポンプ D により水がシリンダー内に吹き込まれる。水は直ちに蒸発して空気を冷やす。圧縮された空気は外向きに開くバルブ o を押し開いて凝縮器 R に入る。高圧空気は、螺旋パイプ P を通る間に周りの水により冷やされる。そのとき水蒸気も凝縮して水に帰り凝縮器の底にたまる。この凝縮水は再びジェットポンプ D へ戻り再利用される。一方高圧かつ冷却された空気がタンク B に蓄えられる。
タンク B からパイプ T を通して膨張機 C に高圧空気が流れ込む。そのときシリンダー内に流れ込む空気量は弁 v により適当なところで断ち切られる。シリンダー内の空気がその後ピストンのストロークほど膨張するとちょうど大気圧になるように、その充填量は調整されるのです。弁の開くタイミングはそのように調整されている。そのときピストンの反対側の空気は、すでに大気圧まで膨張して冷却されている。その冷却空気は弁zを通じて製氷室 G へ排気される。このとき高圧空気の膨張力はシャフト b を通じて圧縮機 A の動力として使われる。膨張シリンダーは次に述べる不凍液のタンク W で囲んである。タンク W は、さらにその外側を断熱壁 F で囲まれている。
膨張機 C における冷却効果を効率良く取り出すために、膨張を開始する直前の高圧空気にジェツトポンプ E により不凍液(塩化ナトリウム、炭酸カリウム、硝酸カリウムなどの塩を含んだアルコール水溶液)がシリンダー内に吹き込まれる。この不凍液の霧は膨張過程で、膨張空気に熱を奪われて氷点下(−7℃程度か?)に冷却される。不凍液の霧を吹くんだ冷たい空気はピストンの復帰動作の過程で弁 z を通じて製氷室 G または W へはき出される。この冷たい不凍液の霧を含む空気は、シリンダー周りと、その上部を包む部屋( W 上部が製氷室G)へ流れ込む。この部屋 W と G には、 G に設置してある製氷用容器 J の周りを包み込むことができる吃水線まで不凍液(塩のアルコール水溶液)が満たされている。不凍液の霧を含む空気は、このアルコール不凍液の中にはき出されるので、霧は再び液に溶け込む。それらの冷却された不凍液は膨張シリンダーを冷却するとともに、ジェットポンプ
E に吸い込まれて再び利用される。
製氷室 G に排気された冷たい空気は、 G に繋がっている螺旋状のパイプ H の中を通って大気中に放出される。パイプ H は製氷室の上に設置された箱の中を通っている。その箱の中には、製氷に使われる水が入れてあり、パイプの中を通る冷たい空気により予冷却されて次の製氷に備える。
彼の装置は空気冷却機なのだが、空気の熱交換性は悪いので、圧縮や膨張の適当なタイミングで水または不凍液の霧を吹き込んで効率よく空気から熱を奪ったり与えたりするように工夫されていた。
1848年
ケルビン(W・トムソン)は1848年にカルノーの可逆サイクルの真の意味や意義を研究しているとき、これを使えば、温度を測るのにどういう物体を使うかに関係なく、エネルギー保存則だけに基づいて、温度の普遍的で絶対的な尺度を作ることができることに気付いた。その考え方は、およそ別稿「絶対温度とは何か(積分因子とは何か」6.(2)で説明する様なものです。
W.Thomson,"On an absolute thermometric scale founded on Carnot's theory of the motive power of heat, and calculated from Regnault's observations"[Cambridge Philosophical Society Proceedings for June 5, 1848; and Phil. Mag., Oct. 1848.]あるいは[Mathematical and Physical Papers,6Vols.(Czmbridge University press)の
Vol.1, p100〜106]を参照。これらはどちらもNetから無料でdownlordできます。
ただし、実際に、トムソンが“絶対温度”の測定法を含めて、その概念を完全に確立するのは1854年です。その詳細は山本義隆著「熱学思想の史的展開」第27章、第29章を御覧下さい。
(3)19世紀後半
1850年
アレキサンダー・トワイニング(Alexander C. Twining 1801〜1884年)は1848年蒸気圧縮冷凍の実験を行い、1850年と1853年に冷凍製氷器の特許を取りました。そして1856年には初めての商業的なエチルエーテルを用いた蒸気圧縮冷凍器を作りました。
1852年
1851年の熱力学誕生に貢献したケルビン(W.トムソン)はカルノーサイクルの意味を正しく理解して、熱機関と熱ポンプは表裏一体の機関であることを看破している。そして 「空気の流れを用いて建物の暖房、冷房を行う経済性について」
“On the Economy of the Heating or Cooling of Buildings by means of Currents of Air”; the Glasgow Phil, Soc. Proc. Vol. Ⅲ. Dec. 1852年
という論文において熱ポンプの詳しい作動原理とその理論的効率を説明している。
彼の論文はインドにおけるイギリス政府の建物の冷房を実現することを念頭に置いたものですが、現在の温度調節熱ポンプ工業を150年前に予言しており、新たに出現した熱力学という科学の威力を遺憾なく発揮してその本質を見事に説明していることにおいて画期的です。
1852〜1854年
ジュール(James Prescott Joule 1818〜1889年)とケルビン(William Thomson 1824〜1907年)は、1852年からの一連の実験で気体の膨張に伴って温度が変化するジュール・トムソン効果を発見。これは気体の液化や冷凍機の発展に取って極めて重要な発見です。彼らは、その後約10年間にわたって様々な気体についてこの現象を詳しく調べ、この効果の温度との関係を明らかにした。
これは、W Thomson が 1848年に提唱した絶対温度 と、実際の実用温度計が示す温度との関係を定める為の方法を与えます。その為、ジュールとケルビンが行った“ジュール・トムソン効果”に対する一連の実験は、“絶対温度”の概念の確立に重要な貢献をしたと言えます。
1856年
オーストラリア人のジェームス・ハリソン(James Harrison 1815〜1893年)はパーキンスの考え方を研究して改良し硫化ジメチルの圧縮を利用する冷凍機をつくった。硫化ジメチルはメチルチオエーテル[(CH3)2S]ともいう。これの大気圧での沸点は37.3℃だが、例えば60mmHgに減圧すれば-20℃で沸騰する。ハリソンは1873年に冷凍機で冷凍した食肉をオーストラリアからイギリスに輸送することを試みるが、冷凍機が故障して失敗した。
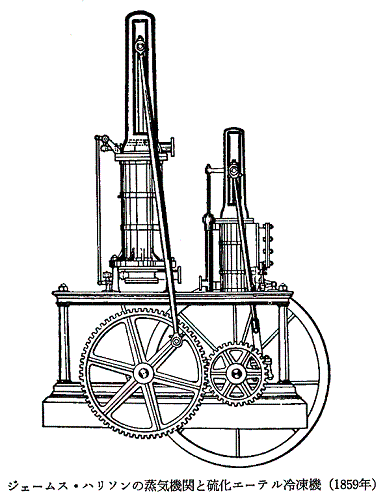
これは実際につくられ、醸造業、石油精製工業で使われた。また製氷のためにも使われた。
1861年
オーストラリアのトーマス・モールト(Thomas Sutcliffe Mort 1816〜1878年)はアンモニアの冷凍機を使って世界初の冷凍工場をシドニーに造った。1876年にはアンモニア冷凍機を乗せた船で食肉のイギリスへの輸送をこころみたがうまくいかなかった。
1869年
アイルランドのトーマス・アンドルーズ(Thomas Andrews 1813〜1885年)は1863年頃に炭酸ガスをガラス管に入れて様々な温度のもとで圧縮してみた。そのさい31℃以上では炭酸ガスにどんなに圧力を加えても液化する事はできないことを見つけた。又彼は31℃のある圧力[73気圧]で液体と気体の境界がなくなる現象を見つけて臨界温度と呼んだ。彼はその後アンモニアや酸化窒素についても臨界温度があることを見つけている。
気体の性質に関する最も重要な論文1869年「物質の気態および液態の連続性について」[The Bakerian Lecture: “On the Continuity of the Gaseous and Liquid States
of Matter”, Phil. Trans. R. Soc. Lond. January 1, 1869 159: 575-590;]及び、1876年「物質の気態について」[The Bakerian Lecture: “On the Gaseous State of Matter”, Phil. Trans.
R. Soc. Lond. January 1, 1876 166: 421-449; ]を発表した。[これらの論文はGoogleBooksから無料ダウロードできるアンドルーズの科学論文集に収録されています。]
つまり気体を液化するとき、ある温度以下に冷却しないと、どんなに圧力を高めても決して液化しない臨界温度があることがわかったのです。低温技術の発展に関してし、これはきわめて重要な発見だった。
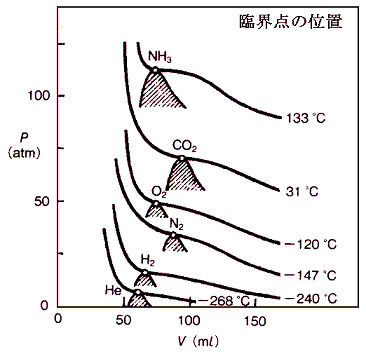
1873年
オランダのファン・デル・ワールス(1837〜1923年)は理想気体の粒子モデルを修正して実在気体の状態を表す式(ファン・デル・ワールスの状態方程式)を導いた。これは簡単な式にもかかわらず、多くの気体の性状をよく説明する普遍性を持っていた。
これは、液体と気体の連続性、臨界状態の理論的根拠、分子間力の存在[これは化学結合や相変化について必須の概念]、分子運動論、さらに水素やヘリウムなどの気体の液化条件、等々を明らかにした。そのため、これは後の低温物理学の発展に多大な貢献をしたといえる。
低温物理学と言えば、超伝導や超流動が注目されますが、低温物理学が果たした最も偉大な功績は熱力学第三法則の検証です。熱力学第三法則は熱力学の基礎となる大法則ですが、物理化学の理論はこの熱力学第三法則に基礎を置くギブズの自由エネルギーの概念にその大半を負うています。また低温における比熱の測定は量子力学の発展に重大な影響を与えました(この事についてゾンマーフェルトはこのように述べている。また別稿も参照されたし)。これらを考慮すると、この方程式が果たした役割の大きさは計り知れません。
ファン・デル・ワールスは、1910年に「液体及び気体の物理学的状態に関する研究」によりノーベル物理学賞を受賞しますが、宜なるかなです。
詳細は別稿「ファン・デル・ワールスの状態方程式」、「熱力学関数(状態方程式曲面)の性質」3.(2)2.や「ファン・デル・ワールスのノーベル賞講演」等々・・・を参照されたし。
1877年
フランスのルイ・ポール・カイユテ(Louis Paul Cailletet 1832〜 1913年)は高圧に圧縮した気体を膨張させることにより酸素の液化に成功。同じ年に窒素の液化にも成功した。
カイユテは下図の装置でアセチレンを液化しようとした。アセチレンは常温でも60気圧まで圧縮すると液化すると思われていたので、水圧器と水銀で毛細管中に圧縮しようとした。しかし60気圧になる前に加圧器が故障して圧力が突然低下した。このとき僅かな間ではあったが毛細管が曇ったのです。彼は圧力が低下した瞬間に温度が下がったのだと判断して実験を繰り返しアセチレンが確かに液化することを確かめた。
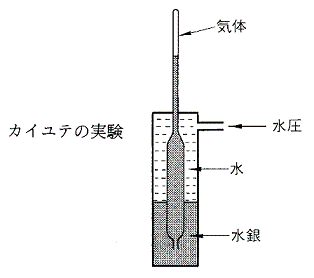
彼はこの方法で酸素の液化を試みる。毛細管を肉厚なガラス管に変え、その中に酸素を詰めて300気圧まで加圧した。毛細管の周りを寒剤(無水亜硫酸つまり液化した二酸化硫黄)で囲み-29℃まで冷却下後に突然圧力を下げて酸素を凝縮(液化)させることに成功した。
1877年
カイユテと、ほとんど同時にスイスのラウール・ピクテ(Raoul Pierre Pictet 1846〜1929年)も独立に酸素と窒素の液化に成功した。ピクテはまず二酸化硫黄ガスを圧縮した後で水で冷却して液体SO2を得る。[SO2は常温で4〜5気圧に圧縮すれば液化する]これを低圧下(20mmHg程度)で蒸発させると-70℃近くの低温が得られる[SO2の凝固点は-72℃]。それを寒剤として圧縮(5気圧以上)した二酸化炭素を冷却して液化する。さらに液体二酸化炭素を減圧下(数mmHg程度)に置き蒸発させて固体二酸化炭素とし-130℃の低温を得る。その低温下で、320気圧に加圧した酸素を冷却することにより液化に成功した。
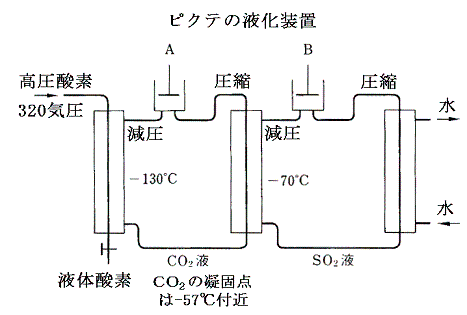
1883年
カイユテの研究成果を元にポ−ランドのクラコフ大学のジグムント・フロ−レンティ・フォン・ヴルブレフスキ−(Zygmunt Florenty von Wroblewski 1848〜1888年)はカルロ・スタニラフ・オルスシェフスキ−(Karol Stanislav Olszewski 1846〜1915年)との共同研究で1883年に酸素の液化に成功した。さらに、この液体酸素(沸点90K)を寒剤として窒素(沸点77K)、一酸化炭素(沸点81K)の液化に成功した。
二人が用いた装置は下図のようなものです。気体エチレンを寒剤Aと寒剤Bにより冷やして液化する。寒剤(ドライアイス+ジエチルエーテル)の大気圧下で到達できる最低温度は-77℃ですが減圧下に置くと-110℃程度は達成できるようです。ちなみにエチレンの大気圧下における液化温度は-104℃です。当然、液体エチレンの大気圧下での沸点は-104℃ですが、減圧下(0.02気圧程度)で蒸発させると-152℃(121K)が達成できます。この温度の下で高圧にした酸素の液化に成功した。ちなみに酸素の臨界温度は-119℃(154K)、臨界圧力は49.8気圧だから、-152℃の低温では高圧にすれば凝縮した。
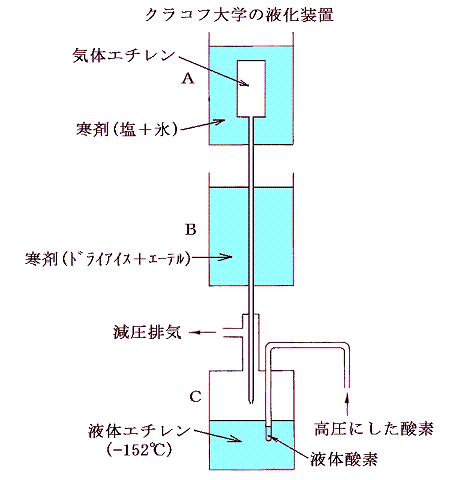
彼らは、この装置を用いて窒素、一酸化炭素の液化を試みたが成功しなかった。これらの気体の臨界温度は-152℃よりも少し高いが、あまり差がないので難しかったのであろう。
しかしすぐ後に、液体酸素[大気圧における沸点-183℃(90K)]を寒剤にして減圧排気(0.1気圧以下)により達成された-200℃近くの低温を用いて、窒素[大気圧での沸点-196℃(77K)、臨界温度−126℃(147K)、臨界圧力33.5気圧]、一酸化炭素[大気圧での沸点-192℃(81K)、臨界温度-140℃(133K)、臨界圧力34.5気圧]の液化に成功した。
彼らは水素の液化にも挑戦したが成功しなかった。水素の臨界温度[-240℃(33K)]はさらに低かったので、この温度ではいくら加圧しても液化は起こらなかったであろう。
1892年
ジェームス・デュワーは二重にした銀メッキガラスの間を真空にした、デュワー瓶を発明した。これは、その後の低温技術の発展にとってきわめて重要なものとなった。
1895年
ドイツのカール・フォン・リンデ(Carl Paul Gottfried von Linde 1842〜1934年) は工業用空気液化装置を開発して特許をとる。
初期の熱交換器は直径10cmの外観の中に直径4cmの内観を入れた長さ100mばかりのもので、それを円筒型に巻きフェルトで断熱してあった。内管を高圧空気が、外管と内管の間を低圧・低温の空気が逆向きに流れるものであったが、最初の実験では65気圧の空気を流したところ、液化が始まるまでに3日もかかったとのことです。
下図は実用化された彼の装置の模式図で三重管が用いられている。[拡大図]
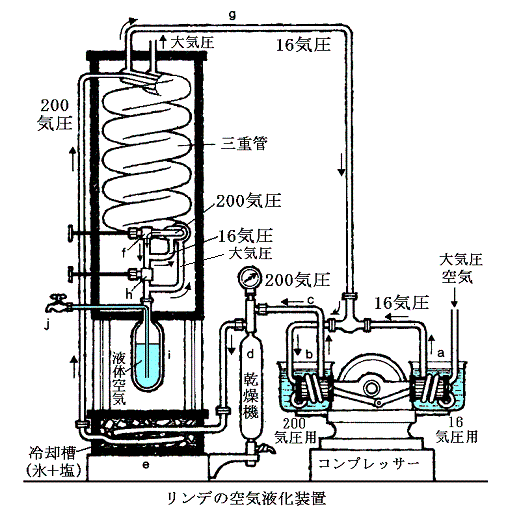
a で空気を16気圧に圧縮し、さらに b で200気圧に圧縮する。これを d で水分を取り除き、冷却槽で冷やしてから、三重構造のスパイラル管に入れる。それを三重管の中を逆方向に流れる冷却気体で冷やした後に細孔 f から噴出させ200気圧から16気圧に下げる。噴出空気はジュール=トムソン効果により温度が下がるが、その冷気の大部分は三重管の中間層に入り、内部の空気を冷やしながら g を通ってポンプ b に戻り以上の過程を繰り返す。
一方fから噴出した16気圧の空気を細孔 h から更に大気圧の元に噴出させるとジュール=トムソン効果によりさらに冷却し一部が液化する。この噴出で液化した空気はデュワー瓶 i にたまり、それを j から取り出す。液化しなかった空気は三重管の外側の層を通り、内側の空気を冷やしながら大気中に放出される。
リンデ・ハンプソンサイクルの熱力学的な説明は「熱機関の効率(冷凍サイクル)」3.(6)の[補足説明]中の引用文1と引用文2をご覧下さい。
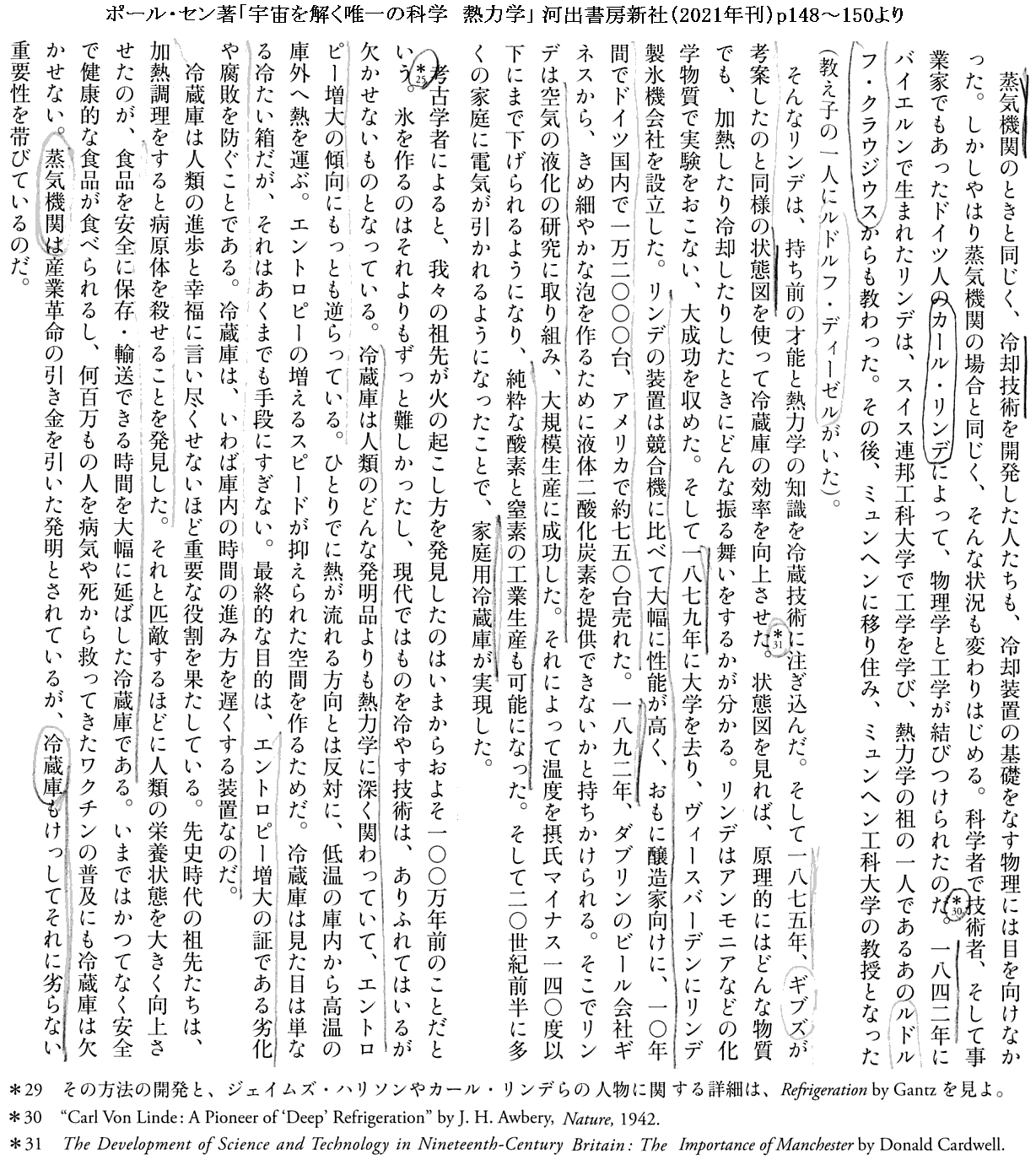
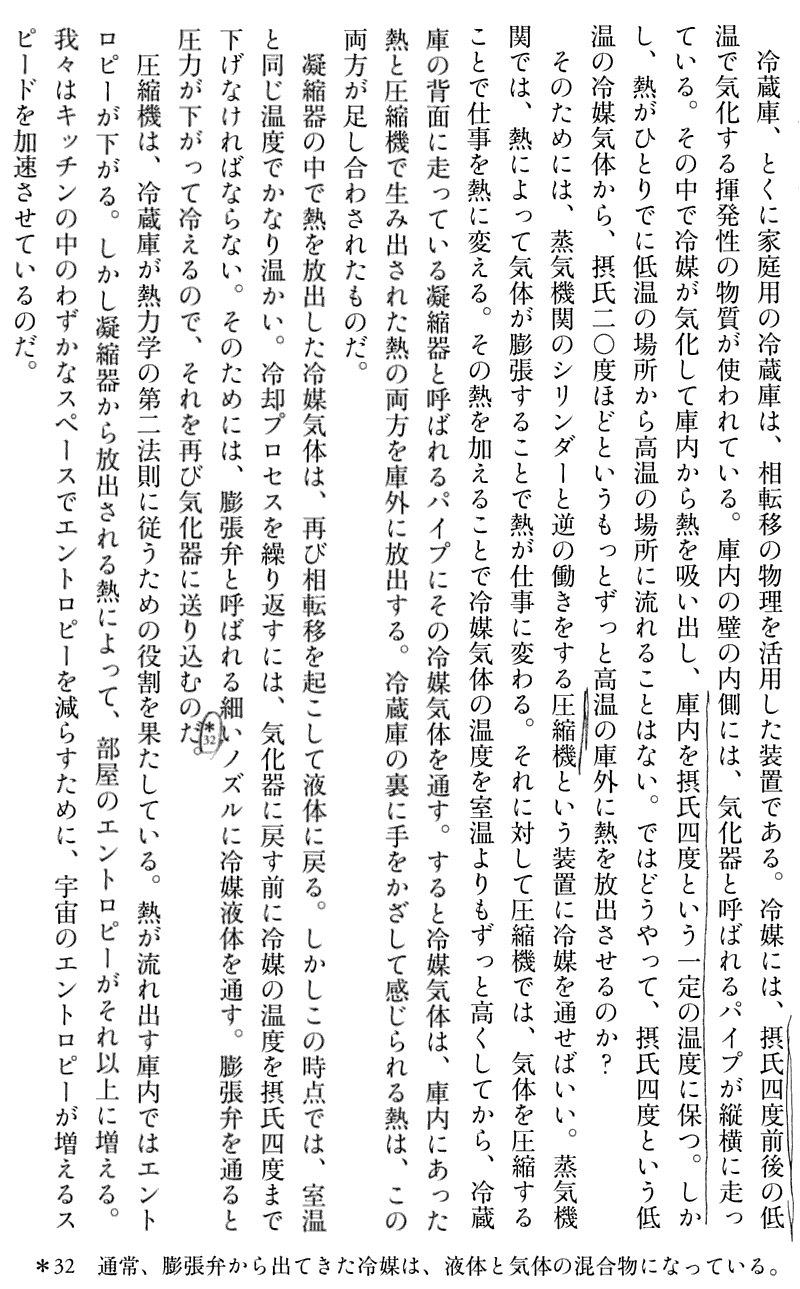
上記作動原理の詳細は「熱機関の効率(冷凍サイクル)」2.(1)をご覧下さい。
1895年
ほぼ同じ頃、イギリスのウイリアム・ハンプソン(William Hampson) も同様な工業的空気液化装置の特許を取っている。ハンプソンの熱交換器は螺旋状に巻いた導管を層状に重ねたもので、その中を高圧の空気が流れる。低圧・低温の空気は高圧導管と直交して流れるようになっており、全体は断熱した器内に入れてある。リンデの熱交換器に比べて熱容量が小さく運転開始から液化までの時間はリンデの装置よりも短かったようです。
いずれにしても、彼らの装置は“熱交換器”と“ジュール=トムソン効果”を最初に採用した装置で、今日リンデ=ハンプソン型空気液化機と言われる。
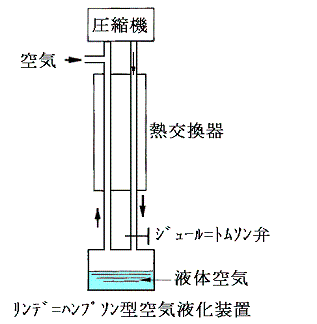
リンデとハンプソンの“熱交換器”の構造は少し違うが原理は全く同じで、低温度にした気体で新しく入る高温・高圧の気体を冷却する。この過程は連続的に行うことができるので、大量の空気を液化することが可能になった。
1898年
クラコフ大学での研究を聞いたイギリスのジェームス・デュワー(James Dewar 1842〜1923年)は1898年に水素の液化を試みた。[デュワーの小伝]
まず液体酸素[大気圧の沸点-183℃(90.2K)]を大量に作りデュワー瓶に蓄えた。この液体酸素を減圧排気(0.04気圧以下)によりさらに-205℃(68K)まで冷却した。この中に、18MPa(約180気圧)まで加圧した水素を通して冷やした後、細孔から噴出させてジュール・トムソン効果を利用してさらに冷却して、史上初めて20ccばかりの液体水素の生成に成功した。
ところで、水素の臨界温度は-240℃(33.2K)、臨界圧力12.8気圧だから、-205℃(68K)ではいくら加圧しても液化は起こらない。ジュール・トムソン効果の使用が必須だった。
ちなみに、水素のジュールトムソン効果の温度逆転領域は下図の様になります。この温度降下領域を最初に明らかにしたのはファン・デル・ワールスです。彼の研究に着目していたデュワーはその成果を利用することができたのです[詳細は別稿「ファン・デル・ワールスの状態方程式」5.(3)参照]。ちなみに、大気圧下における液体水素の沸点は-253℃(20.4K)です。
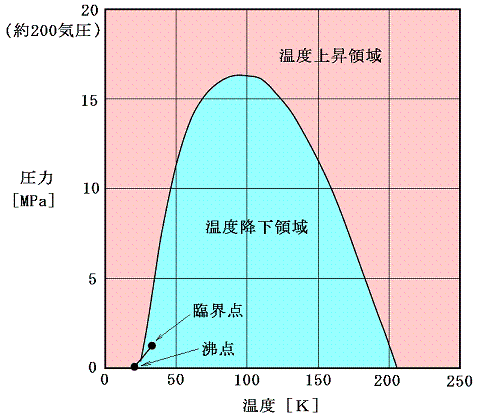
水素を液化するときには中の不純物を十分に取り除いておかなければならない。不純物としては圧縮機からの油、水蒸気、酸素、窒素などがある。酸素があれば爆発のおそれがある。また不純物は低温度になると固化して配管をふさいで破裂させたり、可動部分を動かなくさせたりする。また上図からわかるように温度が200K以上の高圧水素が大気中に漏れ出すとジュール=トムソン効果により高温になるため、酸素と混じり合い爆発事故となる。だから水素の液化は今日我々が想像する以上に難しかった様です。
デュワーは1901年に、さらにヘリウムの液化を試みたが成功しなかった。1903年にイギリスのトラバース(Morris Travers)が液体水素で冷やしたヘリウムを60気圧まで圧縮してみたが液化しなかった。後に明らかになったヘリウムの臨界温度はさらに低かったので、液体水素の沸点温度-253℃(20.4K)付近ではいくら加圧しても液化は無理です。前出のオルスチェフスキーも1905年に試みたが成功しなかった。
(4)20世紀前半
1902年
重工業が発達すると大量の酸素が必要になるので、それをいかにして経済的につくるかは重要な問題です。水の電気分解で酸素をつくると1m3の酵素をつくるのに1.84kWhの電力を必要とするが、空気から分離すると0.6〜1.7kWhの電力でよい。
リンデは空気液化機を発明すると間もなく1902年には液体空気から酸素を分離する装置を考案した。液体酸素の沸点は-183℃で液体チッ素の沸点は-195.8℃ですから、液体空気を分留すれば酸素とチッ素を分離することができると考えたリンデは、下図のような装置を考案した。
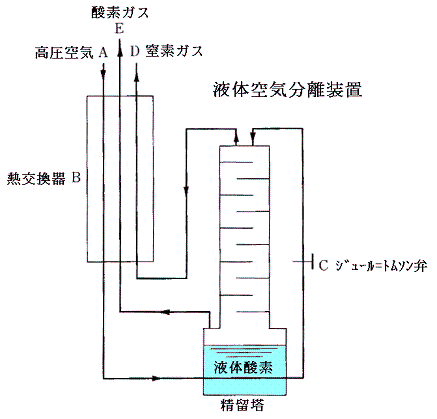
水蒸気と炭酸ガスを除いた高圧空気は A から熱交換器 B を通り精留塔の下部を経てからジュール=トムソン弁 C を通って液化する。精留塔の内部には多くの孔のあいた棚があり液体酸素は下部に溜まりチッ素は上部から熱交換器を通り D から出て行く。もしチッ素も必要なときにはこれでは純度が悪いので次図に示したように2個の精留塔を縦につないで複精留塔にすると高純度のチッ素が得られる。
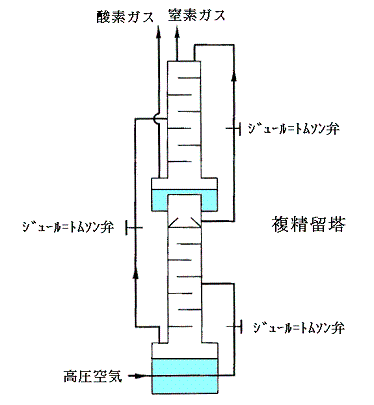
1902年
フランス人のクロード(Georges Claude 1870〜1960年)は1902年に断熱膨張を利用する空気液化法を発明して特許を取り、この年に実用化して新しい会社を起こした。そして1907年には空気からヘリウム、ネオンを分離することに成功した。
これは気体の圧力を高めておいてから、外部に仕事をさせながら準静的に膨張させるとエネルギーを失って温度が下がる現象を利用したものです。そのとき、別稿「気体の断熱変化」で説明したように、最初の圧力、体積、絶対温度が(p1,v1,T1)、断熱膨張後のそれを(p2,v2,T2)とすると、
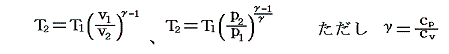
の関係が成り立つ。たとえば空気の場合γ=1.4だから、常温(300K)で80気圧の空気を1気圧まで断熱膨張させると、計算上ではT2=T1×0.01250.286=300×0.2859=86Kまで下がる。[ジュール=トムソン効果では20℃程度しか下がらない。]
これに着目したフランスのクロードは往復動の膨張機を使い断熱膨張だけで空気を液化しようと試みたが機械的に難問が現れ、その後ハイランドがさらに改良してクロード=ハイランド型の空気液化機を考案した。これは下図のようになっている
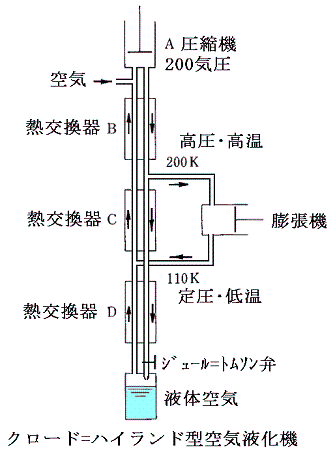
Aは圧縮機でB、C、Dは熱交換器です。Bを通過した高圧空気は一部分、膨張機に入る。これは往復動のエンジンで蒸気機関の蒸気の代わりに高圧空気が入るものと思えばよい。膨張機を出た低圧・低温の空気は熱交換器C、Bを通り圧縮機からの高圧・高温の空気を冷却する。その空気は熱交換器Dを通って冷却された後にジュール=トムソン弁で膨張して液化する。
クロードはその後ネオン灯を発明(1910年)し、酸素製鋼法を研究した。また1917年には高圧によるアンモニア合成法を発明した。
1908年
オランダ人のハイケ・カマリング・オネス(Heike Kamerlingh Onnes 1853〜1926年) は1908年に液体空気を寒剤としてジュール=トムソン効果を利用して液体水素をつくり、次にそうして造った液体水素を寒剤としジュール=トムソン効果を利用してヘリウムの液化に初めて成功した。ちなみに今日わかっているヘリウムの大気圧での沸点は-268.945℃(4.2K)、臨界温度は-267.96℃(5.2K)、臨界圧力は2.24気圧です。[ヘリウムの発見][オネスの小伝]
ヘリウムを液化するにはまずその臨界温度を知る必要がある。オネスは100℃〜-216℃の範囲でヘリウムの体積と圧力を精密に測定した。そしてファン・デル・ワールスの式を用いてヘリウムの臨界温度を6Kあたりであると推定した[実際は5.2K、詳細は別稿「ファン・デル・ワールスの状態方程式」3.(3)参照]。
また同時にファン・デル・ワースルの式からジュール・トムソン効果の温度降下領域の温度圧力範囲を調べ加圧圧力を20気圧とする見当をつけた。ヘリウムの場合膨張開始圧力が高すぎるとジュール・トムソン効果は逆転して温度上昇を招く。[詳細は別稿「ファン・デル・ワールスの状態方程式」5.(3)参照]
最初のヘリウム液化装置は、およそ下図のようなものであった。
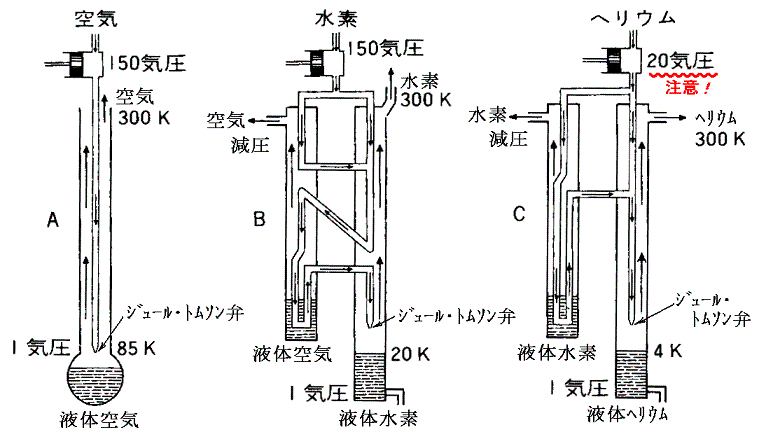
1908年7月9日。まず装置Aにより75リットルの液体空気が作られた。翌日の早朝から装置Bにより液体水素の液化を始め午後には20リットルの液体水素ができたので、午後4時20分から装置Cによりヘリウムの液化に取りかかった。午後7時30分、液体水素がなくなりかけた頃についにヘリウムの液化が確認された。これにより、気体は全て液化可能なことが明らかになった。この装置の詳細についてはオネスのノーベル賞講演(1913年)が詳しい。
オネスは1922年、強力な排気ポンプを使ってヘリウムの蒸気圧を下げて、最終的に0.83Kの温度に到達した。これは従来の方法で達成できた最低温度ですが、さらに低温にするには全く新しい原理に基づく磁気冷却法の発見を待たねばらならかった。
1933年
1926年にアメリカのジオーク(William Francis Giauque 1895〜1982年 J. Am. Chem. Soc., 49(8), 1864〜1870,
1927年)とドイツのデバイ(Peter Joseph Wilhelm Debye 1884〜1966年 Ann. Phys., 386, 1154〜1160, 1926年)が全く独立に、新しい冷却法を発表した。それは常磁性塩の磁気冷却法と呼ばれるもので、ネルンスト(Hermann Walter Nernst 1864〜1941年)が1906年に発見した熱力学第三法則が基になっている。
この法則は「いかなる方法を用いても絶対零度には到達することはできない。ただしいくらでも接近はできる。」あるいは「エントロピーは絶対零度ではゼロになる」と表現される。この当たりの正確な意味は別稿「電気化学ポテンシャルと熱力学第三法則」3.を参照。また、ネルンストについては、弟子のメンデルスゾーンが書いたネルンストの伝記「ネルンストの世界」を参照。
物質の磁性には強磁性、常磁性、反磁性の3種類があるが、磁気冷却法に必要なのは常磁性体である。常磁性体は小磁石の集合体とみなされ、低温度になると小磁性体群は規則正しい配列をとってくる。これはエントロピーが小さい状態です。温度が上がると配列が乱され不規則性が増すので、エントロピーは大きくなる。そのため、常磁性体の磁性は低温度で強く、高温度で弱い。
磁性の強弱を示すには磁化率を使うが、これは外部から作用させる磁場の強さで磁化の強さを割った値です。常磁性体の磁化率と温度の関係を詳しく研究したのはピエール・キュリー(Pierre
Curie 1859〜1906年) で20世紀の初め頃であった。彼はマダム・キュリーの御主人ですがラジウムの研究と同様、磁気の研究にも優れた業績を残している。
キュリーの研究によると常磁性体の磁化率は絶対温度に逆比例する[キュリーの法則]。超低温ではキュリーの法則からはずれてくる物質もあるが、希土類元素の化合物とか鉄族元素の化合物には超低温でもキュリーの法則に従うものがある。ガドリニウムの化合物などがそれです。希土類の塩は大きな常磁性磁化率を持っているのでこの方法に適している。
このような物質を冷却すると、物質間の小磁石の熱運動は次第に静かになるからエントロピーも次第に減っていく。そこで外部から磁場を作用させると小磁石の原子は一定の方向に並ぶので、エントロピーはさらに小さくなる。つまり、エントロピーは系の無秩序の指標ですが、外部磁場が加わると素磁子を整列させ系に秩序をもたらすので、同じ温度で外部磁場がゼロの時よりもエントロピーは減少するのです。
ここで外部からの熱の出入を断ち、磁場を取り去る。このとき断熱変化故にエントロピーは一定に保たれているが、外部磁場がなくなったために磁気双極子の配列はある程度無秩序になる。すなわちエントロピーの磁気による部分(これはエントロピーの大部分を占める)がかなり増加するので、必然的に温度が下がることになる。これが磁気冷却法の原理です。
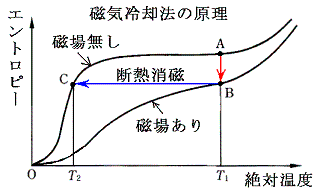
ACO曲線は常磁性体のエンロピーと絶対温度の関係です。BO曲線は磁場を作用させたときのエントロピーと絶対温度の関係を示したものです。磁場をかけないままで冷却し、最後に到達した温度をT1とするとA点がその状態を示している。温度をT1に保ちながら外部から磁場を作用させるとB点の状態になる。ここで外部からの熱の出入を断ち磁場を取り去ると、断熱状態だからエントロピー一定でC点の状態に移る。この点の温度はT2で明らかに最初の温度より下がっている。熱の出入を断ち磁場をも取り去るので断熱消磁冷却法ともいわれる。
このとき以下のことに注意すべきです。これはエントロピーを一定に保ちながら温度以外の変数を変えることにより温度を下げるのですが、はじめの温度が有限である限り、エントロピーも有限です(第三法則により)ので、磁場や体積(普通の断熱膨張)などの他の変数をどのように変化させても終わりの温度は有限です。このため断熱省磁を繰り返せばいくらでも絶対零度に近づくことはできるが、有限回の操作では絶対零度に決して到達できない。
磁気冷却の最初の実験が行われたのは1933年4月で、ジオークがカリフォルニアのバークレー大学で成功した。デバイは理論物理学者であるから自分で実験はしなかった。
次図は磁気冷却の装置の模式図で、常磁性物質Aは真空にできる箱B内に吊るしてある。B内には初めヘリウムガスが入れてある。N、Sは電磁石の両極です。
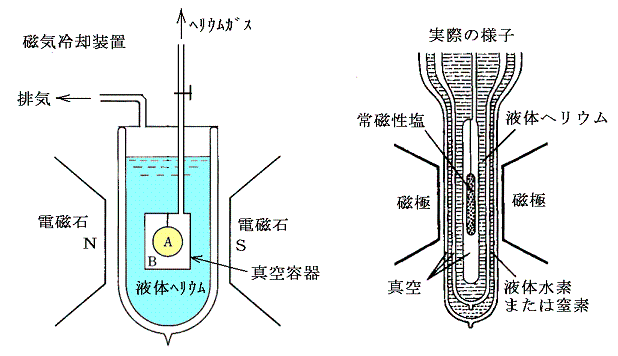
ジオークが実際に使った常磁性物質は硫酸ガドリニウムGd2(SO4)3・8H2Oです。これを、排気ポンプを使って減圧し気化熱で1K近くまで温度を下げた液体ヘリウムで冷却する。
それから磁場を作用させるとエントロピーが減少し常磁性体から熱が出るので、それは周囲の液体ヘリウムで冷却する。このとき常磁性体を入れてある容器にはヘリウムガスを入れておき、常磁性体からの熱を取り出して周囲の液体ヘリウムに伝えやすくする。
常磁性体が充分に冷却されたと思われるとき容器内のヘリウムを排気し外部からの熱の流入を止める。それから磁場を取り去ると常磁性体は0.25Kの低温となった。
同様な実験はライデンでも行われたがバークレーの方が僅かに早かった。その後オックスフォードとかケンブリッジなどで磁気冷却の実験が成功し、今では広く一般に行われるようになった。こうして0.01Kより低い温度がたやすく得られるようになった。
さらに超低温の0.001K付近を得るには2段磁気冷却法が用いられる。下図はその模式図です。
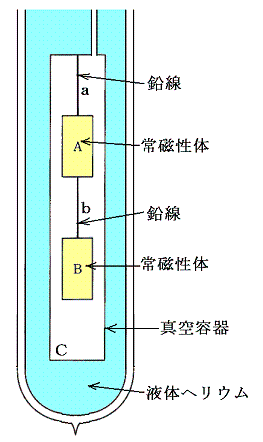
AとBは常磁性物質です。それを鉛線a、bで、真空にできる器C内に吊るしてある。Cの外側は液体ヘリウムで冷却されている。最初はA、B同時に磁場を作用させる。そのときに発生する熱はa、bを通じて外部の液体ヘリウムに逃げる。鉛は7.2K以下では超伝導状態になるが、強い磁場のために超伝導状態は壊れており、熱を伝えることができる。
次に磁場を下方に移動させる(普通は固定された磁場中をデュワー瓶容器全体を上方に引き上げて実現する)とAは断熱消磁で温度が下がる。そのとき鉛線aの位置の磁場もなくなるのでaは超伝導状態になりaを通じての外部からの熱の流入は断たれるが、Bの温度は、まだ下がっていないので熱はbを通ってAに逃げる。
そのとき、bはまだ強い磁場の影響下で超伝導状態は壊れており熱を伝えることができる。[超伝導状態になると熱を伝えなくなる理由の説明は省略]
そこで電磁石の電流を切るとBも断熱消磁で温度が下がるが、鉛線bも超伝導の状態になりAとBは断熱的になる。従ってBはAよりさらに低温度になる。Aに下表のFAAを使いBにCPAを使って、0.4Tの磁場を作用させて0.003Kに達した実験がある。
磁気冷却に使われる常磁性物質を下表に掲げる。T(K)は液体ヘリウムで1.1Kまで冷却した後、5000ガウスの磁場を作用させた場合に到達できる絶対温度を示している。
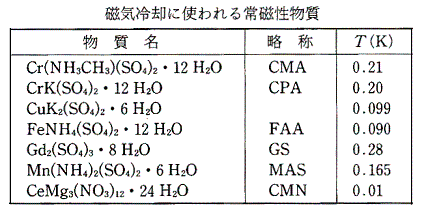
磁気冷却に便われる電磁石で、鉄芯のあるものは、比較的少ない電力で使用できるのはよいが、鉄磁性の飽和現象のために2〜3T(1Tテスラ=104Gガウス)の磁場までしか得られない。それ以上の強磁場を必要とするときは鉄芯なしのソレノイドだけの電磁石を用いる。いずれにしても大電力を必要とし、大量のジュール熱が発生するので冷却するのが大変になる。そのため最近は超伝導磁石が使われる。
1934年
ソビエト連邦のカピッツァ(Peter Leonidovich Kapitza 1894〜1979年)は1934年にヘリウム液化機に膨張機を用いた。30気圧に圧縮されたヘリウムは液体チッ素で予冷されて膨張機を通る。クロード=ハイランド型の空気液化機と同じように最後はジュールートムソン弁を通って液体ヘリウムになる。これは膨張機を用いたヘリウム液化機の最初のものです。
1939年
カピッツァは1939年に膨張タービンを使う空気液化装置を世界で最初に実用化するのに成功した。その装置は下図の様なものです。
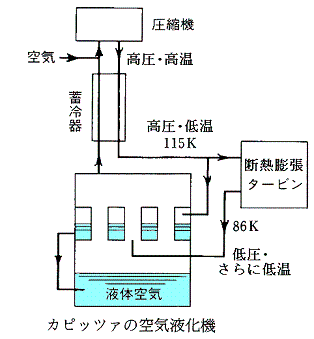
タービンの回転部の直径は8cmで、重さは250g、回転数は毎分4万回転です。熱交換器の代わりに蓄冷器を使う。蓄冷器は断熱されており、中には厚さ0.1mmの金属リボンにひだをつけたものが巻いてある。タービンを通って冷却された空気は蓄冷器を通って金属リボンを冷却する。
次には弁の切替えで高温の空気が冷却されている蓄冷器を流れて低温になる。この繰り返しで蓄冷器は熱交換器と同じ役目をする。蓄冷器では空気中の水蒸気や炭酸ガスを取り除くための特別な空気清浄装置を必要としないので、今日の大型空気液化機では熱交換器の代わりに使われる。
1947年
アメリカ人のコリンズ(Samuel Collins 1898〜1984年)が、1947年簡便なヘリウム液化機を発明した。それまでは液体ヘリウムが使える研究所は世界に数カ所しかなかったが、コリンズの学生で協力者であったD.O.マクマホンが、この液化機を大量生産して世界中に販売した。それは商業的に成功してたくさん売れたために、このとき以後、世界各地で極低温が利用できるようになった。そのため彼の装置は、低温物理学発展へ多大な貢献をした。
コリンズのヘリウム液化機は、前に述べたカピッツァの考案した装置と、原理は同じで下図の様なものです。
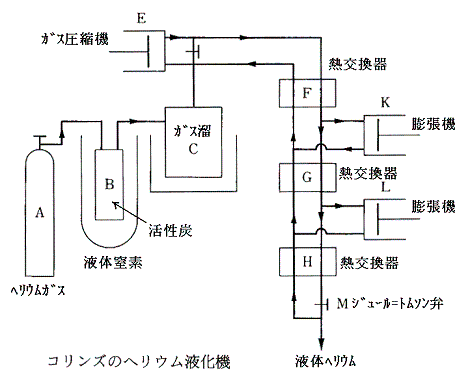
Aはヘリウムのボンベで、Bは液体チッ素で冷した活性炭です。AからのヘリスムはBで清浄され、ガス溜Cに入る。Eは圧縮機でヘリウムは14気圧に圧縮される。F、G、Hは熱交換器でK、Lは往復動の膨張機です。それを通るとヘリウムは8Kまで低温になり、Mのジュール=トムソン弁を通ってさらに冷却され液化する。
(5)20世紀後半
1950〜1969年
1950年にソ連のI.Y.ポメランチュクは液体および固体のヘリウム3Heが低温で示す異常な性質(ポメランチュク効果)に基づく冷却法を提案した。しかし、その実現は難しく長いこと不可能なままであったが、1965年にソ連のモスクワ物理学研究所で部分的に成功、1969年にアメリカのカルフォルニア大学で2mmKに冷却するのに成功した。
この方法は、込み入っているので説明は省略する。[詳しくは参考文献4.参照]
1956年
これまでの磁気冷却は原子(電子)の磁性を使ったものであったが、原子核にも磁性があるのが明らかになったので、それを利用する核磁気冷却が可能になった。核磁気冷却の可能性に気がついたのはライデン大学のC.J.ゴーターやオックスフォード大学のF.E.シモン(Franz Eugen Simon 後に Francis Simon 1893〜1956年)で、1930年代のことであった。しかし実験が成功したのは1956年で、シモンとその共同研究者達です。[シモン小伝]
ここで以下の点に注意すべきです。原子の持つ磁気モーメントには電子によるものと原子核によるものがあるが、モーメントの大きさは後者の方がずっと小さく(約1/2000)、従って磁気モーメントの相互作用も小さい。そのため互いの相互作用で核素磁子が自発的に並び始める温度がより低い。つまり、その温度以上ではアトランダムな状況になり得るということです。すなわち、磁気冷却で到達できる温度の下限は素磁子が自発的に並び始める温度なのですが、核断熱消磁の方がより低温まで到達できることを意味する。
原子核による磁気モーメントが小さいということは、エントロピーの外部磁場・温度変数曲線
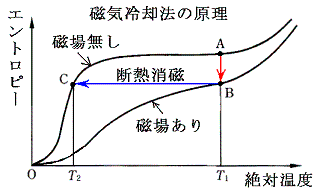
において、外部磁場無しの場合の曲線カーブがずっと左側に寄っているということです。
すなわち、核磁気モーメントは小さいために普通の電子磁気モーメントの断熱消磁よりも強力な磁場が必要で開始温度も低くしなければならないが、それが可能ならばより低い温度まで到達できる。
核断熱消磁冷却はすでに述べた2段磁気冷却に似ているが、作用させる磁場の強さが大きくなっている。シモン達が1956年に行った最初の実験では銅を使った。
まず電子磁気冷却で常磁性体を0.02Kにしておき、それで銅を冷却する。予備冷却媒体の常磁性体と銅は、すでに述べた超伝導金属線による導熱スイッチでつながれている。この金属線の部分にはあらかじめ磁場をかけて超伝導状態を壊しておき、熱が伝わるようにしてある。
それから3T(1Tテスラ=104Gガウス)の強さの磁場を銅に作用させて銅原子核を磁化させる。磁化熱は超伝導熱スイッチを使って、それまで冷却に使っていた常磁性体へ取り去る。その後、超伝導熱スイッチの金属線の部分の磁場を切り熱伝導スイッチを切る。
そして、銅部分に加えていた外部磁場を減少させて核磁気冷却を行い、0.00016Kの超低温に達することができた。しかしこの超低温は銅の原子核に関係した温度であって、周囲にある物質の温度ではない。実験に使われた銅の温度は0.01Kの付近であろう。
核磁気冷却に使われる物質は銅以外にアルミニウムAl、バナジウムV、ニオブNb、インジウムIn、タリウムTlなどがある。下表は、最初の温度が10mKに予冷却された、それらの物質に6Tの強さの磁場を作用させて核断熱消磁冷却したとき到達する温度をmK(1mK=0.001K)で示したものです。
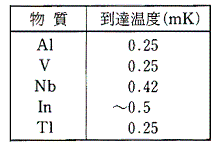
これ以上の説明は省略する。[詳しくは参考文献4.参照]
1962〜1966年
1962年にイギリスのH.ロンドン、G.R.クラーク、E.メンドーザらが希釈冷却法の原理を示した。実際に実用化されたのはソ連で1965年後半、イギリスで1966年始めです。
これはヘリウム3Heとヘリウム4Heの低温における混合物が示す特異な性質に基づいている。冷却の原理はかなり込み入っているので説明は省略する。[詳しくは参考文献4.参照]
2.低温を生み出す三つの方法
冷凍機や熱ポンプは以下に述べる三つの性質のいずれかを利用している。
1.液体の蒸発熱
液化しやすい気体を圧縮・冷却して液体にし、その蒸発熱を利用する。そのとき液体と平衡にある蒸気の圧力(飽和蒸気圧)は温度が高まると大きくなる。温度を下げるには液体と平衡にある蒸気をポンプで取り除いて減圧し、蒸発を盛んにすればよい。飽和蒸気圧がさがるので、平衡時の温度は下がってくる。つまり飽和蒸気圧を下げれば、より低温で沸騰する。沸点とは液体の内部に発生した気泡の圧力(飽和蒸気)が液体にかかる圧力を超えたとき起こる現象。
例えば二酸化硫黄SO2の沸点は1気圧のもとでは-10℃ですが、20mmHgまで減圧すると沸点は降下して-70℃となる。この温度の二酸化硫黄を用いて二酸化炭素ガスCO2を冷却すれば、1気圧のもとで容易に固化する。固体となった二酸化炭素を数mmHgの減圧下で蒸発させると-130℃程度の低温が得られる。この温度になると、圧縮して高圧にすれば、酸素をも液化することができる。酸素の大気圧下におけるは沸点-183℃(90K)であるが、酸素の飽和蒸気圧を高くすると、-183℃よりも高い温度-130℃でも液体状態の酸素と酸素ガスの平衡状態が実現するということです。
1.(3)で述べたラウール・ピクテの酸素液化法はこの方法を用いたものです。しかし現在では、気体の液化にこの方法が使われることはほとんどない。
1834年にヤコブ・パーキンスによって最初に実用化された冷凍機はまさにエーテルの気化熱を利用するものでした。冷媒には、ジエチルエーテルや硫化ジメチルエーテルなど、減圧によって容易に蒸発する液体が用いられる。また、二酸化硫黄やアンモニアなどの加圧によって容易に液化する気体を用いることもできる。
蒸発による冷却法は工業的なドライアイス(固体二酸化炭素)の製造にも利用される。
気体と液体の相変化のメカニズムは非常にわかりにくい。たとえば1気圧のもとでの100℃における水と水蒸気の相変化を考える。着目している物質(水)と外界の温度はほとんど同じであるにも係わらず、外界の温度が100℃よりもごく僅か高くなると外界から水へエネルギー(熱)が流入して水は100℃の気体(水蒸気)になる。逆に、外界の温度が100℃よりもごく僅か低くなると100℃の水蒸気から外界へエネルギー(熱)が流出して水蒸気は100℃の液体(水)になる。
ここで、当然のことながら100℃の水と100℃の水蒸気では水蒸気の方が熱を吸収して[厳密に言うと外界との仕事のやりとりもあるが]より高いエネルギー状態にある。なぜこのような大幅なエネルギーの移動が生じるのであろうか。以下でそのメカニズムを説明する。
この時の相変化は平衡状態を保ちながら無限にゆっくりと行うことができるので、可逆過程です。そのため液体が気体になる、あるいは気体が液体になる相変化が起こっても、水・水蒸気と外界を含めた系全体としてのエントロピーはほとんど変化しない。水が水蒸気になる場合には、水(水蒸気)が吸収する熱量Qをそのときの絶対温度Tで割った量だけ水(水蒸気)のエントロピーは増大するが、そのとき外界には全く同量の熱量Qを絶対温度Tのもとで失うので同じだけのエントロピー減少が生ずる。逆の相変化が起こった場合も同様で、系全体としてのエントロピーはほとんど変化しないのです。
最初に水と水蒸気からなる系(1気圧、100℃)が温度100℃の外界と平衡にあり共存しているとする。
ここで、圧力(1気圧)を一定に保ったまま外界の温度を100℃よりもごく僅か+Δt℃高くしてみる。そうすると、100℃で熱を吸収した水のエントロピー増加量が、(100+Δt)℃で熱を失った外界のエントロピー減少量よりもごく僅か多くなる。このごくわずかの温度差がトータルとしてのエントロピー増大を生み出し、水は不可逆的に外界から熱を吸収してすべて水蒸気に気化してゆく。
逆に1気圧の元で外界の温度を100℃よりもごく僅か−Δt℃低くすると、水蒸気は不可逆的に全て水に凝縮する。この場合100℃で熱を放出した水蒸気のエントロピー減少量よりも、(100−Δt)℃で熱を得た外界のエントロピー増大量がごく僅か多くなるからです。このようになることは別稿「絶対温度とは何か」6.(5)2.や、別稿「ガス動力サイクル」1.(1)4.で説明した。
上記は外圧一定の元での温度のごく僅かの変化で生じる相変化だったが、温度一定でも水と水蒸気の系にかかっている外圧をごく僅か変化させることで同様な相変化を起こすことができる。もちろんこの場合も水と水蒸気からなる部分系の体積は大きく変化する。
蒸発する場合も、凝縮する場合も、水と外界を含めた全体系のエネルギーは保存されるし、エントロピーもほとんど変化しない。しかし温度のごく僅かの違いが、相変化に伴なう系全体のエントロピーにごくわずかの増大を生じ、それがエネルギー分担の大幅な変更を促す。水(冷媒系)と外界の温度や圧力はほとんど同じなのに、両者が担うエネルギーやエントロピーの分配の様子は大きく変化する。たとえごく僅かの温度差でもあっても、どちらの場合も高温部から低温部に熱が流れていく不可逆変化であることは確かです。
それでは温度やエントロピーとは何なのかということになるが、熱力学からはこれ以上のことはいえない。統計力学的に言うと
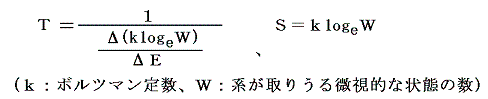
の様な量ですが、ここではこれ以上の説明に立ち入らない。
いずれにしても絶対温度とエントロピーは上記のような性質を持つ量なのだ。
蒸発熱を利用する実際の冷却機では、冷媒の圧力を調整することによって、熱を吸収する所でも、熱を放出する所でも、その位置における圧力での気相・液相平衡温度と外界温度との差が大きくなるようにしてある。温度差を大きくすれば、より急速に熱が移動する。
2.気体の断熱膨張
1844年にアメリカ人の医者ジョン・ゴーリーによって考案された装置は、この効果を利用する最初の実用的な冷凍機です。初期に於いて、海上を航行する冷凍船には、この空気サイクル冷凍機が盛んに使われた。それはエーテルなどの引火性液体を使う前記の方法は火災の危険性がつねに付きまとったからです。
1.(4)で述べたクロード=ハイランド型の空気液化機やコリンズのヘリウム液化機は、その一部にこの原理による冷却を用いている。今日市販されている気体液化装置にはこの原理を用いるものが多い。
また別稿で述べたスターリングサイクルを逆転させて冷凍機とするのもこの原理に基づく。オランダのフィリップ社はこの原理に基づく小型で便利な空気液化装置を製造して販売した。
気体を断熱的に膨張させると、外部にする仕事のために気体の内部エネルギーを失う。そのとき、なぜ温度が下がるかといえば、気体が熱運動による運動エネルギーを持って壁に衝突したとき、その壁が気体の衝突による衝撃で後退した場合、運動量保存則から明らかなように、跳ね返される気体の速度が減少し運動エネルギーを失うからです。高校物理で習うように理想気体の場合、運動エネルギーが減少することこそ温度が下がることを意味する。このあたりの詳細はこちらを参照されたし。
最初の体積、絶対温度を(v1,T1)、断熱膨張後のそれを(v2,T2)とすると、別稿「気体の断熱変化」で説明したように、
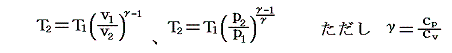
の関係が成り立つ。たとえば空気の場合γ=1.4だから、体積が5倍に膨張すれば、計算上ではT2=T1×0.20.4=0.53×T1となる。
断熱膨張冷却の原理を利用した冷凍機の概念図を次に示す。
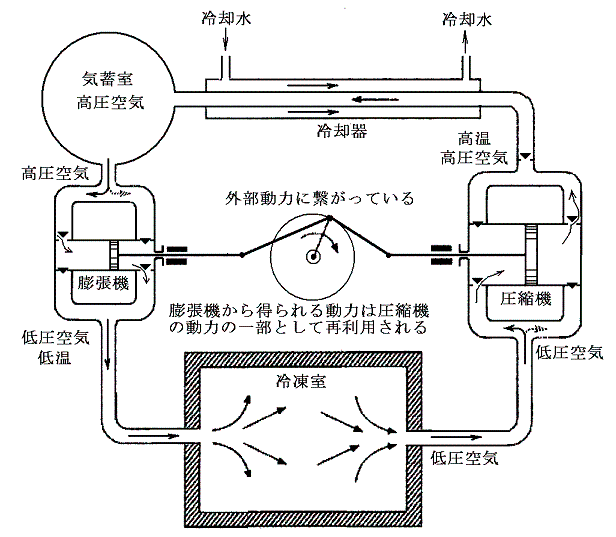
これは、1.(2)で説明したジョン・ゴーリーの空気冷却機械そのものです。
3.ジュール・トムソン効果
これは1852年にジュールとトムソンが発見した現象ですが、2.で述べた断熱膨張による外部仕事とは違って、気体同士の内部仕事によって気体の温度が下がる。リンデ、デュワー、カマリング・オネスが気体の液化に用いたのはこの方法です。
分子間力の働かない理想気体では、真空中に噴出させても温度は変化しない。それは真空の部屋に気体分子が拡散・侵入するとき外部に対して仕事をしないので、そのままの運動エネルギーを保ったままになるからです。その真空の部屋の壁は固定されているので、その部屋の壁と衝突しても完全弾性衝突のために、以後も運動エネルギーの変化は生じない。
ところが、分子間力のある実在気体を、高密度に圧縮して分子間力の働く近距離中に存在する状態から真空の部屋に吹き出し膨張させるとお互いの分子間引力を振り切るための仕事がなされることになる。つまり粒子間距離を大きくした場合、粒子どうしの引力に逆らう仕事をしなければならない。そのため運動エネルギーは減少することになる。これは温度の減少を意味する。これが、高圧に圧縮・冷却した実在気体を絞り弁から低圧の部屋に噴出させると温度が低下するジュール=トムソン効果です。
しかし、ここで注意しなければならいことがある。吹き出す前のガスの温度と圧力が高いときには、分子の運動エネルギーが大きいことと密度が高くて衝突の頻度が大きいために、相互に斥力の領域[下図のAの領域]に入り込んでいる時間が長くなる。そのため、吹き出しによって平均距離を大きくしたとき平均のポテンシャルエネルギーが下がり、ガスの温度はむしろ上昇する。[詳細は別稿「ファン・デル・ワールスの状態方程式」5.(3)参照]
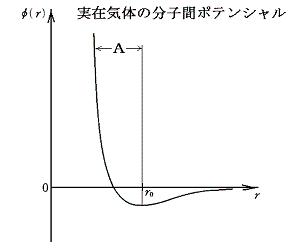
そのため温度が下がるためには始めの状態の温度と密度(圧力)がある範囲以下でなければならない。低圧の状況下への膨張に伴うジュール=トムソン効果による温度降下領域(下図空色の(∂T/∂p)H>0の領域)をN2と4Heを例として示す。ヘリウム4Heの場合、この効果で温度降下が起こるは-233℃(40K)以下というきわめて低い温度領域です。[下右図参照]。これは上図のポテンシャルの谷が非常に浅いことが原因です。
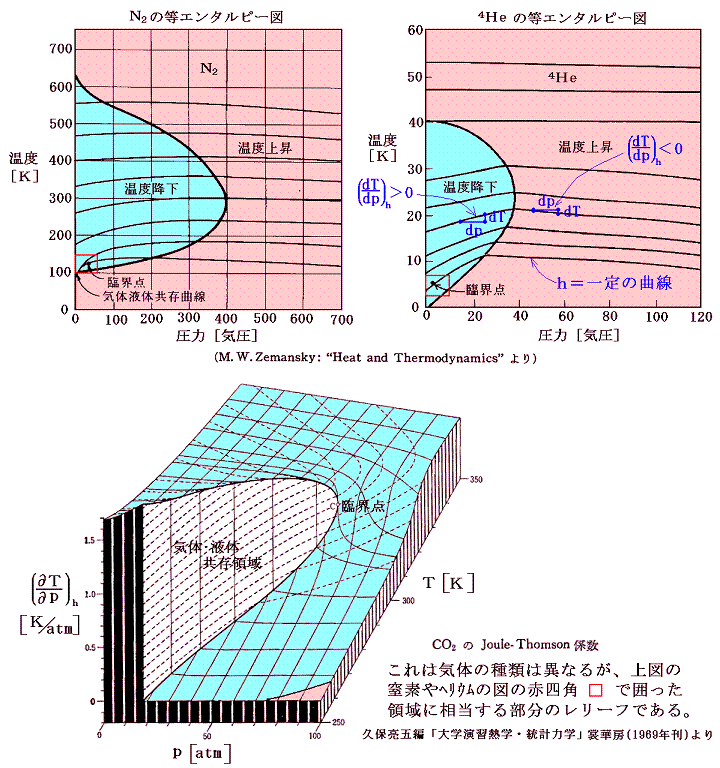
ジュール=トムソン効果の詳細は別稿「ファン・デル・ワールスの状態方程式」を御覧下さい。温度降下領域の境界(逆転曲線)が上図の様になることは、「ファン・デル・ワールスの状態方程式」5.(3)で説明しています。
3.参考文献
このHPの内容は下記の文献に全面的に依存しています。図や表もそれらから引用しました。感謝!
- ジョン・F・サンドフォード著 現代の科学20「熱機関」河出書房新社(1980年刊)
古い本ですが図書館にはきっとあると思います。
- 奥田毅 著「低温小史−超伝導へのみち」内田老鶴圃(1992年刊)
歴史的な事柄についてはこの本から多数引用しました。ただし、少し意味が通らないところを自分なりに補足したのですが、間違っているところがあるかもしれません。とても面白い本ですので読まれることを勧めます。
- 谷崎義衛著「化学の話シリーズ4 気体の話」培風館(1983年刊)
高校生向きでとても解りやすい。幾つかの図と説明を利用させてもらいました。
- ユージン・M・リフシッツ、その他著「現代物理の世界-Ⅴ 極低温の世界」講談社(1972年刊)
O.V.ラウナスマーが書いた第三章に、希釈冷却法、ポメランチュク冷却法、核磁気冷却法の解りやすい説明あり。