�@���̃y�[�W�������������������̃o�[�W�����������p�������B�u���E�U�[�ł͌��ɂ����̂ł�������͑N���ł��B
���U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�̕��ː��ϊ����i1903�N�j
�@���U�t�H�[�h�iErnest Rutherford�A�p�A1871�`1937�j�ƃ\�f�C�iFrederick Soddy�A�p�A1877�`1956�j�́A�����g���I�[���̃}�M����w�ɂ�����1901�N10���`1903�N4���̋��������ŁA�g���E������o�Ă���G�}�l�[�V�����i��q�j�̐��̂����Ƃ߁A�g���E���Ƃ��ꂪ��ς��Đ����閺�j��g���E���w�̕��˔\�̌��������w���͂ɂ���Ē��ׁA���˔\�̌��������f�̕ϊ��ߒ��ł��邱�Ƃ������B�����ŁA�ނ�̒T���̉ߒ����������B
�P�D�P�X���I���̏�
�@�P�X���I���̃E�����A�g���E���̕��˔\�̔����A�����������ː��V���f�|���j�E���A���W�E���̔����ɂ���āA�����I�ɓ���ƕ��ː��̌����������������B�����I���߁A���ː��ɂ́A
- ���ߔ\���������A����ɂ���Ă͂قƂ�NjȂ���Ȃ��A���t�@��
�i���ɑѓd�������q�������ŕ��o�������̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă������A���̐��͕̂s���j
- ����ɂ���ċȂ����A�A���t�@���������ߔ\�̑傫���x�[�^��
�i1900�N�x�N�����́A���W�E������ł�����̔�d�ׂ𑪒肵�āA�������d�q�ł��邱�Ƃ��������j
- ����ɂ���ċȂ��炸�A���ߔ\�̑傫���K���}��
�i1900�N�ɂo�D�u�D���B���[�����ϑ��������A���̖{�����������̂�1914�N�ɂȂ��Ă���ł��B�j
�̂R��ނ̈قȂ���̂����邱�Ƃ��������猩�o����Ă����B�������A���˔\�̌����̐����͍��ׂƂ��Ă��荬�����ɂ߂Ă����B�������ɂ߂����R���A�����̒m���Ő�������ƁA
- ���q������i���Ȃ킿�ʂȌ��f��������j�Ƃ������ێ��̂��F������Ă��Ȃ������B
- �����i�K�ɂ��킽���ċN���邱�Ƃ��m���Ă��Ȃ������B
- ����̔��������̂��܂���������Ă��Ȃ��������A�����ɗl�X���邱�Ƃ��m���Ă��Ȃ������B
- ���ʑ̂̊T�O�͂܂��m���Ă��炸�A����n���ʂ�����邽�ߓ��ꌳ�f�Ŕ������̈قȂ���̂����݂��Ă��邱�Ƃ��m���Ă��Ȃ������B
- ����̓r���Ő����郉�h�����C�̂ł��邽�߂Ɏ����s�v�c�ȐU�镑���������ł��Ȃ������B���̃��h���ɂ��A�E��������ł���̂ƃg���E������ł���̂ł͈قȂ�������������������ނ��̓��ʑ̂����݂����B
- ���h���͂����ɕ��čĂьő̂̊j��ɕϑJ���Ď��͂̕����ɕt���������A���̌��ۂ̈Ӗ����킩��Ȃ������B
�@�ȏ�̗l�ɔ��ɍ��ݓ����Ă���A���̕��G�������ۂ̉��߂��ɂ߂č���Ȃ��̂ɂ��Ă����B
�@�Ⴆ��1900�N�ɃN���b�N�X�������������Ƃł��邪�A�E�������̗n�t�̒��ɐ��_���S�̒��a��������ƁA���˔\�͂��ׂĒ��a�̕��ɂ����Ă��܂��A�E�����͕��˔\���������܂c��B�Ƃ��낪�����o�ƁA���a�͕��˔\�������ăE�����̕�������������B�ނ͂����̎������ʐ^�Ŕ̊�����p�ɂ�蔭�������̂ł��邪�A���̃E�����̒��ɂ����ĕs�v�c�Ȍ��ۂ������������E�����w�ƌĂB����ɁA���̑��̕��ː������ɂ��Ă���͂蓯�l�Ȍ��ۂ��N�����āA����ɗv����o�ߎ��Ԃ͗l�X�Ő����ɂȂ�ꍇ������ΐ����ԁA�����̏ꍇ������A�܂�ŗH��̗l�ł������B
�@�܂��A1899�N����1900�N�ɂ����āA�g���E���A���W�E������͋C�̏�̕��ː��������������Ă��āA���ӂ̕��������̋C�̂ɐG���Ƃ��̕��������˔\�������Ƃ��������ꂽ�B�����A���̋C�̏�̕��ː��������G�}�l�[�V�����ƌĂ�ł������A���ꂪ������ȐU�镑�����Ȋw�҂����f�������B
�@���̌��ۂ��S���V�������̂ł���A���̖{���������Ă��Ȃ��Ƃ��ɁA���ꂪ�����s�v�c�ȏ����ۂ���A�܂��ɈÈł̒�����T��ŁA���̖{���𖾂炩�ɂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ�����͑z����₷��B���̂��߂��̉𖾂̉ߒ��́A���R�Ȋw�̊w��Ƃ��Ă̑�햡���⊶�Ȃ������Ă����B
�@�����A���˔\�ɂ��Ď��̂悤�ȉ������������B
�i�P�j���ː����������͂̋�C���q�̔M�^���̃G�l���M�[����荞�݁A�������ː��Ƃ��ĕ��o����B
�i�Q�j���ː����������̖͂��m���t�˃G�l���M�[����荞�݁A�������ː��Ƃ��ĕ��o����B
�@�@���Â���A�d�q�������ɓ��˂��Ăw������������ߒ��ɗގ��Ȃ��̂Ƃ��āA���ː��̕��o�ߒ����l���Ă���B�����������͂��̂�����ł��Ȃ����q���̂��̂���ς��Ă����Ƃ��������̉��w�҂̏펯�����̂������B
�@
�Q�D�\���m��
�\���m���Ƃ��āA���������Ă��鎖���K���Ă����B
�i�P�j���ː�����̊�b
�@�����@���@�ɂ�������ː����f�̐����m(��)�Ƃ���ƁA�������ɂ�����P�ʎ��ԓ�����̕���(t)��
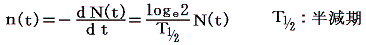
�ƂȂ�B�i�ʍe�u���ː�����Ɣ������v�ŏؖ��j
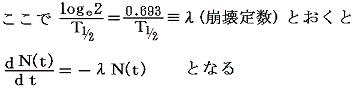
�@�j�����͔��ɃG�l���M�[���������ۂ�����j�O�d�q���W���鉻�w�I�ȕω���M�^���ɔ�����̉e�����قƂ�ǎȂ��B���̂��ߕ��ː����f�����Ă������x�́A���x�A���́A���w�����Ȃǂ̕����I�A���w�I�ɂ��Ȃ��B�����甼�����s1/2���邢�͕���萔�ɂ͂˂Ɉ��̕s�ϒ萔�Ƃ݂Ȃ���B
�@��������0�̂Ƃ��̐e�j��̐����m(0)�Ƃ���ƁA��L�̔����������̉���

�ƂȂ�B���̎����S�Ă̏o���_�ł��B
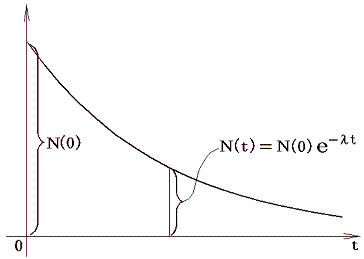
�@���ɁA���ː�������n����Ȃ��ꍇ��_����B���ꂼ��̊j��̕���萔��1�A��2�A�����n-1�͊e�j��̔�������
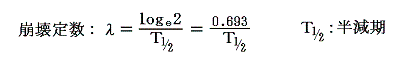
�̊W�Ō��т�����B�����ł͘b���ȒP�ɂ��邽�߂Ɍn��̎}������͖������Ă��ꂼ���̘A������Ƃ��čl����B����n��̎������ɂ�����e�j��̑��ݗʂ��w1�A���j��̑��ݗʂ��w2�A�w3�A������A�wn�Ƃ���B���Ԗڂ̊j��̑��ݗʂwi�̎��ԓI�ω��͎���̑��ݗʂwi�ɔ�Ⴕ�Ď����Ă������x�Ƃwi-1�����Ăwi�ɕt��������Ă��鑬�x�i�wi-1�ɔ��)�ɊW���邩��A�w1�A�w2�A������A�wn�͉��L���A�������������������B
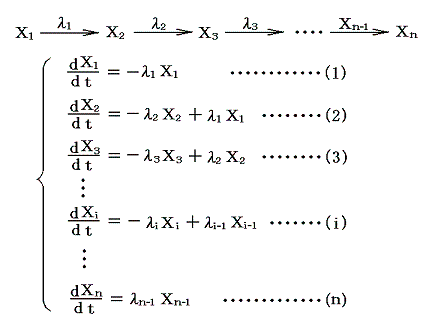
���̘A��������������̐��w�I�ȉ�@�ɂ��Ă͕ʍe�u���ː�����n��̐��w�v�Q�ƁB
�@
�i�Q�j�A������n��̐���
�@���݂̒n����ɂ͎O��ނ̕���n�c���Ă���B�e�n��ɂ͐����Ɏ}�����ꂵ���n���݂��邪�A�ȒP�̂��߂Ɏ}������o�H�ł��̊������P�����x�ȉ��̕���͂��ׂĖ�������ƁA��������قڈ�{�̘A���Ōq���������f�����ǂ��ĕ��Ă����B
�@�@238�t�i������45���N�j����o�����āA�ŏI�I��206�ob�֕����E���j�E���E���W�E���n��i�S���{�Q�j�A
�@�@235�t�i�������V���N�j����o������207�ob�ɕ����A�N�`�j�E���n��i�S���{�R�j�A
�@�@232�sh�i������140���N�j����o�����Ă�����208�ob�֕����g���E���n��i�S���j
�̎O�n��ł��i�ʍ��u���ː�����Ɣ������v�Q�Ɓj�B
�@���R�E�Ɏc���Ă������n��ł͉�ς̏o���_�ɂȂ�e�j��w1�̕���萔��1���A����ȍ~�̖��j��w2�`�wn�̕���萔��2�`��n�ɔ�ׂċɂ߂ď������i�������͋ɂ߂Ē����j�B���̂��߁A���t�i���˕��t�j���������Ă���Ƃ��A���L�̂R�̏d�v�Ȏ��������藧�B�i���w�I�Ȑ����͕ʍe�u���ː�����n��̐��w�v�R�D�i�R�j����n��̃��f���Ƃ��Ă̂����V�̗�j
- �@�n����e�j��̑��ݔ�́A�e�j��̔������ɔ��i����萔�̑傫���ɋt���j���Ă����B
�@�������A���w�I���͂ɂ��e�j�����������ƕ��t�̓��Z�b�g����Ĕt�̏�Ԃ����炭�̊Ԏ����B
- �@�e�j��͕��t���قڒ���Ԃɂ���ƌ��Ȃ���̂ŁA�e�j��ɏ�ʂ̂��̂����ĕt������鑬�x�Ɖ�ς��Ė����Ȃ��Ă������x�͒ނ肠���Ă���A�P�ʎ��Ԃɕ��鐔�͂��ׂĂ̒i�K�̕���j��ɂ��Ăقړ������ƌ��Ȃ���B
�@�������A�������Ԃɂ킽���Ċϑ��𑱂���A�P�ʎ��ԓ�����̕��͏o���e�j��̑��ݗʂ̌����Ƌ��Ɂi�e�j��̔������Łj�������Ă����B
- �@�������Ă��Ȃ��E�����z�A�g���E���z���������˔\�́A��L�̓����ƌ��Ȃ���e�i�K�̕��˔\�̘a�ɂȂ��Ă���B���̂����P�ʎ��ԓ�����ɕ��錴�q�̑����́A��̊j��̒P�ʎ��ԓ�����̕��̂قڒi���{�ɂȂ��B
�@�������A�e����ߒ��ɂ�����x�[�^���A�A���t�@���A�K���}���̃G�l���M�[�͊j�킲�ƂɈقȂ�̂ʼn����������G�l���M�[�̑��a���P���ɂǂꂩ�̒i�K�̕���G�l���M�[�̕���i���{�ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��B
�@��ŏq�ׂ�l�ɓ����A���˔\�̋��x�͕��ː����C�̂��C�I��������\�́i�d���C�̂�d�����łƂ炦�āA���̓d�C�ʂ��ی��d�ʌv�ő���j�ő�����B���̂Ƃ������̓����ɔ�ׂăC�I�����\�͂������̂ŕ������������˔\�̋��x�͌��ǃ�����̃G�l���M�[�a�ɊW����B���ۂR�i�R�j�Ő�����������5.�ɂāA���U�t�H�[�h�͕��˃G�l���M�[��99���ȏ���������S���Ă���ƌ��ς����Ă���B
�@
�i�R�j���R�E�ɂ�����O�̕���n��
�E���j�E���n��
�@���w�I�Ȑ����������E���j�E�����ʑ̂́A�ǂ̃E�����z�������E�������ʑ̔�Ŋe�E���j�E�����܂�ł���B���݂̃E�����z�Β��̓��ʑ̂̑��ݔ䗦�́@238�t�F234�t�F235�t��99.275�F0.005�F0.720�@�i�܂�@235�t�F238�t��137.88�F1�j�ł��B�i�ʍe�u���ː��N�㑪��@�v�Q�D�i�R�j�Q�Ɓj
�@�܂��A�m�P�ʎ��Ԃɕ��錴�q���n���m����萔�n�~�m���f�̑��ݗʁn�i�Q�D�i�P�j�Q���j������A����萔�̔�́@��238�F��235��1.55�F9.84���i1�^4.51�~109�j�F�i1�^7.13�~108�j�@��p����Ɛe�j��ł���E�����̒P�ʎ��ԓ�����̕��̔�́@d238�t�^dt�Fd235�t�^dt��99.275�~1.55�F0.72�~9.84��22�F1�@�ƂȂ�B
�@�Ƃ���ŕ��t�ɂ���n�ł́A�P�ʎ��Ԃɕ��鐔�͂��ׂĂ̒i�K�̕���j��ɂ��Ăقړ������i�Q�D�i�Q�j�̂Q�D�Q�Ɓj�̂�����A���t�ɂ���Ƃ��̓�̃E�����n��̑Ή�����i�K�̕��ː����ʑ̊j��̕��ː����o�̔䗦��22�F1�ɂȂ�B�Ⴆ�Ή��}��222�qn��219�qn�̏o�����˔\�̔䗦��22�F1�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
�@�܂��A���t�ɂ���n�ł́A�e�n��ɂ������e�j��̑��ݔ�́A�e�j��̔������ɔ��i����萔�ɋt���j���Ă����i�Q�D�i�Q�j�̂P�D�Q�Ɓj�̂�����A�e�i�K�ɂ�������ː����ʑ̂̌n��ʂ̑��ݔ䗦�́A�o�������́@238�t��235�t�̑��ݔ�@137.88�F1�@�ɂ��ꂼ��̌n��̓��ʑ̂̐e�j��̃E�����ɑ��锼�����̔���������䗦�ɂȂ�B�Ⴆ�Ή��}��222�qn��219�qn�̌��q�����ݔ�́A���ꂼ��̔�������3.825����3.30�~105�b��3.92�b�ō݂邱�Ƃ��l������ƁA99.275�~�i3.30�~105�^4.51�~109�j�F0.72�~�i3.92�^7.13�~108�j�ƂȂ�B
�@�������A���̑��ݔ�Ɋe���ʑ̂̕���萔�̔�i1�^3.30�~105�j�F�i1�^3.92�j���悶��Ɗe���ʑ̂̏o�����˔\�̔䗦22�F1�ɂȂ�B
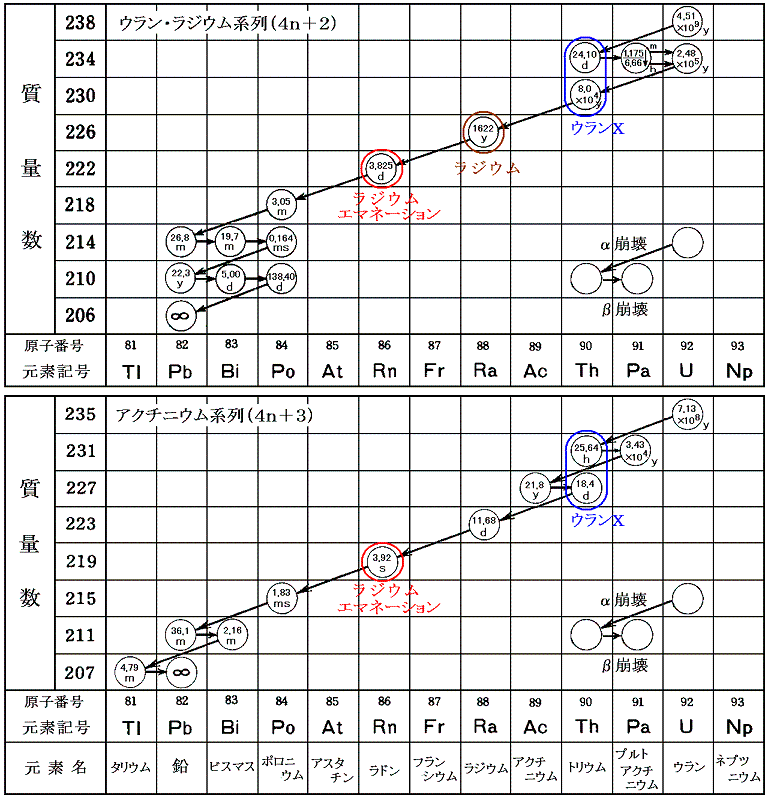
�g���E���n��
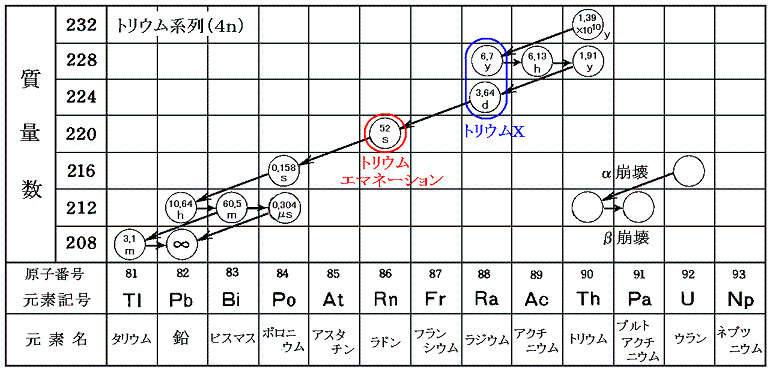
�@
�R�D�������R�ƌ����o��
�i�P�j�����������R
�@�E�����̕���Y���ł���E�����w��A�E�����Ɋ܂܂�Ă��郉�W�E���̕���Y���ł��郉�W�E���G�}�l�[�V�����̎�����Ȍ��ۂ̓��U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�ɂ��g���E���n��̌����ȑO�ɗl�X�ȉȊw�҂ɂ�蔭�����ꌤ������Ă���B�������ނ�͐����������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@�������ʑ��̊T�O�͊m�����Ă��Ȃ������̂ŁA�E�����̕���n���238�t��235�t�̓�n�������邱�ƂȂǑz�����ɂł��Ȃ����Ƃ������B�����̌��t�Ō����ƁA���w�I�����̂��ׂẲߒ��ɓ�n��̓��ʑ̌��f�����݂��Ă���A�E�����w�ɂ͂S��ނ̂sh���A���W�E���G�}�l�[�V�����ɂ͂Q��ނ̂qn���������Ă��邱�ƂɂȂ�B�����̎��������荇�������������E�����n��̉𖾂���ɍ���ɂ��Ă����ł��낤�B
�@���U�t�H�[�h�ƃ\�f�B���A�l�X�ȍ�������z���ē���𖾂��鎖���ł������R�́A�ЂƂ��ɒP��̕���n��ł���g���E���n���g���E���w(���W�E��228�qa�A224�qa�j���g���E���G�}�l�[�V�����i�s�����K�X���h��220�qn�j�ɒ��ڂ����Ƃ���ɂ���B�ނ�́A�����̌��t�Ō����g���E����όn��ɂ����āA���w�����ɂ��g���E���ƃ��W�E�������A���̃A���t�@���˔\�ƃ��h��220�qn�������𑪒肵�A���̋��������όn�j��̕ϊ��ߒ��ł��邱�Ƃ����Ƃ߂��̂ł��B
- �ނ�͍K�^�ɂ��E�����n��ł͂Ȃ��ăg���E���n���p�����B
�@�g���E���n��i�S���j���E�����n��i�S���{�Q�A�S���{�R�j���G�}�l�[�V�����������B�܂��A�g���E����E�����̒��ɂ����˔\�̋��������g���E���w��E�����w�����݂����B���̂Ƃ��ނ炪�p�����g���E���n��̓E�����n��̗l�ȓ��ނ̌n��̍����ł͂Ȃ��āA�������ނ̌n��̎Y���������B
�@�܂��A�E�����n��i�E�������E�����w�i�sh�j�����W�E�������W�E���G�}�l�[�V�����j�̗l���S�i�K�ł͂Ȃ��āA�g���E���n��i�g���E�����g���E���w�i�qa�j���g���E���G�}�l�[�V�����j���R�i�K�ł��邱�Ƃ��K�������B�E�����n��̃��W�E���͓����E�����Ƃ͕ʂ̍����I�ȕ��ː��������ƍl�����Ă���A���̂��Ƃ��E�����n��ɑ傫�ȍ����������N�����Ă����̂�����A�����̍����������鎖���ł����͍̂K�^�������B
- �K�^�ɂ��ނ炪���肵�����h��220�qn�̔�������52�b�������B�E�����E���W�E���n��i�S���{�Q�j�Ő����郉�h��222�qn�̔�������3.8���ł���A�A�N�`�j�E���n��i�S���{�R�j�̃��h��219�qn��3.92�b������A����������̎��̂𑨂���̂�����ł������ł��낤�B
- �K�^�ɂ��g���E���w���\��������ނ̃��W�E��228�qa�A224�qa�̔������ŁA�A���t�@������i�����炪�d�����łƂ炦����j���W�E��224�qa�̔�������3.64���ƒZ���x�[�^�������Ȃ����W�E��228�qa�̕���6.7�N�ƒ����������Ƃł��B�E�����E���W�E���n���A�N�`�j�E���n��̓r������Y���̂sh�̔������̓x�[�^��������Z���A�A���t�@��������������߁A�ނ炪�p�����d�����ɂ�镪�͂ł͖��ĂȎw�����I�ȕω��͓����Ȃ������ł��낤�B
- ���U�t�H�[�h�́A����ȑO�Ɍ������Ă��������d�M���p���̌����ŁA���ȃC���_�N�^���X������H�ɂ����Ȃ�d���d�������Ă��d���͒����ɂd�^�q�Ƃ͂Ȃ炸�Ɏw�����I�ɂ��̒l�ɋ߂Â��Ă��������K�m���Ă����B�܂肻�̂��Ƃ�\���w�����̎�
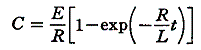
�ɐ��ʂ��Ă����B�܂��A�\�f�B�����ʂ��Ă����P���q���w�����̒m���́A���ː�����̃��J�j�Y���̗����ɑ傫�ȗ͂ɂȂ����Ǝv����B
�@
�i�Q�j�d�����Əی��d�ʌv
�@���U�t�H�[�h�̓\�f�B�Ƃ̋��������̑O�ɁA�������g��̌����i1895�`1896�j�A�����g�Q�����ɂ��C�̂̓d���̌����i�g���\���Ƃ̋��������APhil.
Mag. (5)42, p392�`407, 1896�N�j�A�E�������o���x�N�������ɂ��C�̂̓d���̌����i1897�j�A�d������i�Ƃ��ĕ��˔\�̐����̌������J�n�i1898�j�B���̉ߒ��Ń��U�t�H�[�h�͕��ː������ނ��邱�Ƃ����������ߗ͂̎ア���������A���ߗ͂̋������������ƌĂiPhilosophical Magazine, (5)47, p109�`163, January, 1899�N�j�B�܂����̎����œd�ʌv��p�����d�C�I���o�@�ɐ��ʂ����B
�@���}�͔ނ炪�p�������葕�u�ł��B���}�̓d�����͖�6cm�u�Ăĕ��s�ɒu���ꂽ�̓��d���̔���Ȃ��Ă���A�ׂ��������ɂ�������������ʐ�36cm2�̔����ŏ�Ɉ�l�ɍL����B���̓��̔�100�`300�u�̐��d���ɂ��Ă���B���ː������͓̔̊ԂɘA���I�ɃC�I�������邪�A���̓d�������ł́A���������C�I���̂قƂ�ǑS�Ă��ɕߏW�����B
�@������͉̔E�}�̏ی��d�ʌv��4�̏ی��d�ɔ̓��̈�ɐڑ�����Ă���B���̈�̏ی��d�ɔ͏�ɃA�[�X����Ă���B��̏ی��d�ɔ̊Ԃɂ�����ʂ̋ɔ��݂���ł艺�����Ă���A�݂���̂˂���ɂ��݂��ɑΖʂ��ďd�Ȃ镔���̖ʐς��ω�����悤�ɂȂ��Ă���B���̉�]���镽�s�R���f���T�[���`�����Ă���B�ѓd�������ނƓd�C�I���͂ɂ��A�݂�����˂����ĉ�]���Ă����B
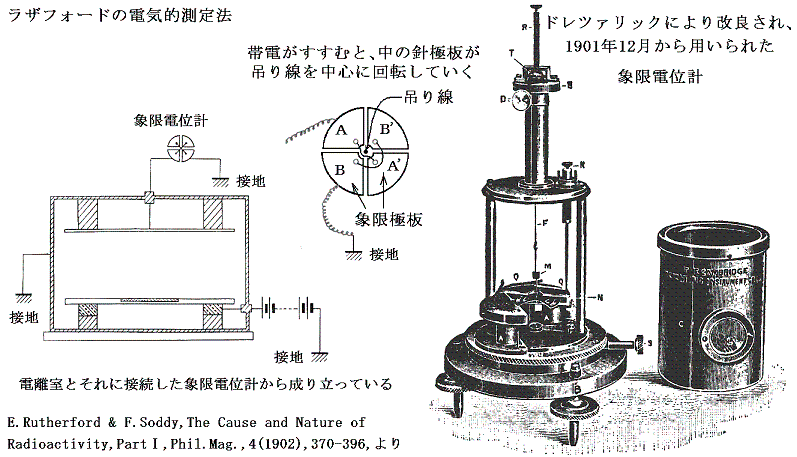
���}�ɂ��ی��d�ʌv�̌������������B
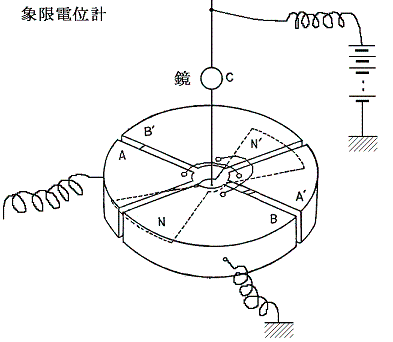
�@����͋ɔ��ʂ̓d�C������d�ʍ���ۂ��Ă���Ƃ��A���̓d�ʍ��𑪒肷�鑕�u�ł��B�l�̐�`�̋������i���ꂪ�l�ی����ƌ����闝�R�j�̂�����������̂`�Ƃ`�f�A�a�Ƃa�f�͓����ŘA������Ă���B�`�ɓd�ׂ����܂邱�Ƃɂ��ݒu����Ă���a�Ƃ̊Ԃɐ�����d�ʍ��𑪒肷����̂ł��B�l�̔��̒����ɐ}�̂悤�ȓ��d���̔�̐j�m���݂��Ă���B����͈��̂˂��蔉���\������B���̐j�ɂ͍����d�ʂ�������^�����Ă���B�Ód�C�͂̂��߂ɂ��̔�̐j�͂`�a�Ԃ̓d�ʍ��i�`�ɒ��܂����d�C�ʁj�ɉ����Ēʏ�̈ʒu������B���̉�����p�ɂ��`�a�Ԃ̓d�ʍ��i�`�ɒ��܂����d�C�ʁj�𑪒肷��B������p�x�͐j���鎅�ɋ��b��t���A���̋��ŕ������̖ڐ���˂����ēǂݎ��B�i�ʍe�u��Γd�ʌv�Əی��d�ʌv�̑��茴���v�Q�Ɓj
�@����͈ȉ��̎菇�ōs����B�܂��A�d�����̏�����̔��A�[�X������ԂŎ��������̓��̔�ɐݒu����B���ɏ���̓��̔̃A�[�X���ƁA���ː��ɂ��C�I���������C�̂̓d�ׂ�������̔�ʂ��ďی��d�ʌv�̈�̋ɔi�`�Ƃ`�f�j�ɒ��܂��Ă����B����͂�����̃A�[�X���ꂽ�ی��d�Ɂi�a�Ƃa�f�j�ɔ��Γd�ׂ�U�����A���̊Ԃɓd�ʍ�����B�ی��ɔ̒��ɒ݂��ꂽ���d�����������Ă���ɔi�j�m�j�͂��̓d��̒��ŐÓd�C�͂ɂ��͂ɂ��݂�����˂����ĉ�]���Ă����B���̉�]�̊p���x��݂���ɕt�������ɉf�镨�����̖ڐ�����������œǂݎ�邩�A���̔��˃X�|�b�g�œǂݎ��B��\�I�ȑ���ł�100�ڐ����ʉ߂���̂ɐ��\�b���x�ł������B
�@�ی��d�ʌv�̏ی��ɔ̉�]�p���x�͓d�����̓̔̊Ԃ𗬂��C�I�����d���̋�����\���A���̃C�I�����d���̋����͕��ː����̕��ː��\�̋�����\���B�܂�ی��ɔ̉�]�̊p���x�������̕��˔\�̋�����\���ړx�ƂȂ�B��̑��肪�I���Ɠd�����̏�����͎̔��̑���ɔ����ăA�[�X�����B���̓d�C�I���@�̐����́A�ѓd�ߒ��̏����i�K�ɑ�������܂��邱�Ƃɂ������Ă���A���̒i�K�ł͈�l�Ȋp���x���ѓd�̑��x�i�C�I���d���j�ɑΉ����Ă���ƌ��Ȃ���B���莞�Ԓ��ɏ�����̔i�`�Ƃ`�f�j�̓d�ʂ̓A�[�X�d�ʁi�a�Ƃa�f�j��������قǍ����͂Ȃ�Ȃ������B
�@���̓d�ʌv�̓P���r���̔����ɂ�邪�A�⏕�R���f���T�[�����ی��d�Ɍn�ɕ���Ɍq���ł��̐Ód�e�ʂ߂ł���悤�ɂ��Ă���B�������邱�ƂŊ��x���L���͈͂ɂ킽���ĕς�����悤�ɂȂ��Ă����B�܂苭�����˔\�ɑ��Ă͑傫�ȗe�ʂ̕⏕�R���f���T�[���A�ア���˔\�ɑ��Ă͏����ȗe�ʂ̕⏕�R���f���T�[�����Ɍq���̂ł��B
�@���̏ی��d�ʌv��1901�N�h���c�@���b�N�ɂ��A�n���̐Ód�e�ʂ����炷���ǂ��������āA�]����100�{�ȏ�̍����x���B���ł���悤�ɂȂ��Ă����B���̈�1mg�̎_���g���E�����������˔\�ł�����\�ł������B
�@���̕��@�́A����܂ł̉��w�V���ɂ��v���ɔ�ׂĐ��ȈЗ͂������B���̓d�C�I�ȕ��@�ł́A�V���Ō��o�����ʂ̂P�����̂P���x�ł����o�\�ł������B�܂��A�ɂ߂Đv���ȑ��肪�\�ł������̂ŁA���ː��������o�����˔\�̌������x�̈Ⴂ��e�Ղɑ��肷�鎖���ł����B���˔\�̌������x�̈Ⴂ����A���ː������̎�ނ̔��ʂ������ɉ\�ɂ����B�\�f�B�͂��̑��u�̗��p�@��M�S�Ɋw��ŁA���ː������������E����E�ω��̒ǐ��ɑ����ɗ��p�����B���̑��u�������ĕ��ː��ϊ����̉𖾂͕s�\�ł������낤�B
�@
�i�R�j���������̌o��
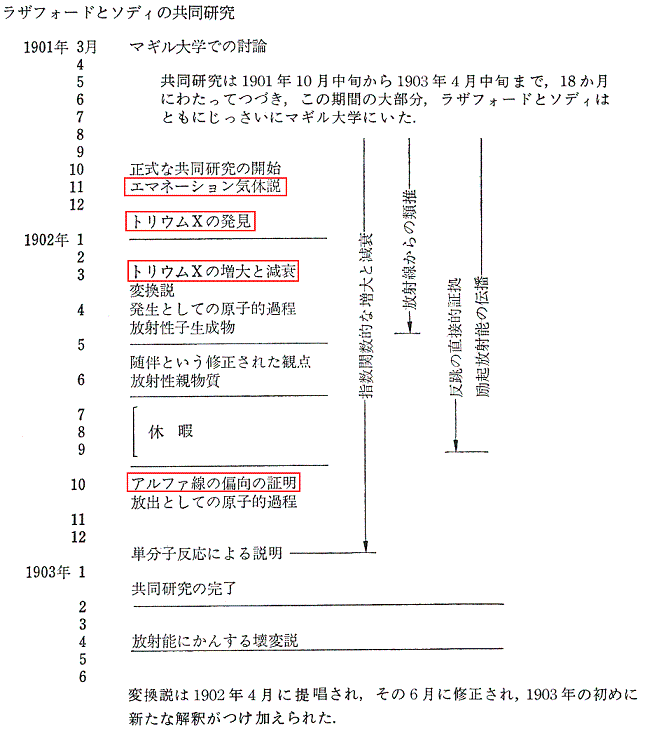
Ernest Rutherford & Frederick Soddy �A���̗L���Ș_���͓��ɕ����ē�̎G���ɓ��e���ꂽ�B�܂��ŏI�I�Ș_����1903�ɔ��\�����B
- 1901�N12��Journal of the Chemical Society�ɓ��e�A1902�N1��16���̊w��̉�Ō������\�A1902�N4��������\���ꂽ���̂�
E.Rutherford & F.Soddy,TheRadioactivity of ThoriumCompounds,I:An Investigation
of the Radioactive Emanation,J.Chem.Soc.,81(1902)321-350,
- ������1902�N4��29���ɓ��e�A5��15���̉�Ŕ��\�A1902�N7��������\���ꂽ���̂�
E.Rutherford & F.Soddy,The Radioactivity of ThoriumCompounds,�U:The
Cause and Nature of Radio-activity,J.Chem.Soc.,81(1902),837-860,
- �ނ�́A4���̘_���i2.�j�Ƃقړ������e�̕������A�����w�҂����̊S�ɏ]���ĉ����C�����s����1902�N5����Philosophical Magazine�ɓ��e�����B������1902�N9��������\���ꂽ���̂�
E.Rutherford & F.Soddy,The Cause and Nature of Radioactivity,Part�T,Phil.Mag.,4(1902),370-396,
- �����āA12���̘_���i1.�j�����������u����ɐi���_�I�l�@�v�̈�߂�t�����������̂�1902�N6���ɓ��e�A1902�N11��������\���ꂽ���̂�
E.Rutherford & F.Soddy,The Cause and Nature of Radioactivity,Part�U,Phil.Mag.,4(1902),569-585,
- ���������̍Ō�ɏ�����A���ː��ϊ������W�听����_����
E.Rutherford & F.Soddy,Radio-active Change,Phil.Mag.,5(1903),576-591
�ł��B���̂���3�D��HP�T�C�g http://web.lemoyne.edu/~giunta/ruthsod.html �Ō��邱�Ƃ��ł���B�܂�4�D��5.�͎Q�l����5�D�ÓT�_���p���ɖ|�f�ڂ���Ă���B
�@
�S�D���U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�̎���
�i�P�j�g���E���G�}�l�[�V�����̕��˔\����
�@�����A���ː������̋߂��ɒu���ꂽ���̂��u�U�����˔\�v�������Ƃ��m���Ă����B�I�E�G���X�ƃ��U�t�H�[�h�͕��ː������ɂ���Đ������C�̃C�I�����̓x��������C�̗���ɉe������鎖����A���ː��ɂ̓g���E�����璼�ڏo����̂ƃG�}�l�[�V��������o����̂̓��ނ��������ƂɋC�Â����B�����ʼn��}�̑��u��p���ăg���E������o��ʏ�̕��˔\�ƁA�G�}�l�[�V���������āA�G�}�l�[�V�����̏o�����˔\�ׂ�����������B
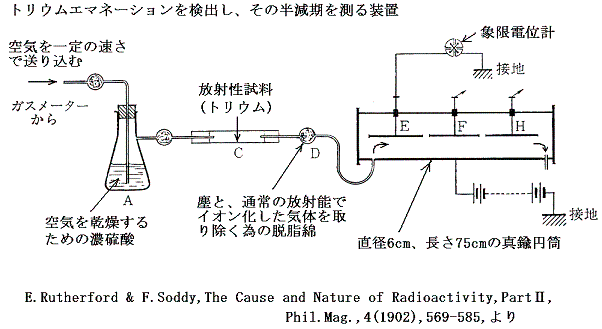
�@�����̃K�X���[�^�����C���e��`���̗��_��ʂ��đ��荞�܂��B��C�͊ǂb���ɒu���ꂽ�g���E�����甭������G�}�l�[�V�����Ƌ��ɁA�d�ɂd�A�e�A�g���݂���ꂽ�ǂ�ʂ��ĉE�֗���čs���A�ǂ̉E��������o�����B��C�������̑����ŗ���������ƁA�d�ɂd�A�e�A�g�𗬂��d���͈��ƂȂ�B�ǂb���̎�������̒P�ʎ��ԓ�����̃G�}�l�[�V���������ʂ́A�d�ɂɗ����d���d���ɔ�Ⴗ��ʂƂ��đ��肳���B�܂��A�d�A�e�A�g�̓d���l�����̒��x�ƁA��C���ʂ��瓱�����G�}�l�[�V�����̈ړ����x�ƕt�����킹�����Ƃɂ��A��C��d������\�́i���˔\�ɔ�Ⴗ��j�����ԂƂƂ��Ɍ������鎖������ł���B
�@���̎�������A�G�}�l�[�V�����̔��������ǂb���̎��������̎��ʂɔ�Ⴕ�A�g���E���͕��˔\�Ƃ͕ʂ̃G�}�l�[�V�����Ƃ����C�̏�̕����o���Ă���B���̃G�}�l�[�V�����͂���ɕ��˔\�������Ă���B���̕��˔\�͖�P���Ŕ����������Ƃ��m���߂��B
�@���U�t�H�[�h�̓G�}�l�[�V�������C�I���g���b�v�ω��Œʂ蔲���鎖���m���߂āA�G�}�l�[�V���������������Ȃ�d�C�I�ɒ����Ȃ��̂ł��낤�Ɨ\�������B�����āA�ނ͗�N���˔\�̓G�}�l�[�V�������g�U���A�����Ē��a���邱�Ƃɂ�錋�ʂł���Ƒ�������\�����Ă����B
�@�܂��A�\�f�B�͔��M����܂ʼn��x�����������������A�}�O�l�V�E�������A���������A�N�����_���ȂǂɃG�}�l�[�V������ʂ��Ă��z�����ω����Ȃ������m���߂��B���̂��Ƃ��烉�U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�́A�G�}�l�[�V�������s�����K�X�ɑ�����V���f��������Ȃ��Ǝv���悤�ɂȂ�B
�@�������A���̒i�K�ł̓G�}�l�[�V���������\�̖{���͈ˑR�Ƃ��ē䂾�����B�G�}�l�[�V�������g���E������o��̂��A���邢�̓g���E���̒��̖��m�������琶����̂��A�܂��G�}�l�[�V���������̕s�K�����i���ꂪ�g���E���������̋z���ɂ��A�Ɖ���̂�1902�N�j�̌����͉��Ȃ̂��A�܂����������Ă��Ȃ������B
�m�����̒m���ɂ������n
�@���̏����O�Ƀ��W�E�����G�}�l�[�V�������o�����Ƃ̓h�����ɂ�����Ă����B�������E�������G�}�l�[�V�������o�����ǂ����́A���̎��_�ł͂܂��m���Ă��Ȃ��B�����������̒��ŁA�ނ�͗l�X�Ȏ����ƍl�@��ʂ��ām�G�}�l�[�V�������s�����K�X�̂悤�ȕ����ł��n�Ƃ������ƁA�G�}�l�[�V�����̓g���E���Ɋ܂܂ꂽ�g���E���ȊO�̐����ɂ����̂ł͂Ȃ��āA�m�g���E�����g�ɂ�萶������镨�ł��n�Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ����̂ł���B
�@�����̌��t�Ō����ƁA�G�}�l�[�V�����͕s�����K�X�̃��h��220�qn�ł���A���h��220�qn�͔�����52�b�Ōő̌��f�ł��|���j�E��216�oo�i���ː��j�ɉ�ς���B�|���j�E���͗l�X�ȕ����ɕt�����āA����������������ː������ł��邩�̂悤�Ɍ����������̂ł��B
�@
�i�Q�j�g���E������g���E���w�̕���
�@�����O�ɁA�N���b�N�X�̓E��������E�����ȊO�̕��˔\���������o�����Ƃɐ������Ă����B�������ނ͓��������g���E���Ɏ��݂����������Ȃ������B�����l�X�ȉȊw�҂ɂ��g���E���̒��ɕ��˔\�̌����������܂܂�Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���A���̕����̎��݂��Ȃ���Ă����B
�@����ȏ̒��ŁA�\�f�B�͎��}�̎������s�����B
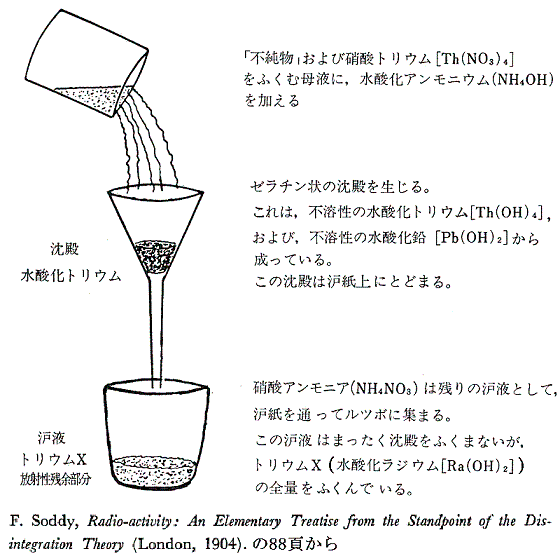
�@�ނ�̓g���E���i�s�������܂ށj�̏Ɏ_���𐅂ɗn�������㤐��_���A�����j�E���������Đ��ɕs�n�̐��_���g���E���Ƃ��Ē��a�������B�����Ē��a�����h�t�����āA�����̕��˔\��ʁX�ɑ��肵���B���̌��ʂ͋����ׂ����̂������B
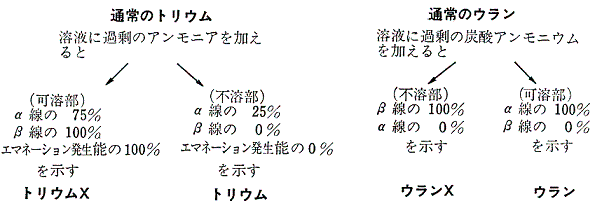
�@���b�������_���g���E���̕��˔\�ׂ��Ƃ���A���̒��b�ɂ̓A���t�@�����o�̕��˔\�̂S���̂P���c���Ă��������ŁA�c��̕��˔\�͂��ׂ��h�t�Ƃ��ĉ��̃��c�{�Ɉڂ��Ă����B�܂��A�G�}�l�[�V�����̔����\�͂̂��ׂĂ��h�t�Ɉڂ��Ă����B
�@�@���U�t�H�[�h�ƃ\�f�C�́A���˔\�ƃG�}�l�[�V���������\�͂����������m�̕������A�h�t�ɗn������Ċ܂܂�Ă���ƍl���A���̖��m�̕������g���E���w�Ɩ��t�����B
�@�\�f�B�͒��a���i���_���g���E���j�̕��˔\�������g���E�������菜���ׂ̉��w�I�����̓w�͂𑱂������ǂ����Ă��g���E���̎����˔\����菜�����Ƃ��ł��Ȃ������B�ŏ������Ă������˔\�̂Q�T�����ǂ����Ă��c�����̂ł��B
�m�����̒m���ɂ������n
�@�A���t�@�����o�̕��˔\�͋�C�̓d���ʂɂ���đ�����̂ŁA���肳�����˔\�͕��o�����A���t�@���̍��v�G�l���M�[�ɔ�Ⴗ��B�����O�̎������������˔\�i�d������p��������ɂ����́j���Q�D�i�R�j�̃g���E���n��}���Ɋ܂܂��S�Ă̕��ː����f�̕��˔\�̘a�i�����̃G�l���M�[�a�j�ł��B
�@����ɑ��ăg���E���Ɖ��̐��_�������a�Ƃ��Ď��o���ꂽ���̂��������˔\��232�sh�A228�sh�����i�ڂ��������ƕ��ː�215�ob�Ȃǂ��܂܂��j�̕��˔\�a�i�����G�l���M�[�a�j�ɂȂ�B�g���E��232�sh��228�sh������o�����A���t�@���̃G�l���M�[�̘a�́A��όn��S�̂ŕ��o�����A���t�@���̃G�l���M�[���v�̖�S���̂P�ɂ�����B���ꂪ���w�����̍ۂɂS���̂P�̕��˔\�����_���g���E���̒��a�Ɏc���Ă������R�ł��B�i�Q�D�i�Q�j�Œ��ӂ����R�̐����Q�Ɓj
�����̎�����1901�N�̃N���X�}�X�x�ɑO�ɍs��ꂽ�B���̌�ނ�͋x�ɂ̂��߂Ɍ��������炭���f�����B
�@
�i�R�j�g���E���w���˔\�̌����ƁA�g���E�����˔\�̉�
�@�\�f�B�͑O���̎����œ���ꂽ�g���E�����a���ƃg���E���w���܂��h�t���N���X�}�X�x�ɂ̊ԕ��u���Ă����̂����A�R�T�Ԃ��Č������ɋA���ė����Ƃ��A���҂̕��˔\�𑪂��Ă݂ċ����ׂ��������������B
�@�g���E�����a���̕��˔\���������Ă����̂ł��B�����Ă���ɋ������̂́A�������˔\������Ă����h�t�̕��˔\�͂قڊ��S�Ɏ����Ă����̂ł��B�܂�A�g���E���ƃg���E���w�����������ƁA�G�}�l�[�V���������\�͂̑S���͂�������w�̕��Ɉڂ邪�A�����o�ɂ�ăg���E���w�̃G�}�l�[�V�����̔������͒ቺ���Ă����A�G�}�l�[�V�����̔����\�͂������Ă����g���E���̕��͏����ÂG�}�l�[�V���������������Ă������̂ł��B
�m�����̒m���ɂ������n
�@�h�t�Ɋ܂܂��228�qa��224�qa�͌��X���t�ɂ������̂ŁA���̑��ݗʂ͔������ɔ�Ⴕ�Ă���A���ꂼ��̊j��̒P�ʎ��ԓ�����̕��͕�����������́A�قړ����ł��B
�@���̂Ƃ��������̒����i6.7�N�j228�qa�̕��͂��Ȃ�̊��ԕ��˔\���o�������邪�A������Ȃ̂œd�����ɂ�鑪��ł͂��̕��˔\�̕ω����قƂ�ǂƂ炦�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���224�qa�����o���郿���͓d�����łƂ炦�鎖���ł��邪�A���̒Z���������i3.64���j�ׂ̈ɋ}���ɂ��̕��˔\�͌��������̂ł��B
�@���t����224�qa���������Ă���228�sh�͐��_�������a�Ƃ��ĕ��ʂ�����h�t�̒��ɂ͑��݂��Ȃ��B���̂��߁A�h�t�̒��ɑ��݂��Ă���224�qa�����Ă��܂����炻��ŏI���ł��B224�qa�̋������ł���228�sh�����܂�ɂ́A���̐e���f��228�qa�i�h�t�Ɋ܂܂�Ă���j�̔������i6.7�N�j���x�̎��Ԃ�������̂�����B
�@�\�f�B�������������g���E���ɂ��Ă̌��_�Ɠ��l�Ȍ��ʂ��A�x�N�����̓E�����ɂ��ď����O�ɔ������Ă���B�E�����𒾓a�����h�t�ɕ����ĕ��˔\���܂܂Ȃ��E�����̒��������݂钆�ŁA�������ꂽ�E�������ʏ�̕��˔\�����߂��A���˔\���R�����Ă����c�]�����̕��̕��˔\�������Ă������̂ł��B��������N���b�N�X��������m���߂���������Ă���B�������Ȃ���A�x�N�����́A�����̌��ۂ��U�����Ő��������B�E�����̓E�����������̐��������X�ɕ��ː��̏�Ԃɂ��镪���s�\�ȕ��ː��������܂�ł���B���ˉ����ꂽ�����̓E�������������番���ł��A���̗U�����˔\�����ԂƋ��ɏ��X�ɏ�������B������ː������̓E�����������̐�������ː�����������Ƃ����̂ł��B
�@�\�f�B�͗l�X�ȉ��w���͂̎�@��p�����g���E���w�̕��������݂邪�A���̑��݂͂��܂�ɂ����ʂŕ����Ƃ��Ď��o�������ł��Ȃ������B�������A���̓w�͂̉ߒ��Ń\�f�B�ƃ��U�t�H�[�h�̓g���E���w�̐����̓g���E�����̂��̂Ɉˑ����Ă��邱�Ƃ������m�M����悤�ɂȂ�B
�m�����̒m���ɂ������n
�@�g���E�������Ăł���g���E���w�͍����̃��W�E���i228�qa��224�qa�j�Ȃ̂����A���̔������̓E�����E���W�E���n��Ő����郉�W�E��226�qa�̔�������1/240�ȉ��ł��B�܂��e���f�̔�������232�sh�̕���238�t���������B���̂����Q�D�i�Q�j�̂P�D�̐������疾�炩�Ȃ悤�ɁA�g���E���z�Β��̃g���E���w�͉��w�����Ƃ��ĕ�������ɂ͂��܂�ɂ��ɔ��ʂł������B���̕����́A�E�����z���烉�W�E��226�qa�����鎖�Ɣ�r���āA�ɂ߂č�������B�����炱�ꂪ���W�E���ł��鎖������̂͂����ƌ�̎��ł��B
�@�\�f�B�̓x�������̃N�l�t���[���珃���ȏɎ_�g���E������肵�āA�m�s�n�����_���g���E���̒��a�n�Ɓm�n���̃g���E���w���h�t�n�������B��������U�t�H�[�h���d�����Ɠd�ʌv�ŕ��˔\���肵�ē������ʂ����}�ł��B�i1902�N3��27���`4��24���j
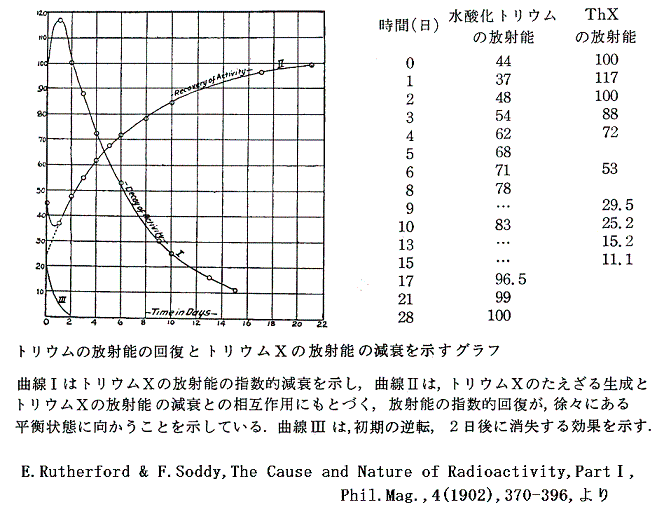
�@���̃O���t�����A�ނ炪��A�̎����œ������ʂ̒��ōł��d�v�Ȃ����ł��B1902�N5���̒i�K�Ń��U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�́A���̃O���t�����g���E���̕��˔\�̉��A�g���E���w�̈�葬�x�̘A���I�Ȑ����ƃg���E���w�̕��˔\�̎��ԂɊւ��ē��䋉���I�Ȍ����ɂ����̂��ƍl�����B���̂��ߕ����O�Ƀg���E�������������x���̕��˔\�́A��̑�������ߒ��̕��t�ߒ��̂��������ƍl���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�����āA�����̍l�@����A�ނ�͕��ː����f�ɂ����āA��ςȂ����ϐ��̉ߒ������̑��x�Ői�s���Ă��邱�Ƃ��m�M����Ɏ������B
�@�������A�c�O�Ȃ���T�A�U�̋Ȑ��̍ŏ��̕����Ɍ�����t�]�̉��߂ɂ��Ă͔ނ�͌���Ă����B�����̃��U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�̓g���E���w�ɂ���Ē��ړI�Ɏh�����ꂽ��N���˔\�ƍl���Ă����B
�m�����̒m���ɂ������n
�@���̃O���t�̉��߂͓���B
�s���ӂP�t
�@�܂��ŏ��Ɏ��̂��Ƃɒ��ӂ��Ăق����B�ʍe�u���ː�����n��̐��w�v�ŋ��߂�����n��̉��́A�o�������݂̂����݂��āA���ꂩ�琶���閺�j��͍ŏ����ݗʂ̓[���Ƃ��ĉ��������̂ł��B���̂Ƃ��A�ŏ�����r���̊j�킪���݂���ꍇ�́A���ꂼ��̊j�킪�A���̑��ݗʂŏo�������Ƃ��đ��݂������n��i�o���j��ȍ~�j�̘A�������������������āA���̑S�Ẳ��𑫂����킹��悢�B���ː������̕��x�́A���̕����̑��ݗʂ݂̂Ɉˑ����āA���̕����̑��݂ɂ͖��W������A���̗l�Ȏ戵���\�Ȃ̂ł��B
�s���ӂQ�t�@
�@���ɒ��ӂ��ׂ������́A��i��Ђ���w����������̎���́A�g���E���������サ�炭���u���Ă����ꂽ�ł��낤����A���̎�������t���������Ă��āA���̒��Ɋ܂܂�����ː��j��̑��ݔ�͂قڂ��̔������ɔ�Ⴕ�Ă������낤�Ƃ������Ƃł��B
�@���m�Ɍ����ƁA����n��̒��ɒ����������̊j��(228�qa=6.7�N�A228�sh=1.9�N)���܂�ł��邽�ߕ��t�ɒB����r���̒i�K�ɂ���B���t���B�������܂ł̕ω��̗l�q�͕ʍ��u���ː�����n��̐��w�v�R�̗�������������B
�@
�m�Ȑ��T�̐����n
�@�h�t�Ɋ܂܂��228�qa��224�qa�͌��X���t�ɂ������̂�����A�h�t��������������̂��ꂼ��̑��ݗʂ͔������ɔ�Ⴕ�Ă���A���ꂼ��̊j��̒P�ʎ��ԓ�����̕��́A�قړ����ł��B���̑��ݔ������228�qa�����n��̏o�������Ƃ���A�������������������B���l�ɁA224�qa�����n��̏o�������Ƃ���A�������������������B�������ē���ꂽ��̉��i�e�j��̑��ݗʂ̎��ԓI�ω����������j�𑫂����킹�����̂��A�e�j��̑��ݗʂ̎��ԓI�ω��ƂȂ�B�܂��A�e���Ԃɂ��ꂼ��̊j�킪�����P�ʎ��ԓ�����̕��͊e�j��̑��ݗʂɕ���萔�i=0.692�^�������j���悶�����̂ɂȂ�B�������ċ��߂��e�j�킪�e���Ԃɏo�����˔\�̍��v�������d���\�͂̎��ԓI�ω����Ȑ��T�ł��B
�@�h�t�Ɋ܂܂��g���E���w�̓��W�E��228�qa��224�qa���琬��A228�qa�̕��̓A���t�@������o���Ȃ��̂ŁA���W�E��224�qa�̕��˔\���g���E���w�̕��˔\�ł���i�ׁ[�^���̓d���\�̓A���t�@���ɔ�r���ď������j�B���̕��˔\�ɔ�Ⴕ�ă��h��220�qn�i�g���E���G�}�l�[�V�����j����������B�A���t�@�����o�̕��˔\���A���h��220�qn�̔����������ɖ�3.7���̔������Ō�������B
�@
�m�Ȑ��U�̐����n
�@���a���Ɋ܂܂��232�sh��228�sh�ɂ��Ă����t���������Ă����̂ŁA�Ɏ_���n�t���璾�a������������́A���ꂼ��̔������ɔ�Ⴕ�đ��݂��Ă���B���̑��ݔ�����̉���232�sh���o�������̕���n��ƁA228�sh���o�������̕���n��̘A�������������������B�������ē���ꂽ��̉��𑫂����킹�A�e���Ԃɒu����e�X�̊j��̑��ݗʌv�Z�ł���B���̑��ݗʂ�����˔\���x�����߂đ������킹�ē�������̂��Ȑ��U�ł��B
�@���a���i���_���g���E���j����228�sh�͉�ς��ă��W�E��224�qa�ɂȂ�̂ŁA���a���ɂ̓��W�E��224�qa�����X�ɐ�������A���˔\�ƃ��h��220�qn�̔��������㏸���Ă����B�������̂Q�`�R�{�̎��ԁi��10���ԁj���߂���ƒ��a���̃��W�E��224�qa�͐����Ɖ�ς��ލ������l�ɖO�a����B���̂��ߕ��˔\�ƃ��W�E��224�qa�̔����������l�ɖO�a����B
�@���̂�����͕ʍ��u���ː�����n��̐��w�v�R(1)(a)���Q�Ƃ��ꂽ���B�����̂w1��228�sh�łw2��224�qa�ƍl����悢�B�����̂R(3)�̍Ō�Œ��ӂ����悤�ɁA�m�e�j��̒P�ʎ��ԓ�����̕��n���m�e�j��̑��ݗʁn�~�m����萔(=0.692�^������)�n������w2�̑��ݗʂ̏��Ȃ��ɘf�킳��Ȃ����ƁB228�sh�̔�������224�qa�̔������ɔ�ׂĔ��ɒ�������228�sh�̕��˔\�͂قڈ�肾����A���˔\�͂܂���224�qa�̔������ő��債�Ă������ƂɂȂ�B
�@
�m�Ȑ��T�A�U�̏����Ɍ�����t�]�̐����n
�@���̕����́A����n��̌���̐�����212�ob�i���ː��j�ɗR������ω��ł��B��萳�m�Ɍ����ƁA212�ob�̓��������Ȃ�����A���̃�����Y���ł���212�ai(������60��)��212�oo(������0.3�ʕb)�̃�����̕��˔\�ł��B���̗��҂͔��������ɂ߂ĒZ���̂ŁA�����̕��˔\���x�͐e��212�ob�̔�����(10.6����)�ŕω�����B
�@�g���E���̕��˔\�Ȑ��̏����Ɍ����闎�����݂́A���t�ɂ������ŏ��̎����̒��ɑ��݂��Ă������ː���212�ob�i������10.6���ԁj���A���a���Ɨn�t�ɕ��������Ƃ��A���_�����Ƃ��ăg���E�����_�����ƈꏏ�ɐ͏o���Ē��a���̕��֎�荞�܂ꂽ���߂ɐ������B���t���̗ʂ������݂��Ă������̂���������10���Ԃŕ����̂ł��B���̂Ƃ����a���ɂ�224�qa(�g���E���w)�͊܂܂�Ă��Ȃ��̂ŁA�V����212�ob�̋����ɂ͂��Ȃ�̎��Ԃ�������̂œ�����o�Ă��̕��˔\�̉e���͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�@�܂��h�t�̃g���E���w�̕��˔\�����Ȑ��̏����Ɍ�����㏸���A��͂���ː���212�ob�̐����ɂ����̂ł��B�h�t����������ɂ́A�h�t��212�ob�͊܂܂�Ă��Ȃ��B�������A������o�Ă��W�E��224�qa�i������3.6���j���o���e�j��Ƃ�����t���B������āA212�ob�̑��ݗʂ͂��̕��t�l�܂ʼn��Ă���B���ׁ̈A�ŏ��̂Q���Ԃɕ��˔\���}�ɑ��債���̂ł��B���̓�����͕ʍ��u���ː�����n��̐��w�v�R(1)(a)���Q�Ƃ��ꂽ���B�����̂w1��224�qa�łw2��212�ob�ƍl����悢�B
�@���U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�̓g���E���Ő���������A�����i1902�N3���`9���j�ɂ킽�鑪������{���ăE�����ƃE�����w�ɂ��Ă����l�Ȏw�����I�ȕω����m���߂Ă���B����͔ނ炪�g���E���Ő������Ă������炱�����������邱�Ƃ��ł����̂ł����āA�ŏ�����E�����ƃE�����w��p���Ă̐����͂��ڂ��Ȃ������낤�B
�@�����A�E�����w�ɕt���Ă͓������܂������Ȃ������B�P�D�ŏq�ׂ��N���b�N�X�̃E�����w�̐����̔���(1900�N)�́A�d����p��p���Ăł͂Ȃ��Ďʐ^�Ŕ�p�������˔\���m����ł������B�Q�D(�Q)�R�D�Œ��ӂ����悤�����U�t�H�[�h�������������ނ̕��ː��̓��A�A���t�@���͓d����p�͋������A���ߗ͂͋ɂ߂Ďキ���ꖇ�őj�~���ꂽ�B����A�x�[�^���͓d����p�͋ɂ߂Ďア�����ߗ͂͂قڂ����ɋ߂����̂������Ă���B���̂��߃N���b�N�X���ʐ^�Ŕ����́A�A���t�@�����~�߂����x�[�^���͒ʂ����̂ŃE�����w���ł����B�Ƃ��낪�\�f�B�������p�����d�����ɂ����@�ł̓E�����w�͌��o�ł��Ȃ������̂ł��B
�@�������A�₪�ă\�f�B���E�����w�̓x�[�^���݂̂�����A���t�@���͕����Ȃ����Ƃ�m��B�����ē����̂`�E�f�E�O���A���J�������x�[�^����p�̓���d�������g���ď�L�̎����m�F�����̂ł��B(�����U�D�Q��)
�m�����̒m���ɂ������n
�@�E�������E�����w�����g���E���ƃg���E���w�������̂Ɠ��l�Ȏw�����I�ȕ��˔\�ω����������A����������I�Ɋm���߂�̂͋ɂ߂č���ł������낤�B
�@�Ȃ��Ȃ�g���E���w����224�sh�̔�������3.6���ŁA���̑����ƌ����̃O���t��ɂ͂R�T�Ԉȉ��ő��肽���A�E�����w���̓��ʑ́i234�sh�A230�sh�j�̔������́A�Z�����i234�sh�j�ł�24��������A���˔\�����J�[�u���m���߂�ɂ͂S�����ȏオ�K�v�ł������B�܂�234�sh�̕���̓�����ł͂Ȃ��ă������畁�ʂ̓d�����ɂ�鑪��ł͂��܂�����ł��Ȃ������ł��낤�B
�@������E�����ƃE�����w��ǐՂ��Ă��������̉Ȋw�҂͐����ł��Ȃ������B���̈Ӗ����ŏ�����g���E���ɏW���������U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�͍K�^�������B
�@���U�t�H�[�h��1930�N�A�M���ɗ�ꂽ�Ƃ��A���U�t�H�[�h���̖�͂Ƃ��ăL�[�E�B���ɕ��˔\���x�̕ω���\���w�����̃J�[�u��g�ݍ��킹�����̂ɂ��Ă���B���̂��Ƃ�����킩��悤�ɁA���U�t�H�[�h�ɂƂ��Ă��̔����͂�قnjւ炵���d�v�Ȃ��̂ł������悤���B

�@
�i�S�j�G�}�l�[�V���������\�̌����Ɖ�
�@���������Ĕނ�́A�g���E���ƃg���E���w�����������ƁA�G�}�l�[�V���������\�͂̑S���͂�������w�̕��Ɉڂ邪�A�����o�ɂ�Ăw�̃G�}�l�[�V�����̔������͒ቺ���Ă����A�G�}�l�[�V�����̔����\�͂��������g���E���̕��́A���ɏ����ÂG�}�l�[�V���������\�����Ă������Ƃ��m���߂Ă���B�i���}�Q�Ɓj�B
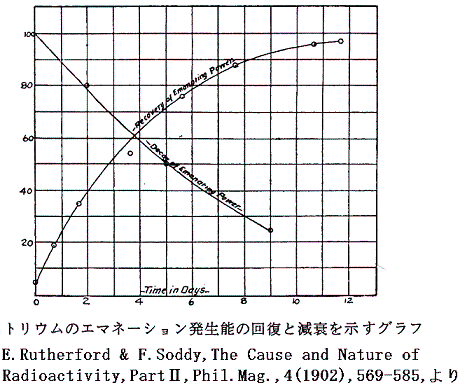
�@�����āA���̃J�[�u�͑O���i�T�j�œ����g���E���ƃg���E���w�̕��˔\�i�����̌��t�Ō����A���t�@���̕��o�j����������ƌ�������������ȋ����������A���̔������������ł������Ƃ��������B
�m�����̒m���ɂ������n
�@�g���E���w�̓��W�E��228�qa��224�qa���琬��A228�qa�̕��̓A���t�@������o���Ȃ��̂ŁA���W�E��224�qa�̕��˔\���g���E���w�̕��˔\�ł���Ƃ݂Ȃ���i�ׁ[�^���̓d���\�̓A���t�@���ɔ�r���ď������j�B�g���E���w�i���W�E��224�qa�j���A���t�@���q���o���ă��h��220�qn�ɕ���̂�����A�g���E���w�̕��˔\�i�����q���o�j�ƃg���E���G�}�l�[�V�����i���h��220�qn�j�̕��o�������ɋN����B���̂��߁A���҂͋��ɖ�3.7���̔������Ō������邱�ƂɂȂ�B
�@�܂��g���E�����G�}�l�[�V���������\������̂́A�������ꂽ�g���E������228�sh������224�qa���~�ς��鎖�ɂ��B����͕��˔\�i�����̕��o�j�����Ă����̂Ɠ������J�j�Y���ɂ��B
�@�������A�ނ�͂��̌��_�ɍ��f�����B�Ȃ��Ȃ瓖���̔ނ�̓g���E���w�̕��˔\�̓g���E���i�g���E���w�ł͂Ȃ��j�̕ϊ��̂�����ł���A�G�}�l�[�V�����̓g���E���w�̕ϊ��̕\�ꂾ�ƍl���Ă�������B�܂�A�g���E���͂����N��ԁi���ꂪ�g���E���w�j�ɂȂ�A�G�l���M�[�̕��˂��s���悤�ɂȂ�B���̃G�l���M�[�̕��˂��g���E�����������˔\�ł��B�܂��g���E���w�͂���ɕϊ����ăG�}�l�[�V��������ƍl���Ă����B�i���}�Q�Ɓj
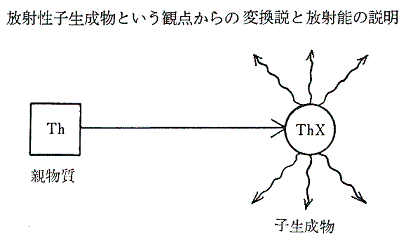
�@������A�g���E���ƃg���E���w�̃G�}�l�[�V���������\���̂��̂��A�g���E���ƃg���E���w���������˔\�̕ω��Ɠ��l�ȕω����������Ƃ́A�ނ�ɂƂ��ĈӊO�Ȏ����������B�ނ�ɂƂ��ăG�}�l�[�V�������g���E���w���l�������G�l���M�[���U�Ɠ������x�Ői�ނ��Ƃ́A�S���̋��R���Ǝv��ꂽ�B
�@�������A����̓g���E���w���A���t�@���ƃG�}�l�[�V�����̓�ɕ������邱�Ƃ������������錋�ʂ���������A�P������ɂ́A�ނ�͂��̐V���������ɒB����B
�@�����܂ł̌��_��1902�N5���܂łɓ���ꂽ���̂ł��B���̒i�K�ŎO�̑傫�ȓ䂪���݂����B
- ���U�t�H�[�h�ƃ\�f�B���܂߂āA�l�X�ȉȊw�҂ɂ��A�E�����y�т��ꂩ�番�����ꂽ�E�����w�̒��ɁA���邢�̓g���E���y�т��ꂩ�番�����ꂽ�g���E���w�̂Ȃ��ɁA���w�I���͂ł͂ǂ����Ă������ł��Ȃ����ނ̐���������炵�����������Ă����B���̓��ނ̑��݂͕��˔\�̎�ށi�������ˁA�������ˁj�̈Ⴂ�₻�̌����̎d���̈Ⴂ����\�z�����悤�ɂȂ����̂����A�ǂ����Ă������̎��̂𑨂��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
- ��L�̃g���E���ƃg���E���w���������˔\�̋����ƁA�g���E���ƃg���E���w�������G�}�l�[�V���������\�̋����̑Ή��W�̈Ӗ����s���������B
- �O���i�R�j�̃O���t�̍ŏ��̂Q���ԂɌ�������˔\�̋}���ȑ���ƌ����̈Ӗ����s���������B
�m�����̒m���ɂ������n
�P�D�̓��ނ̕����s�\�̕����́A�����̌��t�Ō����E�����A�E�����w�A�g���E���A�g���E���w���ꂼ��̒��ɑ��݂�����ނ̓��ʑ̌��f�ł��B����炪�����ł���悤�ɂȂ�̂͂܂���̂��Ƃł��B���ʑ̂̊T�O�̒m���Ă��Ȃ����������ɂ����Ă͍�����[�߂镨�������B
�R�D�̌��������ː���212�ob�ɂ����̂Ɖ���̂͂܂���̂��Ƃł��B
�@��L�̋^��̒����Q�D�ɂ��ẮA1902�N6���܂łɃ��U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�͐V���������ɒB����B����̓E������g���E���̕����s�\�̕��˔\�́A�E�����w��g���E���w�����������Ƃ������ɕ��˂����G�l���M�[�ŁA�E������g���E�����̂������Ă���ƌ��Ȃ��邱�ƂɋC�Â��̂ł��B
�@�܂�g���E���͕��˔\����o���ăg���E���w�ɕω�����A�g���E���w�͂���ɕ��˔\����o���ăg���E���G�}�l�[�V�����ɕω�����A�g���E���G�}�l�[�V���������˔\����o���ăg���E���`�֕ω�����̂ł��B�i���}�j
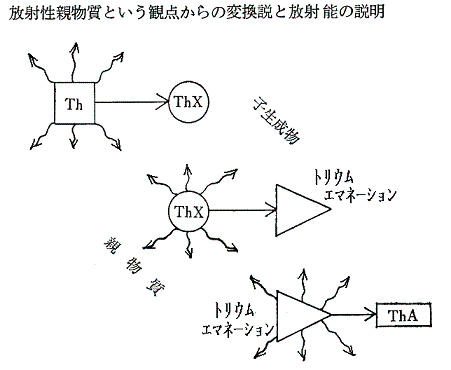
�@���̂悤�ɍl����A�g���E���ƃg���E���w�̕��˔\�̑����̊W���A���˔\�ƃG�}�l�[�V���������\�̑Ή��W���S�Ă��܂������ł��邱�ƂɋC�Â����̂ł��B���������I�ȑO�i�������B������q�ׂ��̂��O�L�_��4.�ɕt���������u����ɐi���_�I�l�@�v�̈�߂ł��B
�@��ɏq�ׂ��悤�ɗl�X�ȋ^�₪�������ō��ׂƂ�����Ԃł��������A�ނ�͂���܂ł̌��ʂ܂��āA���Ȃ�ۑ�������Ƃ͂Ȃɂ��G�}�l�[�V�����Ƃ͂Ȃɂ��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��挈���ƌ��ɂ߂āA�ċG�x�ɖ������炻�̉𖾂ɑS�͂𒍂����B�@
�@
�i�T�j�����̖{��
�@���������͗z�C�I���ł͂Ȃ����Ƃ����\���͗l�X�ȉȊw�҂����Ă����B�������A���t�@���͂ǂ����Ă������d��ŋȂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł��B�����Ń��U�t�H�[�h�̓����͓d�q�i�����j�ɔ�ׂĂ͂邩�ɏd���āA�����ʼn^�����闱�q�ł��낤�Ƃ����\���̉��Ƀ����̕Ό��ׂ�����Ɏ�肩�������B1902�N��9���̂��Ƃł��B
�@�ނ́A�݂��ɐڋ߁i�Ԋu1mm�j���Ă����ꂽ�Q�T���̕��t����ׂ���Ӑ������̕Ό�������胉�W�E�������̏�ɒu�����B���ɒu�������W�E������o��A���t�@�����ʉ߂��Ă���̂���ɔ����t���������d��ő��肷��B�Ό��������͂ȓd���ɂ̊Ԃɒu���ƃA���t�@���������דd���q�Ȃ�ΕΌ��͂��ĕΌ����ăX���b�g�̕ǂɓ�����X���b�g��ʉ߂���ʂ����邾�낤�B�����āA���̕Ό������̓X���b�g�̏o���ɒu���������b�ŃX���b�g�̍��E�ǂ��炩�̔������ǂ��ł݂āA���̉e���ׂ邱�ƂŊm�F�ł��邾�낤�ƍl�����B�Ό����ɐ��f�K�X�𗬂����̂̓��W�E������ł���ː��K�X�i���W�E���G�}�l�[�V�����qn�j�𐁂��������߁B
�@�]���̓d�����Əی��d�ʌv�̑���ɔ����d���p�����͕̂��˔\���m�̊��x���グ�邽�߂ł��B���̌��d��͍ג���������≏���Ŏx���A���̏�[�߂�����ג���������݂艺�������̂ɂ����Ȃ������������̂�����ɐݒu���邱�Ƃ��ł����B���̋����Ƌ����ɓ���̓d�ׂ�^���Ă����ƌ݂��ɔ������ċ����͋����ɑ��Ă���p�x�ɊJ���B���s�̊Ԍ���ʂ蔲���Ă����A���t�@���̍��C�I���̒��ŋ����E�����Ɣ��Γd�ׂ̃C�I���������E�����Ɉ��������āA�����̓d�ׂ𒆘a�������͎���ɂ��ڂށB���U�t�H�[�h�́A�O���̃K���X�����Ƃ����Ė]�����ł��̔��̍~���������A���̉����ڊዾ���̖ڐ��ڂ�ʂ�߂��鎞�Ԃ𑪒肵���B�ނ͋����̍~�����x�ɂ���ĕ��ː��̋��x�𑪒肵���̂ł��B(�Q�l�����U�D)
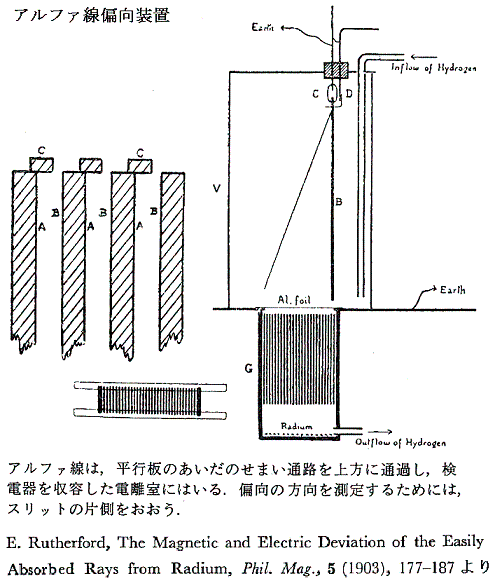
�@�����̌��ʂ́A�A���t�@���͊m���Ɏ���ɂ��Ό����Ă���A�Ό��̕����̓A���t�@�������ɑѓd���Ă��邱�Ƃ������Ă����B
�@�܂��A���U�t�H�[�h�͐Ód�ꒆ�ł̕Ό������ׂ��B�A���t�@���q��Ό�������ׂɂ͋ɔԓd���ɍ��d����K�v�Ƃ��邽�ߋɔԃX�p�[�N�ɔY�܂��ꂽ�B���̂��ߐ��m�ȑ���͍���ł��������A�Ȃ�Ƃ����߂邱�Ƃ��ł����B�d��ɂ��Ό��ʂƎ���ɂ��Ό��ʂ�p���ă����̂��^���̒l�����ς����Ă݂�ƁA�����������Ⴂ�ɑ傫���āA���q���x���̑傫���������Ƃ��������B���̎����͔ނ�̗��_�ɑ傫�Ȑi�W��^�����B�i���U�t�H�[�h�́A�����̎���������ɗǂ����x�ŌJ��Ԃ��āA1906�N�A�������q�̂��^�������f�C�I���̂Q�{�ł��邱�Ƃ������Ă���B�Q�l�����U�D���Q�Ɓj
�@����܂Ŕނ�͑��̑����̉Ȋw�҂Ɠ����悤�ɁA���˔\�Ƃ����͕̂����ł͂Ȃ��i�w���̗l�ȁj�G�l���M�[�g�̂悤�Ȃ��̂��A���I�ɕ��˂���錻�ۂ��Ǝv���Ă����B�����̕��o���A���̎��̂��d�q�ł��鎖�����������Ă��Ă������A��������q�̈ꕔ�ƍl����ɂ͂��܂�ɂ������Ȃ��̂���������A��͂�A���I�ɕ��˂���鉽���̐����ɂ��������Ȃ������B
�@��������˔\�̗l�X�Ȕ������ɂ��ϓ����A�����̕��ː����̃G�l���M�[�������Ԃ��A�����Ԃ��A�����Ԃ��ɂ킽���ď��X�ɘA���I�ɗ���o�����ۂ��ƍl�����Ă����B
�@���ꂪ����A���q���x���̑傫���̌ł܂肪�A�s�A���I�ɁA����C�ɕ��o����錻���ł���Ɖ����Ă����̂ł��B
�m�����̒m���ɂ������n
�@�\�f�B��1903�N7���ɃC�M���X�i�����h���j�̃����[�[�̌������Ń����[�[�Ƌ��ɁA���W�E���E�G�}�l�[�V�������K���X�̖эǂɕ������A�������������ĕ����v�Ō��������B���̌��ʃw���E���̂c3�����ԈႢ�Ȃ����݂��鎖���m���߂Ă���iW.Ramsay,F.Soddy,Gases Occluded by Radium Bromide,Nature,68(1903),246.)�A���W�E���G�}�l�[�V��������w���E�����������鎖���m�F���Ă���B�������A���̎��_�ł̓G�}�l�[�V�����������q����o���鎖�͉����Ă��Ȃ������̂ŁA�����q�����̂悤�ɂ��Đ������w���E���ƌ��т��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@�����q���w���E���̌��q�j�ł��邱�Ƃ��������̂́A1908�N�Ƀ��U�t�H�[�h�ƃ��C�Y�ɂ���ĂȂ��ꂽ����(E.Rutherford and T.Royde�APhil.Mag.17(1909)�A281)�i�Q�l�����T�D�ɖ|��j�ɂ���Ăł��B�ނ�͕��ː���������o�郿���q���K���X�ǂ̒��ɏW�߁A�������d�ǂɓ����Ĕ����������B�����ăX�y�N�g�����w���E���̂���Ɗ��S�Ɉ�v���邱�Ƃ��m�F�����B���̎��_�Ɏ����ă����q���w���E���̌��q�j�i�w���E��4�j�ł��邱�Ƃ��m�肷��B�@
�@
�i�U�j�G�}�l�[�V�����̖{��
�m�����̒m���ɂ������n
�@�S�D�i�R�j���ŏq�ׂ��悤�ɁA�g���E�����̃��W�E��228�qa������̂́A���̒Z���������̂ɂ��̑��ݗʂ͋ɔ��ʂ���������A�ɂ߂č�������B����ɑ��āA�E�������̃��W�E��226�qa�͂��Ȃ蒷���������i1622�N�j����������t�ɂ���E�����z�Β��ɂ͂��Ȃ�̗ʂ��܂܂�Ă���B���̂��߁A���w�I�ɕ������Č��f�Ƃ��Ď��o�����Ƃ��\�ł������B�i���W�E���͂Q���̃A���J���y�ދ����Ȃ̂ŁA�o���E���Ɠ������w�I���������j
�@�����A����n��̔������������悤�ɃE�����w�̓g���E���w�ƈ���ăG�}�l�[�V�������o���悤�ɂ͌����Ȃ������B���̂��Ƃ͈ˑR�Ƃ��ē�ł��������A�E�����z�Β����番�����ꂽ���W�E���͑��ʂ̃G�}�l�[�V��������o���邱�Ƃ������Ă����B
�@���W�E���������������˔\����A�����̉Ȋw�҂̓��W�E�����E������g���E���Ɠ����悤�ȍ����I�ȕ��ː����f���ƍl���Ă����B���̂��߁A�E������g���E���Ɠ����悤�ɃG�}�l�[�V��������o���镨���ł��郉�W�E���w�����W�E�����Ɋ܂܂�Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���āA���̕����ɑ����̓w�͂𑱂������������Ȃ������B���̗��R�͍����̒m�����疾�炩�ł��B���W�E���i226�qa�j���̂��̂��G�}�l�[�V��������o���镨���������̂�����B
�@�g���E���w�i224�qa�j����o��g���E���G�}�l�[�V�����i220�qn�j�̔������i52�b�j�͔��ɒZ�����ߒ�ʑ��肪�\�Ȃقǒ~�ς��Ȃ����A���W�E��226�qa����o�郉�W�E���G�}�l�[�V�����i222�qn�j�̔������i3.8���j��6000�{�������̂ŗe�Ղɑ��ʂ��~�ς���B���ʂɒ~�ς��ꂽ�G�}�l�[�V�����́A���̊�ȕϓ����͂邩�Ɍ֒������������Ŏ����B���̂��߁A���U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�̓G�}�l�[�V�����̖{���ׂ邽�߂Ƀg���E���G�}�l�[�V�����̑���Ƀ��W�E���G�}�l�[�V������p���邱�Ƃɂ��߂炢�͂Ȃ������B
�@�ނ�͂܂����W�E���G�}�l�[�V�����̎����s���萫�͌ő̉������W�E���������z���ɗR��������̂ł��鎖���A�n�t��Ԃł̔����\�Ɣ�r���邱�Ƃɂ�薾�炩�ɂ����B
�@���ɔނ�́A���W�E���̃G�}�l�[�V�������������̍�������̒���ʂ��Ă��ω����Ȃ����Ƃ���A�g���E���G�}�l�[�V�����Ɠ����悤�ɉ��w���������Ȃ����Ƃ��m���߂��B
�@�܂�1902�N10���ȍ~��C�̉t�����u�𗘗p�ł���悤�ɂȂ�A�g���E����W�E���̃G�}�l�[�V�������t�̋�C�ŗ�p���������ǂ�ʂ����Ƃɂ��A���ꂪ�}�C�i�X150�x�t�߂ŋÏk���鎖���m���߂��i�����킩���Ă����h���̕��_��-61.7���A�Z�_��-71���j�B
�@����ɁA�G�}�l�[�V�����̏o�����˔\�̌����Ȑ��́A�G�}�l�[�V�������Ïk���Ă��邩���Ȃ����ɂ͑S���e������Ȃ����Ƃ��m���߂Ă���B
�@�ނ�͂����̈�A�̎�������A�g���E����W�E���̃G�}�l�[�V�������A���̏����O�Ƀ����[�[�ɂ�蔭������Ă�����K�X�i�w���E���A�l�I���A�A���S���A�N���v�g���A�L�Z�m���j�Ɠ��O���[�v�ɑ�����A���w�I�ɕs�����ȃK�X��Ԃɂ��関�����̌��f�i�܂茴�q�j�ł����Ɗm�M����Ɏ������B
E.Rutherford,F.Soddy,Condensation of the Radioactive Emanations,Phil.Mag.,5(1903),561-576
�@
�T�D���ː��ϊ���
�@�A���t�@����G�}�l�[�V�����̂Ȃ邩�������Ă��̂ŁA���U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�͍�����˔\���s�v�c�Ȍ��ۂ̑S�̑������ʂ����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�܂�X�̕�������o����ː��͑S�Ă��̌��q�̕���ɔ������ŁA�e���q�̓����q�i�Ƃ��ɂ̓����̓d�q�̏ꍇ������j����˂��ĕʂȌ��q�ɉ���B�����ĕ��˔\�͌��q�̕ω��̕\��ł͂Ȃ��āA����Ƃ�����p���̂��̂̈ꕔ�������̂��B�����ă����q�̕��o�������A���˔\�ɔ����G�l���M�[�Ǝ��ʂ̑����������N�����̂��Ƃ͂�����Ɨ��������B�i���}�Q�Ɓj
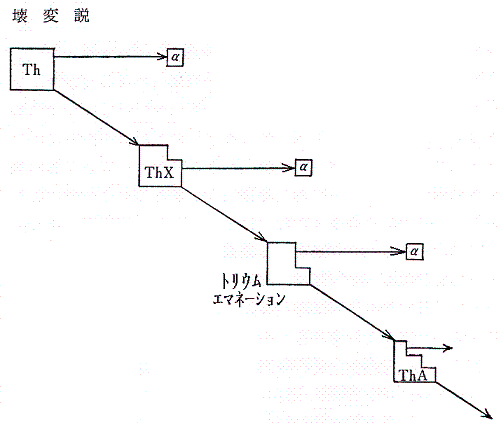
�@���U�t�H�[�h�ƃ\�f�C�́A�ȏ�q�ׂ��������ʂ���A�g���E������g���E���w�������A�g���E���w����͋C�̂ł���G�}�l�[�V�������������A�G�}�l�[�V�����͍X�ɋC�̂���ő̂̔����q�ƂȂ��Ď��͂̕����ɕt�����A�����ɕ��˔\����������B�����̕ω��͉��w�ω��ł͂Ȃ��A���f�̉�ωߒ��ł���A���ː��͂����̕ϊ��ߒ��ɔ����ĕ��o�����ƍl�����B���ꂪ���ː��ϊ����ł��B
�@�ނ�͕��ː��ϊ������������ŏI�I�Ș_����1903�N4�����ɂ܂Ƃ߁A5��1��������\�����B���ꂪ�L���Ș_��
E.Rutherford & F.Soddy,Radioactive Change,Phil.Mag.,5(1903),576-591
�ł��B�i�Q�l�����T�D�ÓT�_���p���ɖ|��j
�@���}�͔ނ�̍ŏI�_���Ɍf�ڂ���Ă������n��̐}�ł��B
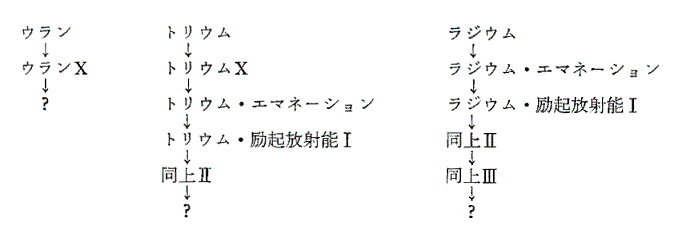
�@���W�E���̌n��Ɋւ��ẮA���W�E���̕���̑������E������g���E���̕S���{�������̂́A���̕���̎����i�������j���Z���i�ނ��2,3��N���Z���Ɨ\�z�j����ŁA���̂��ߎ��R�E�ɂ����鑶�ݗʂ����ɏ��Ȃ��̂��Əq�ׂĂ���B���̂������W�E���͍z�����ɑ��݂��鑼�̌��f�̈�����Ăł������n��̓r���̎Y���ł��낤�Ƃ͂�����\�z���Ă���B�����̒m���Ō����܂��ɃE�����̕���Y�������W�E���Ȃ̂����A���̒i�K�ł͂܂��A�����܂Ō������Ă��Ȃ��B
�@���̒i�K�ł́A�ŏI�I�ɐ��������̂����ob�̈��蓯�ʑ̂ł��邱�Ƃ͉����Ă��Ȃ��B�܂��A���̎��_�ł͕���ɔ����ĕ��o����郿���q�i���邢�̓����q�j����Ȃ̂������Ȃ̂��͉����Ă��Ȃ����A�����炭��̐e���q�����̕��ː��i�����qor�����q�j���o���P�̌��q�ɕ����̂��낤�Əq�ׂĂ���B����ɍۂ��Ĉ�̐e���q�����ވȏ�̎q���q�����؋��͂Ȃ��̂ŁA����n����P��̘A���I�Ȃ����ł��낤�Ɨ\�z���Ă���B
�@�ނ�́A�����̉ߒ����P���q���w�����Ɨގ����Ă��邱�Ƃ��A���ł�1902�N6���ɋC�Â��Ă������A���̒i�K�ł͂͂�����Ǝw�����������Ƃ肢��āA���ː��ω��̖@����������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�����č����̌��t�ł�������萔�ɂ����A���˔\�̌��ۂ̕��G���́A���ꂼ��قȂ����萔���������A�݂��ɓ����ɕω����Ă������̈�����^�̕������������邱�ƂɋN�������Ƃ������Ƃ��͂����藝�������B�܂��ɁA���̕������͉�ς̌������A���q���̂��̂Ɋ�Â����R�����I�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ������Ă����̂ł��B
�@�_���̍Ō�ŕ��ː��̃G�l���M�[�ɂ��ċ��������͂����Ă���B
�@���ː���ς̏ڍׂ͊��S�ɂ͉����Ă��Ȃ��������A���W�E���ɂ��Ă̓A���t�@���q�̕��o���܂̕���ߒ����m���Ă����B����ɂ���ă��W�E�����q�̉�ςɔ����G�l���M�[�̍Œ�l(�A���t�@���q�̃G�l���M�[�̌ܔ{)�����߂���B�����A�{�K�h�����͂قڒm���Ă����̂Ń��W�E���P�����̌��q���͑�̉����Ă����B���������ĂP���̃��W�E���̉�ςɔ����ĕ��o�����S�G�l���M�[���v�Z���Ă݂�ƂP��cal�^���̑傫���ɂȂ�B����͎_�f�Ɛ��f���琅�P�����ł���Ƃ��������M4000cal�^���ɔ�r����ƂQ���{�ȏ�A���Ƃɂ��ƂP�O�O���{�ł��邩������Ȃ����𒍈ӂ��Ă���B
�@�܂��A�����P�̃C�I�������̂ɕK�v�ȃG�l���M�[�͂قډ����Ă����̂ŁA���W�E���E�E���j�E���E�g���E�����P�ʎ��Ԃɕ��o����G�l���M�[�l�͂��̓d����p����v�Z�ł���B���̒l���A���t�@���q���o�ɔ����G�l���M�[�l�Ŋ����āA���̎O�̕��ː����f�̂P�����P�ʎ��Ԃɉ�ς�������v�Z�ł���B�����ă��W�E���̔������͖�P��N�A�E���j�E����g���E���̔������͖�10���N�����ς����Ă���B(���̓�����͍��Z�����̒m���ŗ����ł���̂Ō��_����ǂ�ł݂��邱�Ƃ�E�߂�B)
�@�����čŌ�ɁA���q�̉�ς���o�Ă��邱�̔���ȃG�l���M�[���A���ː����f�ȊO�̌��f�ɂ��������܂�Ă���̂ł͂Ȃ����A�܂��F�������w�ɂ����鑾�z�G�l���M�[�̌������ꂩ���m��Ȃ��Ɨ\�����Ă���B
�@
�@���U�t�H�[�h�͂��̌�1907�N�܂Ń}�M����w�ɍݐE�������̖{���̒T���ƁA�����p�����U���������s���B1907�N����}���`�F�X�^�[��w�Ɉڂ�B1908�N�u���f�̕���ѕ��ː������̐����Ɋւ��錤���v�ɂ���m�[�x�����w�܂�����B�܂��A�����ōs������������L�����L�j���q���f�������B�����đ����̗L�\�Ȑl�ނ���Ă��B1919�N�L���x���e�B�b�V���������̏����ɏA�C���A1937�N�ɖS���Ȃ�܂ŃP���u���b�W�����w�̉����������ɂ����B
�@����\�f�B��1903�N10������O���X�S�[��w�ɐE�āA�����ŕ��ː������̉��w�I�ӂ�܂��Ɋւ��闝�_�W�����A�ψʑ��i���f����������o����ƌ��q�ԍ����Q�قǒႢ���f�ɂ����A��������o����ƌ��q�ԍ�����傫�Ȍ��f�ɂȂ�j��A���ʑ̂̊T�O(1913�N��Q�l�����T�D�ɖ|��)�\�����B���̌�1914�N �X�R�b�g�����h�̃A�o�f�B�[����w�A1919�N�I�b�N�X�t�H�[�h��w�̋����ƂȂ�A�P921�N�u���ː������̉��w�Ɋւ��錤���v���m�[�x�����w�܂���������B
�@
�U�D�Q�l����
�@���q�T���̐X�ɕ��������Ă����ɂ́A���˔\�Ƃ͉����̗������s���ł����B���U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�ɂ����ː�����𖾂̉ߒ���������Ă���Ă���̂������P�D�ł��B
�@����́A���̕���̊�{�I�����Ȃ̂ł����A���̖{�͎����ĉ�����\�����������ɓ���ȕ��͂ŁA���̂܂ܓǂ�ł��A�������������̂��悭����Ȃ��i���ꂾ�������̉Ȋw�҂͍��ׂ̒��ɂ����j�B����ŁA�������̓��e���������g�o����肽���Ǝv���Ă��܂����B
�@
�@�������A���̖{�𗝉�����ɂ͎��ۂ́m����n��̒m���n�ƁA���́m����n�������I�ȐU�镑���̐��w�I�ȗ����n���s���ł��B
�@���������炩���ߗ������Ă����Ȃ��ƁA������ǂ�ł������������ł��B���̂��ߒ����ԒI�グ��Ԃł������A�ŋ��u���ː�����Ɣ������v�S�D�Ɓu���ː�����n��̐��w�v�̏������ł����̂ō�邱�Ƃ��ł��܂����B
�@
�@����Ă݂ĉ��߂Ċ�����̂́A���̖��͑����̉Ȋw�҂��S���͂��X���Ď��g�������Ő�[�̃e�[�}�������Ƃ������ƁA���̉𖾂̉ߒ��������Ȋw��������햡�Ƌ����A�����ĉ𖾂ɐ����������U�t�H�[�h�ƃ\�f�B���^�̗ǂ��ł��B�K�^�̏��_�́A�ő���̓w�͂��ׂ����҂ɖj�ނ悤�ł��ˁB�@
- �s�E�i�E�g�������A�������O ��u���錴�q�v�|���U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�̋��������j�|�@�O���o�Łi1982�N���j
- ����n��̐��w�ɂ��Ắ@http://ksgeo.kj.yamagata-u.ac.jp/~kazsan/class/geomath/ex16.html
- �G�~���I�E�Z�O�����A�v�ۗ��܁A���T���u�w������N�I�[�N�܂Łv�݂������[�i1982�N���j�A61�`79��
- �X�e�B�[�u���E���C���o�[�O���A�{�ԎO�Y��u�d�q�ƌ��q�j�̔����v���n�T�C�G���X�Ёi1986�N���j�A136�`150��
- �����w�ÓT�_���p���V�u���˔\�v�A���C��w�o�ʼn�i1970�N���j�A103�`200��
�m2009.12.11�NjL�n
�@���̃y�[�W��ǂ܂ꂽ���Z�����N�ɉ��L�̖{��ǂ܂�邱�Ƃ������E�߂܂��B������łɂȂ��Ă��܂����A�}���قɂ͂����Ƃ���Ǝv���܂��B
- �A���t���b�h�E���}�[���@����̉Ȋw29�u���q�̒T���v�@�͏o���[�V�Ёi1969�N���j
�@���̂g�o�Ŏ��グ���������܂߂đ����̋�̓I�Ȏ�@���ڂ��������Ă���B�����̘b�ȍ~�ɂ��Ă��ڂ����B���̃y�[�W�Ő�����������n��̎��ۂƂ��̐��w�I�������Q�Ƃ���ēǂ܂��Ɨǂ�����Ǝv���܂��B
- �G�h���[�h�E�m�E�_�E�b�E�A���h���[�h���@����̉Ȋw6�u���U�t�H�[�h�v�@�͏o���[�V��(1967�N��)
�@���j�I�ȗ��ꂪ�ǂ��킩��B�����Ă���̓��U�t�H�[�h�̕]�`�Ƃ��ďG��ł��B�A���h���[�h�́A���U�t�H�[�h����Ă������̒�q�E���������҂̓��̈�l�ł��B