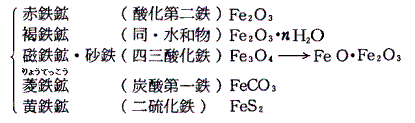
このページを印刷される方はこちらのバージョンをご利用下さい。ブラウザーでは見にくいのですが印刷は鮮明です。
鉄は鐵とも書く。これは”金(カネ)の王なる哉(カナ(感嘆の助辞))”という意味で、例えば新日本製鐵株式会社の社名に、自分たちが工業の根幹を支える産業であるという自負と気概を感じる。それゆえ製鉄の歴史は面白い。その面白さ伝えたい。図は最後に掲げる参考書から引用した。
[2012年11月追記]
新日本製鐵株式会社は、2012年10月1日に住友金属工業株式会社と合併されて、新日鐵住金株式会社となられました。それに伴いまして第7章で引用していた刊行物のURLが変更になっています。合併前の技術系刊行物はhttp://www.nssmc.com/company/publications/monthly-nsc/index.htmlにて紹介されています。引用したもの以外にも貴重な情報が有りますので、こちらのURLをぜひ参照されて下さい。
[2019年4月追記]
新日鐵住金株式会社は2019年4月に社名を“日本製鉄”に変更されました。それに伴いまして上記indexのURLは
https://www.nipponsteel.com/company/publications/monthly-nsc/index.html
に変更されています。そのため引用URLのnssmc.comをnipponsteel.comに変更しました。
鉄は地殻での存在量がアルミニウムについで多い金属である。鉄はアルミニウムなどの陽性の強い(電気陰性度の小さな)金属に比べて製錬しやすく早くから用いられてきた。しかし、熔解にかなりの高温を必要とするため、本格的で大規模な使用は銅、金、銀、錫、亜鉛、等に比べて遅れた。
多くの金属の中で、なぜ鉄が王と言われるのか。それは以下の3点の複雑で多面的な優れた性質による。
以下の議論で重要な金属の一般的な性質を説明する。
純粋な単体金属は、原子がキチンと規則正しく並び相互に緻密に結合した結晶構造になり融点が高い。そして原子が規則正しく並んでいるので結晶面に沿って滑りやすく柔らかい。
一方、不純物を含む合金は大きさ・性質の異なる原子が混じる故に結晶構造が壊れガタガタになり融点が低い。また、不純物を含む合金は、ちょうど砂をかんだボールベアリングの様に、結晶面にそって滑りにくく堅い。
融点と硬さの関係が常識とは反した関係になることに注意。このことが製鉄の歴史に於いて重要な意味を持ってくる。
鉄の鉱石として主なものを次に記す。
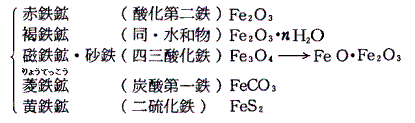
硫黄は鉄を脆くするので、黄鉄鋼のようにSを含んだものは、まず焼いて酸化鉄にして用いる。
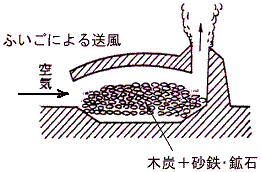
初期の製鉄炉は木炭と鉱石を層状に装入して、ふいごなどで空気を送って燃焼させ、そのとき生じるCOによって酸化鉄を還元したものと思われる。
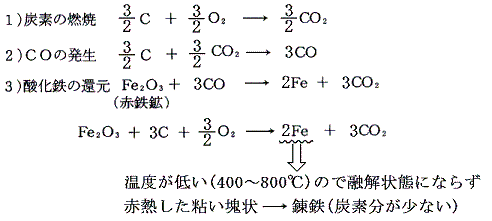
ここで注意すべきは、鉄鉱石は熔けなくても鉄に変えることができることである。一酸化炭素COが鉄と結合している酸素を奪って二酸化炭素CO2となり、鉄鉱石は金属鉄になる。この化学反応に必要な温度は400〜800℃程度で、温度が低ければ、固体のまま還元されて酸素を失った孔だらけの海綿状の鉄になり、温度が高ければ、粘いあめ状の塊になる。これは炭素分の少ない錬鉄といわれるものであり、一般には1500℃以上にならないと熔けないが、熔けなくても鉄ができるのである。
ただしこれは不純物を含んでいるので、硬いものの上で赤熱のまま打ち叩いて不純物を絞り出し、鉄原子どうしをくっつけなおさねばならない。これが「鍛える」という操作である。この操作をすることで純粋な鉄にすることができる。さらにこれを炭に包んで熱して炭素分を加えて鍛えて鋼にすることができる。
純銅Cuは1000℃以上の温度でなければ熔けない。また純銅は柔らかくて道具にならない。ところが錫Snを混ぜると融点が下がり700〜900℃で熔け、しかも硬くなって道具の材料になる。一方純鉄Feは1500℃以上でなければ熔けない。炭素を含有した最も融点の低い銑鉄でも融点は1200℃程度である。そのため歴史上青銅器文明が鉄器文明に先行して発達したと言われている。
しかし、鉄は青銅の場合よりもさらに低い温度で鉄鉱石から鉄に固体のままで変えることができ、これを鍛えれば使用できる鉄ができる。つまり鉄はその融点から想像されるよりも、遙かにやすやすと製造できた。また銅や錫の鉱石の産地は地球上で偏在しており、広範な交易の発達が必要であったのと比較して鉄鉱石は何処にでもあった。そのため冶金学的には青銅に先行して鉄が用いられた可能性がある。
現在青銅器文明に先行する鉄器文明が見つからないのは、青銅は錆びにくく鉄は錆びやすいため古い遺跡で青銅が圧倒的に発見されやすいからかもしれない。また青銅が貴重な金属として王侯の宝庫におさめられたのに対して、鉄は卑しい金属として顧みられず錆びで土に還元してしまったのかもしれない。また鉄は未開の地に於いても小規模で、手軽な装置で製造できたために遺跡として残らなかったのかもしれない。

下図はリビングストンやスタンレーによって報告された、19世紀後期の未開アフリカにおける製鉄の様子。きわめて簡便な方法で製鉄が可能であったことが伺える。棒の先に付いている原始的なふいごで風を送っている。
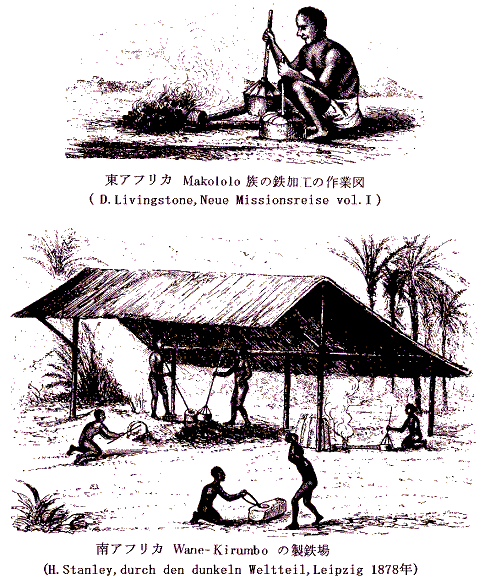
高炉法は14〜15世紀頃ドイツのライン河流域のジーゲルランドで始まったとされている。高炉の発達をうながしたのは送風への水車の利用であった。水車の恒常的で強力な動力により炉内に大量の空気を送り込むことが可能になり、炉内の温度を上げることができるようになった。還元された鉄は温度が高いと活発に炭素を吸収する。炭素の吸収が進むと鉄の融点が下がる。純鉄の1530℃に対して3〜4%の炭素を含有する鉄の融点は1200℃程度である。そして鉄は完全に解けて湯になり炉底にたまるようになる。
その状態に対応して炉形に根本的な変化が生じる。風を炉に送り込む下部の送風口(羽口)のところの温度が上がるように、下部(炉床)の直径を小さくする。木炭の燃焼で生じるガス量が膨大になるので、炉の上部から装入されて降下する鉱石と木炭にガスの熱を与えて有効な熱交換がおこない、一酸化炭素による還元が有効に働くように、羽口から炉頂までの炉内長を長くする。こうして融けた鉄を下の口から流し出し、原料の鉱石や木炭を上から入れて連続的に鉄を製造する“高炉”の形が完成する。
(16世紀の高炉は本体高さ6メートル、日産一トン程度)
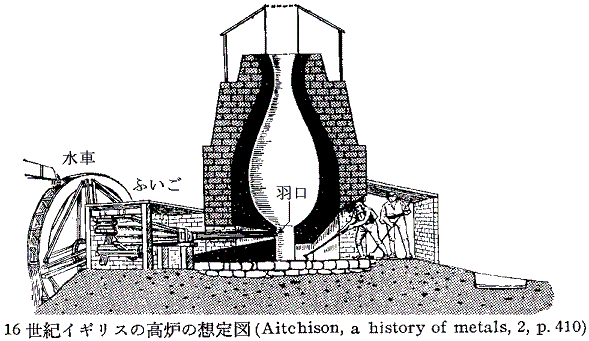
高炉法の発展とともに、厖大な木炭の消費が生じ、森林資源の枯渇による燃料の欠乏が生じるようになった。そのため石炭の利用が16世紀終わり頃から試みられた。しかし石炭の利用には解決すべき問題が多く存在した。
石炭は高温で軟化溶融して空気循環をさまたげ還元反応を停滞させる。そのため乾留してコークスとして利用しなければならない。(cf.イギリスのアブラハム・デービーは1709年にコークスによる製鉄に成功)
木炭と違って石炭は硫黄を含む。硫黄が入ると鉄は脆くなり硫黄の除去が課題になる。硫黄は乾留してコークスにすることによりある程度は除去できるが大きな問題を残した。
コークスは石炭よりも燃えにくい。そのために今まで以上に強力な送風装置が必要になる。より強力な水車、そして蒸気機関の利用が始まる。(cf.ニューコメンの蒸気機関の発明は1712年、ジェームズ・ワットによる蒸気機関の改良は1769年)
石炭と蒸気機関により、高炉は森林や水流から離れて立地できるようになるとともに生産能力が増して産業革命を起こす要因の一つとなった。
木炭と違ってコークスには灰分がある。コークスを使って流れの良いスラッグ成分を作る工夫が必要。不純物の二酸化ケイ素SiO2は石灰石を融材として加え、ケイ酸カルシウムとして取り除くことができる。スラッグが高温で、石灰分が高いときに初めてコークス中の硫黄も十分に除去できることが経験的に解明される。
(1771年、高炉は高さ9メートル、日産4.5トン)
1828年イギリスのジェームス・ニールソンは、炉に送風する空気をあらかじめ熱風炉で加熱して炉内に送り込むことにより、炉内の熱効率を上げる方法を実用化した。ガス会社の技師であった彼は、日常の経験から、空気を予熱して燈火用ガスの燃焼効率を高める実験をしていた。この方法の高炉への適応を考えたのである。それまで高炉が夏季より冬季のほうが成績がよいのは空気が冷たいためと信じられていたが、ニールソンはこれを夏と冬の湿度の差によるもので、湿度が同じなら送風は高温のほうが効率がよいと考え、送風を予熱して燃焼効果を高めることを着想した。この方法によって銑鉄1t生産するときにコークスを2〜2.5t節約できるようになり、瞬く間にスコットランド全域に広まった。
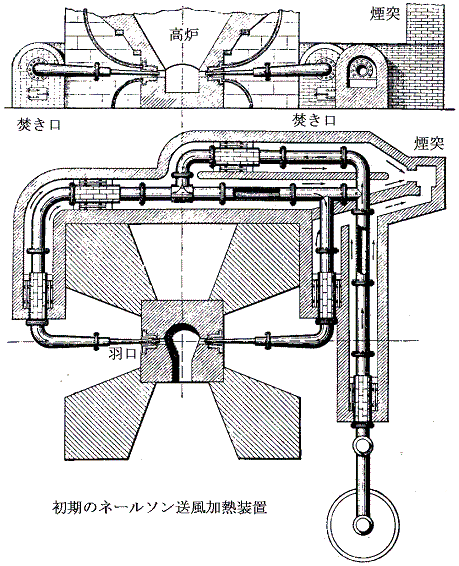
ニールソンは予熱を高温の炉内の管に空気を通すことによって行ったが、1857年E.A.カウパーがれんがの格子積み熱風炉を高炉に適用した。カウパーの熱風炉は送風機から高炉にいたる送風経路のあいだに設置され、風は高炉に入る前にこの熱風炉に送り込まれる。そのなかの強熱された耐火煉瓦の格子組みを通過するあいだに熱を吸収して高温度となる。なお格子組み耐火煉瓦の加熱にはおなじ高炉の廃ガスを利用する。そのために熱風炉が少なくとも2基必要で、一方が空気を熱しているあいだに、他方は高炉の廃ガスで熱され、次の段階での加熱に備える。送風経路を切り替えて2つの熱風炉を交互に使用すれば、高温に熱せられた空気を連続的に高炉に送ることができる。
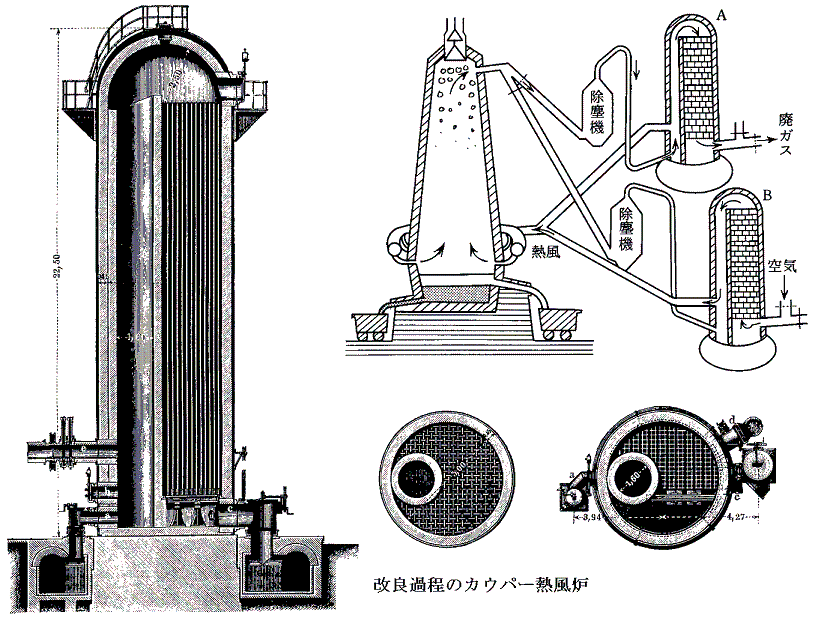
カウパーの熱風炉は、1860年、ミドルスブローの近くにあるオームズビで採用され、絶大な効果を発揮した。、熱風の温度は620℃にも達し、これによって熔銑の出銑量は20%も増加Lた。そして熱風による炉内の高温化により、高炉の直径や高さの大型化が可能になり、生産量を飛躍的に高めた。カウバー熱風炉の改良形は今日でもなお炉の送風予熱装置としてひろく使用されている。(1872年、高炉は高さ24メートル、日産65トン)
高炉法により完全に融けた鉄が連続的に大量に生産できるようになり、まさに鉄の時代が始まったのだが、高炉法が生み出す鉄には多くの問題点があった。その最大の問題点は炉内が高温になり炭素が融解鉄に大量に溶け込むようになったことだ。そのため得られる鉄は炭素分の多い銑鉄で可鍛性のない脆い鉄だった。ただしこの鉄は青銅や銅のように鋳造できるため鋳造鉄工業が発展する。しかし真に有用な鋼にするには炭素分を減らさねばならない。これが鉄工業発展の最大の課題となる。
さらにコークスの使用は不純物のリンPや硫黄Sの混入がさけられず、これらの混入により鉄は脆くなる。そのためリンや硫黄をいかにして取り除くがが大きな課題となった。
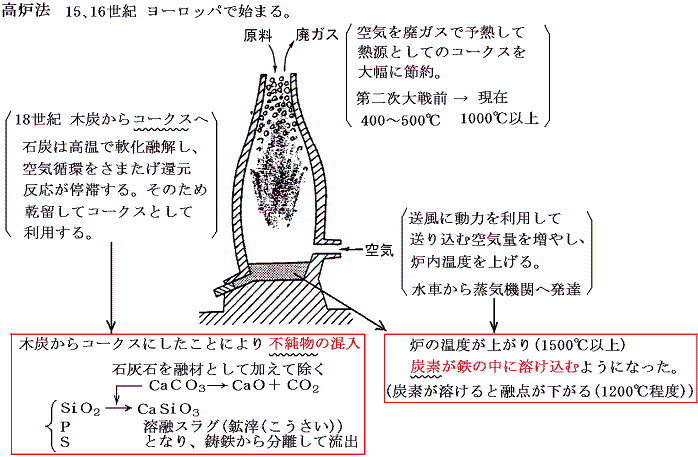
18世紀の初めから鋳鉄の鋳造のために反射炉で鋳鉄を再熔解する技術が工業化された。反射炉とは、火床(ロストル)で石炭を焚き、その火焔を火橋を越えてとなりの熔解室に導く。ここを反射熱で高温にして装入された鋳鉄を溶かすものである。石炭を鋳鉄と接することなく燃焼させて石炭の持つ不純物が鉄に混入することを防ぐ優れたアイディアであった。石炭の火力は反射熱で銑鉄(融点1200℃)を溶かすのに十分なほど強力であったから可能になった。
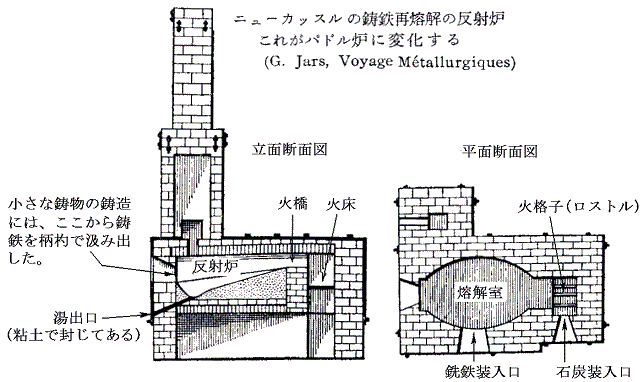
このとき火焔の中に過剰の酸素を送ると、その酸素で鋳鉄中の炭素や不純物のリン・硫黄を燃焼除去することができる。反射炉を炭素含量を減らして鍛鉄(鋼)を製造するために用いたのが1783年にヘンリー・コートが実用化したパドル法である。パドル(paddle)とはボートを漕ぐのに使う櫂(かい)のことである。
鉄は炭素を失うにつれて純度が増し熔融点が高くなり流動性を失う。だんだん粘くなって反応が不均一になり、そのままでは反応が進行しなくなる。そのため反射炉に開けた小さな窓から鉄の棒(パドル)を差し込んでかき回して反応を進行させた。このかき回しの操作をパドリングといい、そのためにパドル法と言われた。人力で銑鉄をこね回し最終的にボール状の錬鉄にして炉から取り出す。こうして得られた塊状の鉄には滓が含まれるので、高温下で圧伸・圧延して滓を絞り出して製品とした。
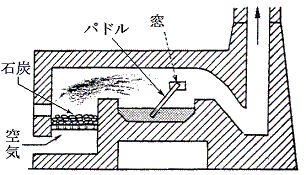
石炭と銑鉄とは接触しないので石炭を燃料として炭素除去の製錬が可能になったのだが、上記の燃焼方法の反射炉では炭素成分の少ない鉄(融点1400℃以上)を完全な融解状態にするほどの高温を得ることができなかったのでパドリングが必要だったのだ。ただし、この方法は1回の作業に10数時間を要し、しかも得られる鋼の量は少ないため大規模生産には向かなかった。この課題を解決して鋼の大量生産を可能にしたのが次に述べるベッセマーの転炉である。
イギリス人ヘンリ・ベッセマーは銑鉄と過剰空気の反応を詳しく調べて、熔けた銑鉄にそのまま空気を吹き込めば、燃料の熱源なしに、銑鉄中の炭素やケイ素を燃焼除去できることを発見した。そして、その着想を用いた転炉の開発に取りかかった。転炉(converter)とは銑鉄を鋼に転化convertする炉という意味である。
ベッセマーが最初に実験に使用したのは固定式垂直形転炉で、1855年セント・パンクラスのバクスター・ハウスにある彼のロンドン工場に設けられた(下図)。この炉は小さい円筒形で、内部の高さ約4フィート(1.2m)、空気は底部にある6本の“羽口”を通して水平に炉底へ吹き込まれる。送風の圧力は1平方インチあたり10〜15ポンド(約0.7〜1kg/cm2)銑鉄はキュポラで再熔解したのち、その可動式出銑樋(とい)から直接転炉に流し込む。製鋼が完了すれぱ、転炉底部の湯出し口を開いて熔鋼を流出させ、浅い可動式のなべ(受け器)に受ける。
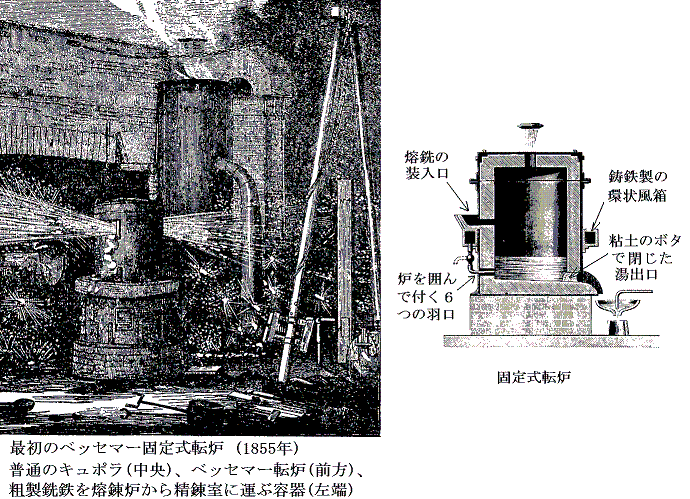
固定式転炉の欠点は、熔銑装入中も熔鋼湯出し中も送風をつづげなければならないため、熱の損失が大きいことであった。この対策はまもなくベッセマー自身が見つけだした。それは転炉を軸上にのせて支持し、前後に自由に転倒できるようにする方法であり、こうすれば、熔銑装入時に“羽口"を熔金面の上方に保つことがでぎる。熔鋼を湯出しするときも同じことができるから、ともに送風を中止して作業することが可能となる。こうしてできたベッセマーの可動式(傾注式)転炉は、シュフィールドにある彼自身の所有する製鋼工場で最初に操業されることになった。この新型転炉は、今目にいたるまで、実質上当時とかわらぬ形で存続している。(下図)。
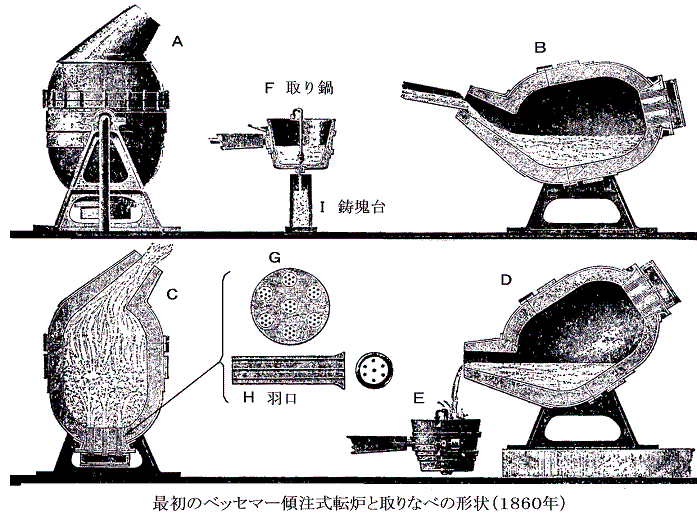
(A)は装入作業開始前の転炉が立っている状態。取りなべ(F)で運んできた熔銑を装入するときは(B)のように炉を水平に倒す。装入完了ととも送風を開始して転炉を起こしていく。風は炉底外部の風箱から“羽口"に入り、炉内に吹き込まれる。(G)は炉底部の水平断面、(H)は“羽口"の形状を示す。(C)は送風中の転炉の状態で、風は熔金をおしのけて上昇し、炭素やケイ素の燃焼過程が起こる。最初はケイ素が比較的静かに燃え酸化物となって浮上、次いで炭素が激しい爆発をともないながら燃えCOとなって噴出する。炭素成分を4%から1%程度まで減少させる。炭素やケイ素の燃焼熱が溶融した鉄を沸騰(1500〜1600℃)させ反応が一気(僅か20分程度)に達成される。工程の終りにはふたたび炉を倒して(D)、鋼を取りなべ(E)に受け、鋳塊台(I)に注ぎ込む。鋼は完全に融解しているので、不純物は滓となって表面に浮上するかガスとなって出て行き、純粋な鋼塊を作ることができる。
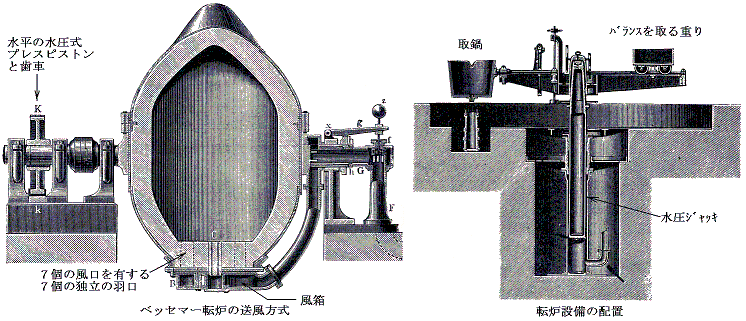
転炉法は燃料を用いることなく、きわめて短時間で多量の鋼をつくることができる非常に効率の良い製鋼法で、鋼の大量生産を可能にした。急速にヨーロッパ、アメリカに普及していき、まさに鋼の時代が始まった。
ベッセマーの方法は革新的で偉大な方法であったが、欧州産の大部分の鉱石(リンや硫黄を含む)では良質の鋼は得られなかった。良質の鋼を得るには低リン、低硫黄の高品位鉱石(アメリカ、旧ソ連、北欧)が必要であった。
なぜリンPや硫黄Sを含むと旨くいかないかと言うと、すべての化学反応は可逆反応だからである。反応が一方方向へ進んでいくように見えるのは、反応物、生成物が持つ熱エネルギーに比べて、反応の活性化エネルギーや反応熱の段差が十分に大きいからである。ところが温度が高くなり、分子のもつ熱エネルギーが大きくなると、反応熱の段差や活性化エネルギーの山を飛び越えて反応物側→生成物側へ飛び越える分子と、生成物側→反応物側へ飛び越える分子の数はほぼ等しくなり、生成物が一方の側に偏ると言うことが無くなる。
前述の反射炉を用いる方法では炉内温度は1300℃程度の比較的低温だったのでリンも硫黄も燃えて取り除かれたのだが、ベッセマー転炉のような1500〜1600℃という高温になると完全に一方へ反応が進まず、リンや硫黄が熔鉄の中に残ってしまうのである。
実際どの程度の温度で逆の反応が目につくようになるかは、各化学反応の反応熱段差と活性化エネルギーの山の高さに依存し、元素により異なるが、リンの場合1500〜1600℃という温度になると、一部がハッキリと鉄の中にのこり、鋼を脆い劣悪なものにした。
脱リンの困難は、従来の耐火材としてケイ酸を主成分とする「酸性」の耐火材しか無かったからである。それまではベッセマーの転炉法でも、シーメンスとマルチンの平炉法(6.で説明)でも、ケイ酸成分の酸性耐火材を炉材として使用していたが、それでは銑鉄のリンを除去できず、高炉で低リン鉄鉱石から製造した低リン銑鉄にしか適用できなかった。大部分の鉄鉱石はリンを含有しているので、転炉法も平炉法も適用範囲が限られていた。高名な製鉄家たちが脱リン法の開発に知恵を絞ったが成功できなかった。
イギリスの製鉄発明家ギルクリスト・トーマスは早く父に死なれ、一家を支えるために17歳で裁判所の書記に就職した。しかし好学の念やみがたく、夜学に通い、家に化学実験室をつくり、学問を捨てなかった。夜学の先生チャロナーが「転炉法で脱リンに成功すれば運をつかむだろう」と語るのを聞いて、この問題の解決に情熱を燃やした。
トーマスは従来の研究を検討し、塩基性の石灰が脱リンの唯一の鍵(かぎ)であることを確信した。銑鉄中のケイ素が酸化されて浮上しスラグになるが、同じく酸化されてスラグに入るリンは還元されて鋼に戻ってしまう。このとき、スラグに石灰を添加すると、塩基性の石灰と酸性のケイ酸は結合するが、過剰の石灰を加えると酸化されたリン(酸化リンも酸性酸化物)ともしっかり結合して安定した化合物をつくりスラグに取り込まれる。そして、リンはもはや鋼に戻らない。
しかし従来のように酸性のケイ酸の耐火物であると、スラグ中の石灰は炉壁のケイ酸とも激しく反応して炉壁がたちまち破壊してしまう。そのため炉壁に石灰石、マグネサイト、ドロマイトなどから製造した塩基性の耐火材を使用する必要があった。しかし、それらの物質は脆くてすぐボロボロになってしまう。それらから耐久性のある耐火材をつくることはきわめて困難であった。
彼はドロマイト(炭酸カルシウムの鉱石。カルシウムCaの一部がマグネシウムMgによって置換されている。方解石より硬く、酸に溶けにくい。)を従来以上の高温で焼いてクリンカーにし、石炭タールを接着剤に使用してこの難問を解決した。(1879年)こうして塩基性耐火材が工業界に誕生し、塩基性転炉法が確立した。
ベッセマーの酸性法はベッセマー法とよばれ、塩基性法はトーマス法とよばれることになった。塩基性法は次に述べる平炉法にも適用され、溶鋼法は含リン銑鉄にも適用され大発展を遂げた。
ドイツ人ファーベル・デュ・フォールは石炭焚きではなくて、高炉の炉頂ガスを回収してパドル炉を加熱する着想を工業化した。また、パドル炉の廃ガスで燃焼用空気を予熱して一層高い反応温度を得ることを工夫した。さらに1840年には安い泥炭をガスに変えて冶金燃料とするガス発生炉を着想し工業化した。
平炉法は1856年ドイツから帰化したイギリス人フレデリック・シーメンスにより考案された。これはパドル法と同様に燃料を用い、反射炉熔解室で鉄の製錬をおこなうが、大きく改良されたところは、炉の廃ガスを用いて加熱した煉瓦の格子積み熱風炉で燃料ガスと空気をあらかじめ予熱しておいて燃焼させる蓄熱室切替法にある(前述のカウパーはシーメンスの協力者で、この原理を高炉に応用したのがカウパーの熱風炉である)。予熱の結果1600℃以上の高温が得られ、溶融状態で脱炭素精錬が可能になった。燃料は石炭をガス化した気体燃料を用いる。
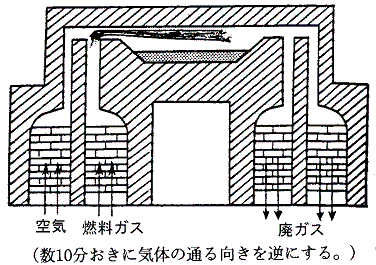
ほぼ同時期にフランスのマルチン親子により、平炉を用いて(くず鉄+銑鉄)による製鋼が試みられた(1865)。このため平炉製鋼法をシーメンズ‐マルチン法ともよぶ。
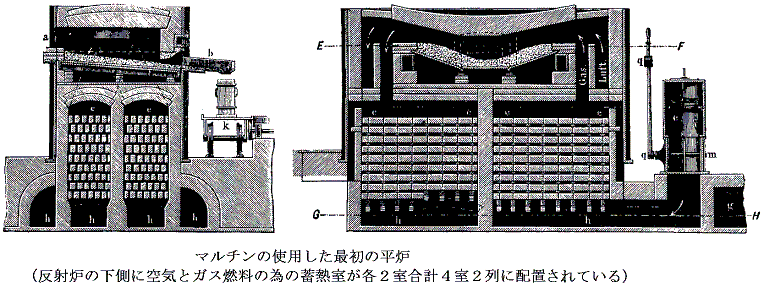
当時の空気吹きの転炉製鋼法では銑鉄の成分に各種の制約があった。転炉では銑鉄に含まれるCとともにP、S、Siも高温発生のための燃焼反応の燃料になるので、酸性炉材のベッセマー転炉ではPやSが少なく、Siが多いものを、塩基性炉材のトーマス転炉ではPやSが多くて、Siの少ない鉱石を必要とした。しかし高温にするために別途燃料を用いる平炉法ではそれらの制約から解放された。
転炉と同じように塩基性炉床の平炉が確立されてからは石灰の多い塩基性滓によっる脱リン・脱硫黄も容易になり、幅広い組成の銑鉄の精錬が可能になった。さらに溶銑、冷銑、くず鉄の配合割合を自由に調節することが可能で、広範で優れた成品品種の生産ができるため製鋼法の主流を占めるようになり1955年には世界の粗鋼の80%以上を生産するようになった。
炉容量の拡大、酸素製鋼の採用、燃焼バーナーなどの改良による燃焼効率の向上、天井、炉床耐火物の開発、改良による耐火物原単位の減少、さらに各種計測による操業の自動化などにより発展を続けたが、1950年代後半の酸素上吹き転炉の開発、工業化によりしだいに押され、旧ソ連地域、中国、アメリカなどでは操業されているもののその割合は激減し、日本では1977年(昭和52)に姿を消した。
第二次世界大戦後
〔1〕鉄鉱石の整粒、粉鉱の焼結・ペレット化(鉄鉱石と石灰石を焼き固める)などの鉱石事前処理技術の進化。
次のホームページを参照されたしhttp://www.nipponsteel.com/company/publications/monthly-nsc/pdf/2004_3_137_05_08.pdf
[2]高炉を密閉して炉頂圧力を高めて、上昇ガススピードを遅くする。そして原料と還元ガスとの接触時間を長くしコークス量を節約する。
〔3〕送風の酸素富化、熱風温度の高温化(1200〜1300℃)。
[4]水蒸気添加による空気中の水分調節。重油、天然ガス、微粉炭燃料の熱風への吹込み。
このあたりはここを参照されたしhttp://www.nipponsteel.com/company/publications/monthly-nsc/pdf/2004_1_2_135_11_14.pdf
〔5〕高炉内反応の解析に基づく管理技術の発達
等々の技術革新と供に高炉の大型化が進む。炉の形は鉄の熔融物が安定して落下するように経験的にきめられているが、最新の高炉は炉本体の高さが40m、炉底直径は14mにもなり、全体の高さは125mに達する。
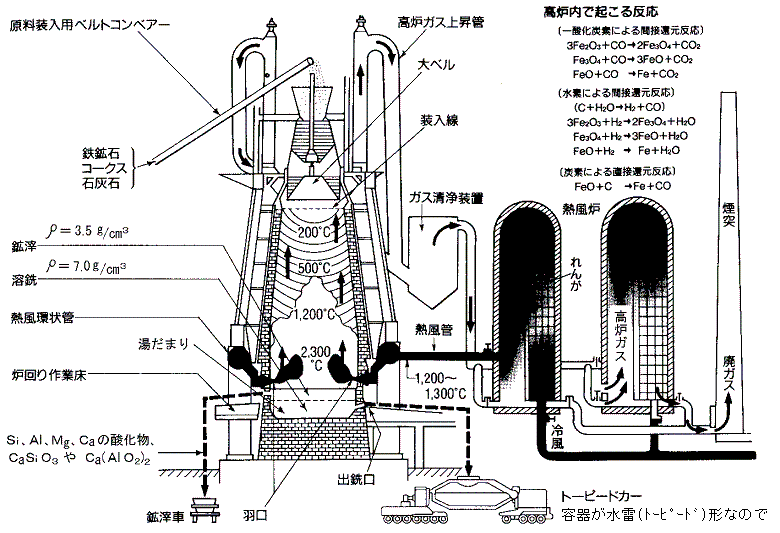
高炉は一度火がつけられると、通常は10年間くらい休むことなく連続操業される。最新鋭の高炉ではだいたい1日に1万5000tの鉄鉱石と5000tのコークスから、約1万tの銑鉄が作られる。その際 [鉱石(2000t)+コークス(900t)+石灰石(600t)+熱風(3600t)] から [銑鉄(1000t)+スラグ(700t)+廃ガス(5300t)+炉塵(100t)]が生じる。
鉄鉱石とコークスは交互に60cm厚の層をなすように積み重ねられている。反応は間断なく進み、鉄鉱石とコークスの層は1時間に3mの割合でずり下がっていき、だいたい装入から8時間後に銑鉄となる。
操業中に突然停止させた炉の解体調査(1968〜1972年)から、炉内の様子が下図のようなものであることが解ってきた。融着帯というものが存在し、その形状が高炉の操業状態と深く関わることが解ってきた。
融着帯の上にある塊状帯では鉱石もコークスも原型をとどめており、下から上がってきた一酸化炭素ガスによる間接還元が進行中である。また熱風中に含まれる水分が分解してできる水素ガスによる還元反応も進行している。
“融着帯”では、鉱石と鉱石が半分融けた状態で、お互いに融着しあって板状につながっている。そこはガスが通り抜けられないので、ガスはコークス層をすり抜けて上に逃げる。そのため融着帯の形が高炉の生産性を大きく左右する。
融着帯の下の滴下帯では鉱石がどんどん融解して滴となって豪雨のようにコークスの間を流れ落ちていく。そこでは、液状の酸化鉄とコークスの炭素が直接反応する直接還元が進行している。
その下に円錐状の“デッドマン”(炉芯コークス)と言われる部分がある。送風羽口に近い所のコークスはガス化して消滅するが、炉の中央部のコークスは文字通りほとんど動かないで静止している。燃え尽きるまでに約1ヶ月程度かかる。この部分は高炉内の熱変動を緩和する蓄熱材としての働きと、そのまわりに滞留するコークス粉が滴下する鉄やスラグと接触して消失する場を与える。デッドマンは溶けた銑鉄の中央部に浮かぶ浮島のようなもので、その浮遊位置や大きさ・形状が高炉の操業状態に大きく影響する。
最終的に溶融した鉄が炉内を滴下し、最下層の湯だまりにたまり、出銑口から取り出される。
鉄鉱石中に含まれる不純物(ケイ素、アルミニウム、マグネシウム、カルシウムなどの酸化物)も一酸化炭素や水素による還元反応をうけながら溶融して、最後に熔融した鉄の上に鉱滓(スラグ)として浮かぶ。鉱滓は密度が小さく鉄の上に分離して浮かんでおり、鉱滓口から取り出される。
融着帯とデッドマン(炉芯コークス層)について興味ある記述が以下のホームページにある。
http://www.nipponsteel.com/company/publications/monthly-nsc/pdf/2004_3_136_11_14.pdf
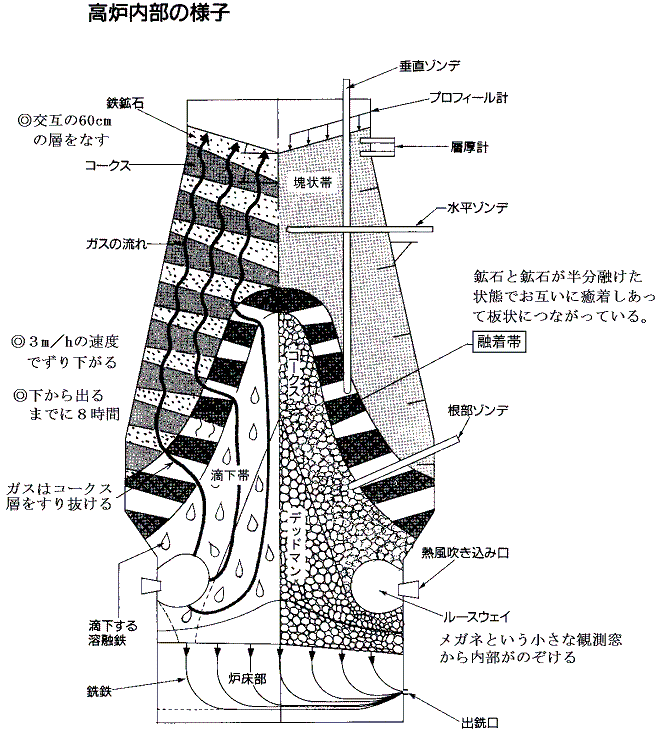
高炉の操業で最も重要な項目はコークスの比率であり、その燃料代である。1tの銑鉄を生産するのに必要なコークス量は19世紀初頭で30t、20世紀初頭で3t、現在の日本最新鋭高炉で0.5tと、どんどん効率化されてきた。
技術者はコークス比率を下げることに腐心するが、下手に下げると、鉱石がおおくなりガスの通りが悪くなり温度が下がり過ぎて大不調になる。不純物の残量が増えて困ることもある。原料の鉱石や石炭は、世界中から輸入されている。何十種類もの銘柄があり、それぞれ品質が違う。それをどう混合するかが大きな問題だ。層に積み上げていくときどういった形状を取らせるかも問題である。積み上げたあとのずり下がりで層が崩れていくが、その崩れ方がコークスの装入のされ方によって違ってくるからだ。
高炉は、原料の質や構成比が変わるなどして、操業条件がよく変化する。銑鉄の温度が下がったりする不調が結構ひんぱんに起こる。ちょっと原料の入れ方を変えねばならないという不調なら1週間に1回くらいは起こる。調子がなかなか元に戻らなくて1週間から10日くらい調整を続けなければならない大不調が半年に1回くらいは起こる。
その時、吹き込む熱風の温度をどう調整するか、熱風に含ませる水分(水素還元反応に関係)の調整はどうするか、など沢山の調整項目がある。それらは1970年代までは現場のベテラン作業長の経験と勘に頼っていた。
しかし、今日では解体調査から得られたデータや今まで積み重ねられてきた経験と勘による厖大な知識が、理論的解析の結果と供にコンピュータープログラムの中に取り込まれている。そして、コンピューター制御された人口知能システムでコントロールされている。
従来の空気底吹転炉では耐火物の種類と発熱源に対応して溶銑成分に制限があり、空気吹きのため窒素による熱損失と同時に、窒素が溶鋼に吸収され、鋼の性質に悪影響を及ぼす。これが、転炉が生産性が高く、省エネルギーの製鋼炉でありながら平炉に圧倒された大きな原因である。
1895年リンデの空気液化装置の発明以後純粋酸素を安く大量に製造できるようになった。窒素の沸点は−195.8℃で酸素の−183℃より低く、最初に窒素が蒸発してくる。そのため残った液体空気中の酸素濃度が高まる。窒素と酸素の沸点の違いを利用した液体空気の分留により酸素を得ることができる(液体空気から液体酸素と窒素ガスを分離する装置については「冷凍・低温技術の歴史」1.(4)1902年を参照)。
工業的に純粋酸素を安く大量に利用できるようになったことで酸素富化が行われ、窒素の問題は改善されたが、脱リンによる溶鋼中の酸素が高くなる欠点は残った。また酸素富化による羽口溶損の点で富化に限界があった。以下その改良の工夫である。(以下小学館「日本大百科事典」より)
【純酸素上吹転炉】
炉体の中心線上の炉口よりランス(酸素を送り込むパイプ"lance槍”)を熔銑直上に降ろし、純酸素ガスを吹き付け吹錬する。炉を回転させるときは,ランスを上方に引き上げる。炉底は羽口がなく炉腹と一体で、炉腹上部に出鋼孔がある。耐火物は塩基性で、マグネシア、タールドロマイト、さらに近年はマグカーボンれんがが用いられている。酸素上吹きはベッセマーの特許にもみられるが、当時は酸素が高価で実現しなかった。その後リンデ‐フレンケル法により高純度の酸素が安価になり製鋼への利用も可能になった。
純酸素上吹転炉法はドイツのデューラーR. Durrerにより1946年スイスで半工業化に成功、その後オーストリアのリンツとドナビッツで工業化された(1953)。LD法という名称はこれらの地名の頭文字によるともいわれている。本法は低窒素鋼が容易に得られ、廃ガスへの熱損失が少なく熱効率が高く、熔銑成分にとくに制約がなく、また30%程度のくず鉄の配合も可能である、など非常に大きな特徴をもつ。そのため第二次世界大戦後の復興期の日本、ヨーロッパで急速に発展した。
LD 転炉の特徴は空気の代りに純酸素ガスで精錬することであるため,極端な低窒素鋼が得られる。できる鋼は従来の底吹転炉に比べて低リン,低酸素であり,鋼質は平炉鋼よりも優れている。LD
法は品質のみならず,原料選択の自由度,コスト,生産性の面でも平炉法よりも優れていたため,世界中で急速に平炉法にとって代わった。日本においては,1957年に最初の
LD 転炉が稼働して以来,高度成長期にあったため転炉の建設が相次ぎ,世界に例をみないほど急速に生産量を増していった。また
LD 転炉技術は日本で大きく成長,発展した。日本が一流の製鉄国になるためにも
LD 法が果たした役割は大きい。
高リン銑を産するヨーロッパでは、酸素とともに粉状の生石灰を吹き付け脱リンに有効なスラグの生成を促進させるLD‐AC法(OLP‐OCP)、またスラグと金属間の反応を促進させるため炉体を傾斜あるいは横型として回転させるカルドー法、ローター法なども開発された。
【純酸素底吹転炉】
溶鋼の攪拌(かくはん)が非常によく精錬反応が促進される底吹法では、羽口、炉底耐火物の損耗という問題点があり、純酸素の導入が困難であったが、1965年カナダで炭化水素系ガスを同時に吹き込み、この分解の吸熱冷却を利用する二重管羽口が開発された。炉底には同心二重管からなる複数個の羽口が取りつけられている。羽口の内管から純酸素ガスを,内管と外管の間隙からプロパンなどの炭化水素ガスを吹き込む。羽口先端部における炭化水素の分解熱により羽口を冷却し,保護している。生石灰を粉末にし,酸素ガスに懸濁して羽口から添加する。
この羽口を利用することにより旧西ドイツで純酸素底吹転炉法(OBM-oxygen bottomblowing method)の工業化に成功した(1968)。アメリカではUSスチール社が開発し、Q‐BOPと名づけた。フランスでは冷却剤に液体燃料を使うLWS法が開発された。
底吹きでは、スラグ中の酸化鉄が少なく、鋼の歩留り向上、溶鋼中の酸素の低減という利点があるが、水素の増加という欠点もある。
【上下吹複合吹錬転炉】
1970年代後半になって,底吹転炉の優れた冶金特性が明らかにされた。その結果,底吹転炉に比較して少ないガス量を,上吹転炉の底から吹き込むことによって,上吹転炉の特性が顕著に改善されることが期待された。底吹きと上吹きの利点の両方を生かすため近年急速に開発されてきた転炉で、底吹き羽口の冷却にアルゴンや炭酸ガスを用いる形式のものもある。
以上の純酸素を用いる製鋼法は塩基性酸素製鋼法(Basic Oxygen Process=BOP)と総称される。転炉の容量で400トンに近いものもあり、廃ガスの回収装置や種々の感知装置を取り付けコンピュータ制御を行うなどし、現在の粗鋼の70%近くを生産する。
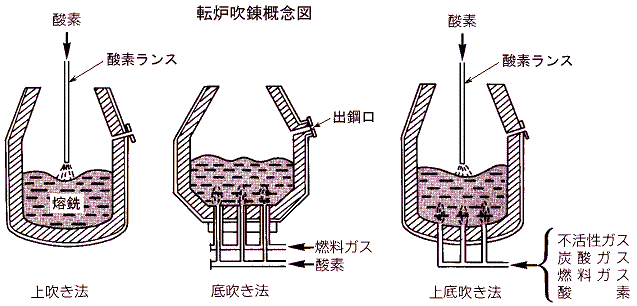
転炉の技術については以下のホームページを参照されたし。
http://www.nipponsteel.com/company/publications/monthly-nsc/pdf/2004_5_138_11_14.pdf
http://www.nipponsteel.com/company/publications/monthly-nsc/pdf/2004_6_139_13_16.pdf
[2023年9月15日 追記引用] 拡大版
製鉄業は今日新しい時代を迎えています。高炉法による製鉄は大量の石炭を消費し、二酸化炭素を大量に放出します。地球温暖化の脅威が現実のものとなる今日、鉄の生産消費には大幅の削減が必要とされるのでしょう。
1.重松栄一著「化学」民衆社P170〜178 最初に製鉄史を概観するには最適。
2.立花隆著「電脳進化論」朝日新聞社P55〜66
熔鉱炉の本質が明解に説明されていて非常に面白い。
3.相田洋、NHK取材班荒井岳夫「NHKスペシャル新・電子立国 5驚異の巨大システム」日本放送協会P157〜380
巨大製鉄所のコンピューター化の詳細が当事者のインタビュー記事とともに詳細に展開されていて非常に面白い。
4.中沢護人著「鋼の時代」岩波
新書版だが日本語の基本的文献
5.チャールズ・ジョセフ・シンガー、他著「技術の歴史9-鋼鉄の時代(上)」筑摩書房P43〜57
6.ルードウィヒ・ベック著、中沢護人訳「鉄の歴史」たたら書房
大きな図書館には必ずある名高い大著(全19巻)。厖大故に必要なところだけ拾い読みする本。
[参考書の追記]
新日本製鐵編著「カラー図解 鉄と鉄鋼がわかる本」日本実業出版社(2004年刊)
鉄と鉄鋼を理解するのに最適。とくに工業高校生に勧めます。
[2019年4月追記]
かって八幡製鉄所にお勤めされていた方から、日本の近代製鉄発展史について興味深い資料を教えていただきましたので紹介します。
https://my.ebook5.net/meijiindustrialrevolution/DA9diZ/
日本の近代製鉄の黎明期の状況が良く解ります。ただ上記のURLでは資料の拡大率に制限があり残念なのですが、その方から源本も送っていただいたのです。そのときの私どものお礼のメールと、そのとき送っていただいた写真を別ファイルで紹介します。とても興味深い写真です。