このページを印刷される方はこちらのバージョンをご利用下さい。図がより精細・鮮明に印刷できます。
田中航著「蒸気船」毎日新聞社刊 より引用
以下の内容は下記の本から、ほぼそのまま引用しました。ただし、解りやすいように章・節を付け、且つ少し改竄しています。
田中航(紀之)著「蒸気船」毎日新聞社(1977年刊)
これは技術史・社会史の本として極めて面白い。著者は蒸気機関の事が本当に良く解っている方の様ですね。ここではエンジンに関係するところだけ引用しましたが、それ以外も非常に面白いので読まれる事を是非勧めます。
1.蒸気機関(P101〜110)
(1)形式の発展
1.ビーム・エンジン
ごく初期の蒸気船に使用された主機関には、ビーム・エンジンと呼ばれるものが多かった。例えぽフルトンのクラーモソト号もそれで、このタイプのエンジンは、以後伝統的にアメリカの河蒸気に引継がれることになる。
ニューコメソが初めて完成した蒸気機関には、ビームと呼ぱれるシーソー状の、長大な構造物がピストン・ロッドの末端に連絡されていた。彼のエンジンはシリンダー内部の蒸気が凝縮すると、大気圧でピストンが押し下げられ、その運動がビームを仲介として排水ポソプに伝えられる、という単純たものだった。また、ワットはニューコメンの大気圧機関を大幅に改良したが、彼のエンジンもまた最初のうちは、大きなビームのついたものであった。
彼らの蒸気機関は本来、陸上使用のため製作されたものだから、シリンダーの上の方に大きなビームがあっても、それ程の不都合はたい。しかしこれを船に備え付けるとなると、空問的にも制約があり、しかも大きく重いビームを上の方に据えることになるので、安定上も好ましくない。この場合はビームの一端の上下運動を、伝達装置を介してクランクに伝え、ここで回転運動に変えて外車軸を回そうというのが、ビーム・エンジンの船舶への応用である。
2.サイド・レバー・エンジン
これを船舶の外車回転にもっと適するように故良したのが、サイド・レバー・エンジンと呼ばれるタイプのものである。日本の古い専門書では側挺(ソクテイ)機関という名で呼ぱれている。要するに垂直に立てられたシリンダーの下の方、エンジンの基部付近にビームを据えたもので、一本のシリンダーを挾んで対称的に二本のピームがあり、この場合上の方につけた本来のビームと区別するため、サイド.レバーと呼んだ。
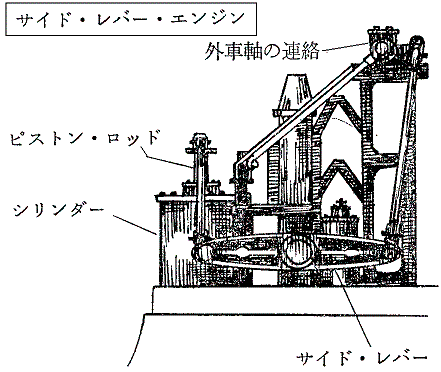
前記コメット号のエンジンは、すでにこのタイプのものになっていて、この改良は主としてイギリス人技術者により、清力的に進められた。19世紀半ぱ頃、外車蒸気船の成長期には多くの船がこの種の主機関をつけていて、一時期、船舶用蒸気機関の主流となっていた。
これはまた初期の蒸気機関の傑作ともいわれ、たんに船体推進用の原動力として働くばかりでなく、支柱や側面には彫刻、彩色などを施して、鉄と黄鋼の金属美を発揮させ特に大型蒸気船のそれは、芸術品的観賞価値のあるものが多かった。蒸気力利用といった純然たる科学技術の分野にも、現代人にはまったく余計たものにしか思えない、中世的な独得の美観が発揮されていたものとみえる。
それは総体に機械としても良くバランスのとれたものが多く、故障が少く修理も容易で、当時のものとしては経済的だったという。またビームが下にあるので、船そのものの安定性が良く、機関室の上の方にビームのための大きな空問をとられる不具合を除くことができた。しかし欠点もある。それは、長いサイド・レバーが頑張っているために、ピームを持たない蒸気機関に比べると、主機関の占める容積が大きくなる点が一つ。このことは貨物倉の容積を少くし、乗組員や船客の居住区をせばめることを意味する。例えば500馬力の蒸気機関どうしを比較したとき、サイド・レバー・タイプは他のものより6m以上も、エンジン・ルームの一辺を大きくしなければ納まらたかったとのことだ。また重いことも大きな欠点の一つで、これまた貨物や燃料の積載重量が減るという、好ましくない結果をまねく。船は原則として、同じ出力なら主機関は重さはより軽く、容積も小さいに越したことはたい。やはり500馬力の蒸気機関を考えたとき、サイド・レバー・タイプは他のものよりも、エンジン自身の重さが100トソ以上も重くなる、と言われていた。しかし外船用の蒸気機関としてはしぽらくの問これ以上のものが現われたかったのでかなり大型のものまで製作されるようになった。
3.直動機関
長大なビームやサイド・レバーを使わないで、外車軸を回そうというのが直動機関と呼ばれるもの。
このタイプはピストン・ロッドを直接コネクティング・ロッドにつないで、それがクランクを動かして回転運動を得る仕組みで、ピストンとクランクとの問にビームは介在したい。
これには大別して、オッシレイティング・エンジン(揺動機関)とダイヤゴナル・エンジン(斜動機関)との二種類があった。オッシレイティング・エンジンは、垂直方向に立てて据えたシリンダー、が運転時、蒸気供給用のパイプを中心にして、首を振るようた運動をするのでこの名が出た。
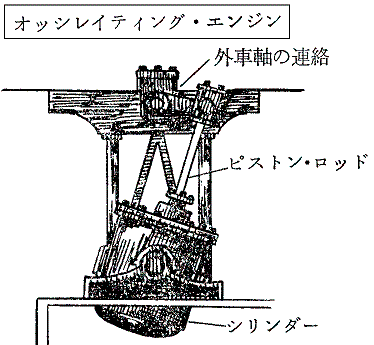
これは外車船用として最も優れたエンジンと言われていた。船底付近にシリンダーを据え、そこから上に延びたピストン・ロッドがクランクを介して、外車軸を回す仕掛けで、船体を横に貫く外車軸の下にエンジンをコンパクトにまとめることができるので、重量が外車用蒸気機関のうちでは最も軽く、容積も小さくすることができた。これをつけた船で有名なのは、後出のグレート・イースタン号がある。
ダイヤゴナル・エンジンとはシリンダーをわざと斜めに寝かせて配置したもので、斜め上方に延びたピストンロッド、がクランクを介して、直接外車軸を回転させる仕組みである。これも外車船には多く使用された蒸気機関の一種だった。
4.倒置堅型式蒸気機関
シリンダーが垂直に立ててあるのを竪型(タテガタ)蒸気機関という。ワットが完成したのはもちろんこれであり、その場合シリンダが下、ピストン・ロッドが上にあった。これまでに出てきた外車船に用いられた各種の蒸気機関も、ほとんどのものがシリンダーとピストンとは基本的にはこの関係にあった。ところが19世紀の最後の四半世紀にたると、もっと大馬力で回転数のあがる蒸気機関に対する要望が強くなり、シリンダーとピストン・ロッドの上下関係を、従来のものとは逆にしたのが開発された。ワット時代の堅型機関に対してこれを倒置堅型式蒸気機関と呼び、以後はこれが主流になった。却ちこのタイプではシリンダー、が上にあり、ピストン・ロツドやクランク装置は下にある。
倒置竪型式は据付けや修理が容易で、運転による部品の消耗も比較的少く、ストロークを大きくできる。しかもその結果、以前よりも大馬力の出力が期待でき回転数を上げられるという、結構ずくめの発明だったそうだ。
(2)多段膨張式往復動蒸気機関
これまでにごく初期の実験的蒸気船の主機関は、たった一本のシリンダーとピストンから成り立っていたと述べてきた。これをシングル・シリンダー・エンジン(または単汽筒汽機)、あるいはシンプル・エンジンと称する。要するに最も単純な蒸気機関という意味だ。この場合にはピストンを動かした蒸気は、まだ膨張の余力が充分あるのに、空中に放出されるか、あるいはもっとましな場合でも、コンデソサー(復水器)に導かれて水にかえってしまうのがおちである。せっかく作った蒸気もただ一回の仕事しかしない。これでは燃料.がいかにも不経済なので、これを大きさの違う何本かのシリンダーへ順に送り込んで、蒸気の持つ膨張力をトコトン利用してやろうと考えた頭の良い人物がいた。それはジョン・エルダーという、グラスゴー生れのイギリス人技術者だった。
彼は当時有名だったネピア造船所で、造機技術者として働くうちに、シングル・シリンダーの改良を思いたった。彼の作ったものは大小二本のシリンダーをもち、蒸気を先ず小型のシリンダー(これを高圧汽筒という)で働かせ、次に大型のシリンダー(低圧汽筒)に入れここでもひと仕事させ、その後でコンデソサーに帰そうという、言わば二段膨張式の蒸気機関である。このタイプを二連成エンジンと称し、シリンダーの数が増えるにつれて三連成、四連成と名付けられる。
連成エンジンのアイディアはもっと古くからあったそうだが、実用に耐えるものを完成して船舶に応用したのは、このエルダーが最初で、時に彼は29歳の若さだった。彼は1853年にその特許をとった。翌年、これを装備した蒸気船を走らせて、シングル・シリンダーのものよりも、同一馬力ならば燃料消費が二割以上少いことを証明してみせた。
これに目をつけたイギリスのある船会社は、それまでもっていたシソグル・シリンダー船を数隻、エルダーの二連成エンジンに改装して、自社の年間石炭消費量を約半分に減らすことができた、という話が伝わっている。
さらに1874年になると、A.C.カークによって実用的な三連成機関が完成された。それは高圧、中圧、低圧の三本のシリンダーから成り立っている。蒸気船会社は争ってこの大出力の蒸気機関を採用し始めた。その後19世紀末には、四連成機関も製作された。この辺でシリンダーとピストンを用いる往復動蒸気機関、いわゆるレシプロケイティング・エンジン(略しくレシプロ・エンジン)は、ひとまず発達の極限に達した。
このようた蒸気機関の発達は当然、外車推進からもっと効率の良いスクリュー推進への飛躍を促すものであり、また逆に外車よりも高速で回転してこそ初めてその真価を発揮するという、スクリューの性質が理解されてきたので、そんな要望に応えるべく蒸気機関もどんどん発達したとも言える。(スクリュー推進開発の具体的経緯についての部分は省略)
(3)ボイラーの発達
1.箱型ボイラー
蒸気機関は燃料(石炭でも重油でもよい)を燃やして蒸気を作るボイラーと、その蒸気を使って機械的仕事をするエンジンとの、二つの主要部分から成り立っている。従ってボイラーとエンジンとは、不可分の関係にあるわけで、一方の進歩は当然他方の発達を促し、またその逆の関係もあった。
ごく初期の船舶用蒸気機関は、はたはだ幼稚なシングル・シリンダー・タイプだったので、それ程高い蒸気圧を必要としたかったから、ボイラーもまた鉄板を張合わせて作った四角た箱状のものか、あるいは銅の風呂釜のようなものでこと足りていた。どちらかか言えば、銅製の方が多く用いられていたようだ。鉄よりも単価の高い銅が、好んで用いられたのは、鉄に比べて工作が容易なのと、海水を入れた場合に鉄よりも腐蝕に耐えて長もちするからだ。もっとひどいのになると木の桶のポイラーというのもあった。
もう少し銅製ボイラーの話を続けると、19世紀初めの頃のことだが、約700総トソで120馬力の蒸気機関をつけた船のボイラーを、銅にした場合は同じものを鉄で作るのに比べてコストは三倍となるが、耐用期間もまた三倍あり、しかもそれを解体したときに鉄製はただ同然であるが、銅のスクラップは新品ボイラー製作費の半分くらいの値になった、というデータがあるそうだ。結果としては随分経済的だ。だから銅の方が好まれた。
また当時の技術では、鉄よりも銅の方が大きた板を作り易かったので、これで作れぱ火の当る部分を継目なしにできる、という利点もあった。このようなポイラーは外側が箱型だが、内部には折れ曲った長い煙道があり、燃焼ガスはそこを通りながら水に熱を与えて蒸気を作り、燃焼排気は煙突から出るようにしてあった。
しかし銅にせよ鉄にせよ、初期のものは工作技術が拙劣だったので、作ったはよいが水を張ってみると、板の継目やびょうの頭のところからやたらに水が洩りだし、じょうろのようになるのもそう珍らしいことではなかった。だから鉄のボイラーの場合は、大きな洩れだけはなんとか抑え、後は小孔が錆で自然にふさがるのを待った。錆の発生を早めるために、ボイラーに張った水の中へゆでたじゃが芋やかぼちゃ、オートミール、ひどいのになると馬糞を投げ込んだりした。こんなことが真面目に行われていたのだ。しかもやっかいなことに、いよいよ火をたいて蒸気を作る段にたると、熱と蒸気圧のためにポイラーはいびつに変形する。そのうちに工作技術も材料も進歩して、さすがに馬糞を投げ込んで水洩れを止める、というのはなくなってきたが、それでもこの箱型ボイラーは19世紀半ば頃まで商船には使われていた。
2.煙管式ボイラー
同じ頃、煙管式ボイラーも作られるようになった。これは細いパイプを何本も並べて水中に置き、燃焼ガスは炉からこのパイプを通って煙突へ出て行く途中、外側の水を加熱して蒸気にする仕組みでおり、このタイプの極めて素朴なものをアメリカの蒸気船研究家、ジョン・フィッチがすでに作ったことは先述した。
初期の煙管式ボイラーは外観が四角な箱型をしていたが、これでは平面の部分が多く圧カに弱い、その上図体がかさぽる欠点もあった。そこでいっそのことコンパクトた円筒形にしてしまえ、という考えで作られたのがスコッチ・ボイラーとか円缶(マルガマ)とか名付けられるものである。これは現在でも、補機類の蒸気供給源とLて商船などには愛用されている。補機とは、発電機、荷役用ウインチ、消火装置、冷暖房機械その他、船の推進を直接司る主機関を除く一切の機械類を指す便利な言葉である。
3.水管式ボイラー
煙管式の次に登場したのが、ウォーター・チューブ・ボイラー水管缶(スイカンガマ)と称されるものである。これは煙管式とは火と水との関係が逆になって、水を循環させる多くのパイプの外側を燃焼ガスが加熱して、蒸気を作る仕掛のものだ。このタイプは19世紀末に実用化され、初めは主として軍艦に採用された。こうして高温高圧の蒸気が得られるようになると、蒸気機関は非常に能率的にたった。船舶備え付け用のボイラーは、小型でしかも大量の高圧蒸気を常時作れることが望ましい。そのためには水に対してたるべく大きな面積の熱伝導面が必要である。そこでボイラーの内部は細かく分けた方がよい、ということになる。このような基本的な考え方のもとに、単純た風呂釜スタイルから出発Lて、鉄箱型、煙管式、水管式へと発展してきた。それは、そのような構造のボイラーを作れる材料、鋼の出現と工作技術の進歩が、一九世紀末にもたらされたからでもあった。
(4)復水器
次に、コンデンサーにも触れておこう。シリンダー内で膨張しピストンを動かして仕事を終えた蒸気を、水に戻すための装置がコンデンサー(復水器)であるが、ワットが発明したのは噴射式復水器といい、冷却されるべき蒸気の中へ冷却水を直接送り込む仕組みだった。陸上用の蒸気機関ならば、冷却用の真水もふんだんに使えるからこれでも良かったが、水に制約のある船内ではそうはいかない。そんなことをすれば冷却用の真水とボィラー用の真水(ボイラー・ウォーター、養缶水(ヨウカンスイ)、缶水)だけで、船内はいっぱいになってしまうだろう。これでは何のための船だか分らたい。
そこで、初期の蒸気船では、仕方なく冷却用に海水を使っていた。だからひと仕事終えた蒸気はコンデンサー内で水に戻るときに海水と混り合ってしまう。さらに初期の蒸気船では養缶水として海水をそのまま使っていた。船がまだ小型でエンジンも幼稚、そんな初期の蒸気船時代には、真水など人問の飲料分しか積めない場合も多かったので、そうせざるを得たかったのだ。これでは航海中にボイラー内部に塩が溜って、ひんぱんにそれを取り除かなければ、円滑な運転ができなかったのも当然である。この作業中ボイラーはもちろん使えないから、船は止めるかあるいは帆走するしかない。運航の非能率は甚しい。しかも塩落しは難作業で、揺藍期の蒸気船がこれに悩まされたことは多かった。
こんな欠点を改善するために発明されたものがサーフェイス・コンデンサー(表面復水器 surface condenser)で、それはこういう仕組みだ。細いパイプをたくさん並べその中に冷却水を通す。冷却水としては船の周りに豊富にある海水を、ポンプで汲み上げ流してやればよい。その冷却パイプの外側に蒸気(排気)を触れさせれば、それは簡単に水に戻る。おるいは冷却水と排気の配置の関係はこの逆でもよい。要するに冷却用海水と蒸気の復水とを完全に分離しているところが、この装置のみそである。こうすれぼ排気を水に戻して再び加熱し、蒸気としてまた仕事をさせる、という循環が成立する。空問と重量に非常な制限がつきまとう蒸気船にとって、それは大きな福音だった。これがうまく働いてくれれぱかなり小さい船でも、真水の養缶水を必要量積み込んで航海することが可能となる。
サーフェイス・コンデンサーは、イギリスの造機技術者サミュエル・ホール(Samuel Hall 1781〜1863年)により1834年に発明された。700余トソの小さなシリウス号が、この新装置をつけていたおかげで、蒸気力のみによる初の大西洋横断蒸気船の栄冠(1838年4月23日)を獲得できた。発明されて間もないころのサーフェイス・コンデンサーは価格が高く、新製品にありがちな故障多発という理由で、当面は不評だったが、1860年頃になると改良が進んで真価を現わし姶め、以後は広く用いられるようになった。
2.船舶用蒸気タービン(P191〜199)
(1)タービンの開発
蒸気ターピンは原理だけは、往復動蒸気機関よりもずっと古くから知られていた。しかしそれを工業用の動力源として実用価値のあるものにするのは、多くの理由で不可能でもあった。ジェームズ・ワットが彼の記念すべき蒸気機関を完成させたのとちょうど同じ頃、ポルトガルのある技術者が工業用の反動蒸気タービソの試作に成功した、との噂が彼のところへも伝ってきた。が、ワットは『タービンというものは、馬鹿馬鹿しい程の高速度で回転したがる機械だ。その点が解決できなけれぽ実用にはならない。当分の間、蒸気タービソの時代は来ないだろう』と笑っていたという。事実はそのとおりとなった。
タービンの実用化はワットの指摘のように、高速度で回転するタービソの本体に、いかにして大きな機械的仕事をさせるか、という点を技術的に解決することにかかっていた。その時期は19世紀の後半になって、ようやく訪れる。この頃には往復動蒸気機関が一応発達の頂点に達して、もっと高速運転が可能な新しい原動機の開発が要求され始めた。そこで原理的には古くから知られているタービソの再開発となる。工作技術と材料の進歩は、実用に耐えるものの生産を可能にしつつあった。
このような時期に、蒸気タービンの実用化に尽力した技術者は世界に数多くあった。しかLイギリスのチャールズ・アルジャーノソ・パーソンズ、アメリカのゴードン・カーチス、フランスのエドモン・ラトーおよびスウェーデンのド・ラヴァルの四人の作品が、いずれも優れた実用価値をもつものとして成功した。なかでもイギリス人パーソンズは、蒸気タービンを船舶推進用の原動機として実用化するのに、最も力を注いで数々の成果を挙げ、その結果蒸気タービソ船時代を開く直接の元祖となった。
パーソンズ(Charles Algernon Parsons 1854〜1931年)はアイルラソドの由緒正しい伯爵家の末子として、1854年に生れた。青年時代はケンブリッジ大学で、数学と工学を学び共に抜群の好成績だった。生家が金に困らたかったので、学業のかたわら船好きの彼は兄弟でヨットを買込み、イギリス沿岸から大陸地方まで、白家用ヨットの巡航を楽しんだりした。若い頃のこんな環境が彼を生涯、船舶用の蒸気タービン研究、製作に目を向けさせることになる。
卒業後は有名な兵器メーカー、アームストロソグの工場で実技を習得することに努め、1884年には自分の発明した蒸気タービソに関する最初の特許をとる。わずか30歳の若さだった。以後の10年間は、他の実業家と共同したり、あるいは単独で工場を経営したりして、もっぱら発電用の大型タービンなどを製作Lた。
彼は1894年にパーソンズ・マリーン・スティーム・タービン社を創立し、ここで船舶用蒸気タービソの開発と生産に乗り出す。彼はまずそれの特許をとった。その発明の題名は“蒸気タービソで船舶を推進する発明で、回転運動するタービンで直接または歯車を介して、スクリューあるいは外車を駆動する装置”というものだった。これで分るように、従来の往復運動機関とはまったく別の手段で船を動かすことが、強調されている。
(2)タービニア号
パーソンズはタービンをテストするための実験船、タービニア号(Turbinia)を建造した。それはこれから述べるようた経過で成功し、世界に初めて出現したタービン駆動の蒸気船として、非常に有名になった。陸上運転用のタービンではすでに多くの実績を残していたバーソンズだったが、船舶に応用するのには極めて慎重だった。実船建造に先立って長さ1.8mほどの模型船を作り、彼はそれを使って実船に必要た機関出力とスピードとの関係を検討した。タービンという機械の特質を発揮させるために、推進器はスクリューとした。スクリューのシャフトも最初は一本だけからスタートし、三本付けるのが最も良いとの結論を得た。
これだけの準備をLた後、実船建造にとりかかる。タービニア号の要目は長さ30m余、幅が約2.7m、深さが2.1m強で吃水が1mくらい。船体は全部鋼鉄で造られた。高速が予想されるので、弱い材料では船体がもたないのである。パーソンズのタービンは、蒸気の衝動と反動両方の作用を組合わせたもの、これには大量の高圧蒸気が必要だったのでポイラーは水管缶をつけた。
三本のプロペラ・シャフトはそれぞれ一台のタービンで、直接回転する構造とした。蒸気はまず右舷側の高圧タービンに送られ、そこでシャフトを回転させ、やや圧力を減じた後に左舷側の中圧ターピンに入り、そこでもうひと仕事し、さらに中央の低圧ターピンを回転させて、最後には復水器へ戻るようにした。三台のタービンの出力合計は2400馬力だった。シャフトには初めただ一個のスクリューを付けた。これで試走してみるとスピードが意外に上らない。各種のスクリューを付けかえて、30回ほど試してみてもよい結果がでなかった。
パーソンズは粘り強く実験を繰返し、その原因がプロペラのキャビテイションにあることを突止めた。シャフトは1800rpm(回転/分)という非常な高速で回転するので、それが起ったのである。キャビテイションとは空洞現象ともいい、水中で回転する翼の先端や背面、付根などへ、部分的に水圧が低下することによって気泡が着き、翼面に孔があいたり振動や騒音の原因になったりする現象である。これは高速回転するプロペラにつきまとう、やっかいな間題となっている。
プロペラの直径を大きくすれば、これはある程度防げることが分った。しかし船体が小さいので、むやみに大きなプロペラにはできない。そこで彼は一本のシャフトにあるプロペラの個数を増やして、それと同じ効果を得ることにした。こんなわけで、ターピニア号のブロペラ・シャフトには各三個ずつ、都合九個のスクリューが付いている。これで難問の一つは解決した。
あとはこの船を、どのようなかたちで世間に発表するかである。海軍や商船界の首脳部には、画期的な発明や技術革新をなかなか受入れたがらない傾向があることは、これまで何回か述べた。ましてやパーソンズが相手にするのは、なかでも特別な石頭で鳴らしているジョンブルの海軍だ。生半可なことでは、ターピン推進の優秀性を理解してくれそうもない。
彼はこのことをよく承知していたので、タービニア号の実験は、人目の少いスコットランドの片田舎の海で秘かに続けながら、機会がくるのをじっと待っていた。3年が過ぎた。1897年6月、ついにチャンスが訪れた。この年はヴィクトリア女王の在位60年に当り、記念の大観艦式がスピットヘッドで催されることに決ったのである。スピットヘツドとは、イングラソド南部、ポーツマス沖の艦隊泊地のことで、彼はここでターピニア号の優秀性を、いやおうなく納得させるために次のような“秘策”を用いた。
6月26日、大観艦式の当目、そこには160隻以上の英国軍艦が威風堂々と集合していた。それらの中には最新の往復動蒸気機関を装備した新鋭艦もあり、大英帝国の誇りと繁栄を堅持するべく多年にわたって奮闘してきた帆走艦も混っていた。いずれも賑やかに満艦飾を施し威儀を正している。この他にも招待された外国の軍艦や優秀商船があり、さしもの広い錨地が一杯であった。定刻、女王陛下の御召艦が近づくと各艦の発する礼砲はいんいんと響きわたり、式典がまさにクライマックスに達しようという瞬間、錨地の端から艦列の中へ猛然と割込んできた小艇があった。それは女王を迎えてかしこまっている大小の軍艦の間を、波を蹴立てて文字通り縦横無尽に馳巡った。このハプニングに、式場警備の駆逐艦や魚雷艇など、すわ一大事発生とばかり直ちに制止にのり出したが、平素快速を誇っているそれらの艦がやっきになって追回しても、この小さな船の猛スピードには、全然歯がたたなかった。これこそパーソソズのタービニア号であった。
当時の駆逐艦などは最高速のものでも30ノット(約56km/h)程度。この時ターピニァ号は34.5ノット(約64km/h)の快速で走り回ったので、彼らの追いっけようはずがない。この船は船首部が極端に幅を狭くしてあり、船底は船首に向い斜めに鋭く上っていて、まるで刃物のようた船型をしている。しかも小さた船体に2400馬力ものタービンを積んでいるのだから、それこそエンジンの化物だ。それが女王陛下および海軍高官連の目前で、並み居る新鋭軍艦を尻目に、会場狭しとばかり馳巡ったのだから、まさに宣伝効果は満点だった。パーソンズは、自身が伯爵家の出身という貴族だったので、こんな派手な演出も平気でやれたのだろう。
(Turbiniaの写真はこちら 次のサイトも参照 http://www.nationalhistoricships.org.uk/register/138/turbinia)
(3)タービン船の時代
さすが頑固た海軍首脳部も、このデモンストレーションに会っては、パーソンズのタービソの実力を認めないわけにいかなかった。新発明に何かとケチをつけなけれほ気のすまない彼らも、この時ばかりは至極あっさりとパーソンズに二隻の駆逐艦用タービン製作を依頼した。そこでヴァイパー号、コブラ号という史上初の蒸気タービン推進駆逐艦が誕生する。ヴァイパー号は長さ約64m、排水量370トン。高圧ターピンニ台、低圧タービソニ台で出力合計10000馬力。それぞれのタービンが一本ずつのシャフトをもち、シャフトにはスクリューが二個付いていた。試運転でこの艦は37ノット(約69km/h)を記録した。その時点での世界最高速である。コブラ号もほぽ同様の艦だが、こちらは35ノット止りだった。ところがこの二艦は就役後問もなく本国近海で、荒天のため艦体が真っ二つに折れる事故をたて続けに起した。1901年の8月と9月のことだった。調査の結果、艦体構造が高速力航行に対して比較的弱かったことが判明し、タービソ推進の欠陥ではないことが証明された。
その後三年を経て、イギリス海軍は全艦を高速化する方針を打ち出し、.1905年には戦艦ドレッドノート号までが、ターピン推進で建造される。世界の各海軍国も先を争ってそれを進め、ここに軍艦のタービン推進時代が開幕する。潜水艦その他の特殊なものは別として、それは第二次世界大戦が終るまで続いた。
一方一商船はどうだったろうか。パーソソズはターピニア号の成功の後、民間の船会社および造船業者と提携して、商船のタービン推進を研究し始めた。彼らのグループは1901年にキング・エドワード号という550トンで長さ76mばかりの鋼船を造った。この船は中央に高圧タービン、左右両舷に低圧タービソを掘え、三本のシャフトがこれに連絡されている。中央のシャフトは直径約1.4mのプロペラ一個で700rpm、左右のシヤフトは直径約1mのプロペラをそれぞれ一個ずつもち、1000rpmだった。三台のターピンの出力合計は3500馬力相当である。
この船はイギリス沿岸の遊覧客船とLて造られたが、パーソソズのグループは従来の蒸気機関外車船と比較するために、ほとんど同じ構造、大きさのものをもう一隻造り、それには同じ馬力のダイヤゴナル・エンジンを搭載した。これによってまず判明したことは、タービンの方が重量で約120トソも軽いことだった。次に、両者を競走さた結果、ターピン船は最高20.5ノツト(約38km/h)を記録したのに、レシプロ・エンジンの外車船は18ノット(約33km/h)しか出なかった。タービン推進の優秀性は商船でも証明されたのである。以後は商船、軍艦共に蒸気タービン化され始め、20世紀初頭に幕開いた大西洋の豪華客船時代には、ほとんどの船がタービン推進だった。たお付け加えておくと、キング・エドワード号は二度の世界大戦に軍隊輸送船として使われ、1951年に引退するまで、現役就航50年という希に見る長寿を保った船だった。
パーソンズはタービンだけではなく、後には光学機械の研究にも着手、多くの考案や改良も行った。これらの業績で数々の学問、科学技術上の賞を受け、1931年に77歳で世を去った。彼はジェームズ・ワット以後のイギリスが生んだ、最も創造性に富む技術者と称えられている。
(4)減速装置
現代のタービン船では、タービン本体とスクリュー・シャフトとは、減速歯車で連絡されているものが多い。一般にプロペラは商船の場合100rpmくらいで最も有効に働くから、毎分何千回転とか数百回転とかいうタービンの高遠回転を、プロペラに適する回転数まで落とLてやらなければならない。そのために直径の異る歯車の組合せ装置を、タービンとスクリュー・シャフトの間に置くのだ。
このタイプのものをギャード・ターピン(歯車減速タービン)という。大小の歯車の組合せを一回だけ使うものを一段減速、二回使うものを二段減速と称する。現在の船ではターピンに直結したプロペラ・シャフトは全然使われず、歯車装置を含む何らかの減速装置を必ずもっている。
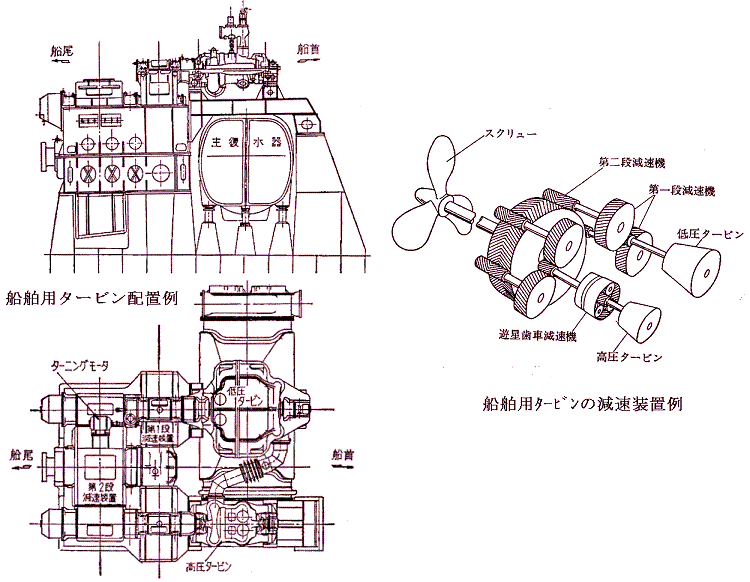
なお、ターピンはその構造上、逆転が効かないので、船のようにブロペラを反転させる必要のあるものでは、回転方向が反対の後進専用のタービソを備えている。後進用は段数も少なく出力も前身用の30〜40%で、前進時これはコンデンサー圧力に等しいほぼ真空に近い中で空転させておく。
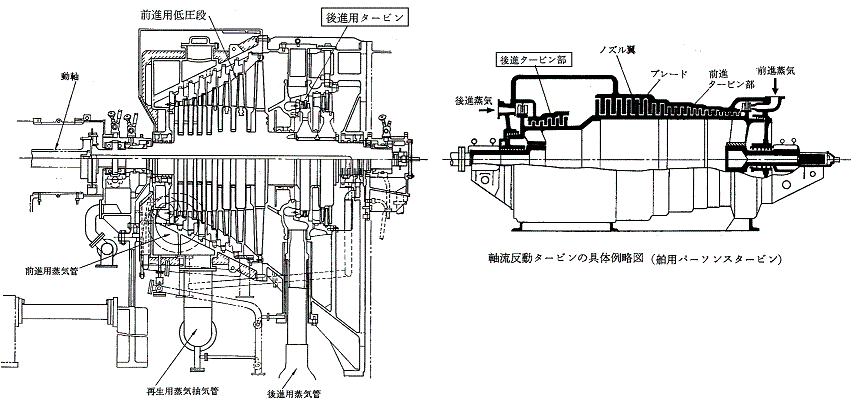
終りに、往復動蒸気機関に比べて蒸気タービンの利点を挙げると、同じ馬力を得るのに小型軽量にできること、軽くて回転が速いから高速力が出せること、衝撃による機関や船体各部の損傷および震動が少い。このことは結果として維持、修理費が安くつき船客、乗組員の生活環境もよい、などが考えられる。
(5)組み合わせ蒸気機関(P212)
・・・処女航海で遭難(1912年4月15日)した悲劇で有名なタイタニック号(Titanic)の機関について述べる。この船はイギリス有数の汽船会社の一つ、ホワイト・スター・ラインの持船だった。1911年にベルファストの造船所で進水、翌年完成。姉妹船にオリンソピック号があった。長さ270m、幅が28m余で46328総トソ。
ボイラー室は6室あり合計(24基+予備5基)の石炭ボイラーが備え付けられていた。もちろん蒸気は海水で冷却した復水器で凝縮させて再利用する循環式である。大西洋横断に6000トンの石炭が必要でした。
推進機関はちょっと変っていて、三軸のスクリューをもっていたが中央のものが蒸気タービン(16000馬力)で両舷のは四汽筒の3段階膨張往復動蒸気機関(four-cylinder
reciprocating triple-expansion steam engines 高圧1、中圧1、低圧2シリンダー 15000馬力×2基)で回転された。出力合計46000馬力だったが、いざとなれぱそれは55000馬力の実力を容易に示すことができた。このタイプのエンジンを組み合せ蒸気機関と呼ぶ。高圧蒸気をまず往復動蒸気機関で使い、やや圧力の下ったその排気をタービンに入れて回転させる。こうすることにより蒸気使用の効率をあまり落さず、逆転が容易というレシプロ・エンジンの特性も併せもつことができる。このシステムを最初に実用化したのは、やはりパーソンズだった。このタービンはまだ減速ギアがないスクリュー直結式です。タイタニック号は平均速力22ノット(約41km/h)で運航させるはずだった。この船の所有会社は、一時期ブルー・リボン獲得競走に精出したが、この頃にはそれは止めてスピードはやや遅いが船体の巨大化と、内部設備を一段と豪華精巧、ひらたくいえばぜいいたくにするようになっていた。大西洋の船旅での絶対安全と、乗心地のよさとを売物にしていたのである。そのための看板船がタイタニック号でありオリンピック号であった。それはそれで、非常な人気を集めていた。・・・(次のHPが詳しい http://gigazine.net/news/20150212-titanic-engineering-facts/)
3.船舶用ディーゼル機関(P216〜225)
(1)ルドルフ・ディーゼル
熱機関は燃料の燃焼を機関本体の外部で行わせる外燃機関と、内部で燃焼させる内燃機関とに大別できる。前者にはこれまでに出てきた往復動蒸気機関や蒸気タービンが含まれる。外燃機関が往復運動式と回転式とに分けられたように、内燃機関にもそれがある。シリンダーとピストンその他の付属装置で往復運動するものが、ガソリソ・エンジンやディーゼル・エンジンであり、回転式内燃機関とはガスタービンのことである。現在ではその中でもディーゼル・エンジンが、船舶推進用の主力となっているので、ここでは揺藍期のディーゼル・エンジンを積んで走った船を概観することにする。
厳密にいえば、ここに述べるルドルフ・ディーゼルよりも前に、内燃機関の研究をした人物がいたが、それは省略して、ディー
ゼル機関の生みの親ルドルフ・ディーゼルの経歴の紹介から始める。彼は1858年3月、パリで生れた。しかし家系は生粋のドイツ人である。ディーゼルはわずか12歳の時、単身ドイツのアウグスブルグに渡り、工業学校に入学し続いて、ミュンヘン工科大学に進んだ。生家が貧しかったから、この間アルバイトをしながら勉強を続けたが、成績はいつも学校創立以来の、最優秀学生だった。
卒業後は大学で恩師カール・フォン・リンデ教授の助手を務めるかたわら、蒸気機関の熱効率を改善する研究を始めた。当時、リンデといえば熱力学の最高権威者で、冷凍機の発明者でもあったから、その影響を強く受けた。やがて冷凍機を製造する会社の支配人に就任、かたわら研究も続けていたが、この頃には蒸気機関の改良ではなくて、もっと直接的に機械的エネルギーを得られる内燃機関の研究に切りかえていた。
約13年の研究生活の後、1890年2月に彼は最初のディーゼル・エンジンの特許を取った。しかし、その真価を理解する人がほとんどなかったので、啓蒙と宣伝を兼ねて「合理的熱機関の理論および構造」と題する著書を表わした。これは後に非常に有名な本となる。これを出版してからディーゼルは自己の理論にもとずく新しいエンジンの、実用品を作ることに約7年間を費した。当時一流のドイツの機械メーカーが資金を提供したのである。その間に二基の試作品を造ったがそれらは失敗。三台目のものがようやく成功した。それはたった18馬力の能力だったが、史上初の信頼し得るディーゼル・エンジンとなった。1897年のことである。
内燃機関の作動の理屈は簡単にいえぱ、シリンダーの中へまず空気と燃料の混合気体を入れ、それをピストンで圧縮する。そこへ点火すると混合気体は爆発してピストソを動かし、最後に排気をシリンダーの外へ出してやる、ということの繰返しである。シリンダー内部での吸入、圧縮、爆発、排出の四行程がクランクの二回転で完了するものを四サイクル機関といい、それが一回転で終了するのをニサイクル機関と呼ぶ。ただしディーゼル・エンジンの場合は、最初シリンダーに送り込まれるのは混合気ではたく空気だけである。これを圧縮すると大層な高温になる。そこへ燃料(霧状にたった重油)を噴射してやると爆発が起る。外部から点火する必要はない。同じ内燃機関でもガソリン・エンジンなどは点火装置が必要だが、それが要らないのがディーゼル・エンジンの特徴である。
1898年には、ディーゼルは四台目のエンジンを作った。彼のエンジンの高性能なこと(燃料消費が少い割合に大きた馬力が出せる)は、発明者ディーゼル以外の第三者の試験、計測により客観的に証明された。ディーゼル・エンジンの優秀性は世界的に造機メーカーの注目するところとなった。初期のそれは四サイクル型ばかりだったが、やがてニサイクルのものも製作される。同じ大きさで同じ回転数の四サイクル機関とニサイクル機関とを比較した場合、燃料の爆発する回数は後者が二倍となるから、単純にいえぽ得られる馬力も二倍になる。だから様々た制約があって、しかも大馬力を必要とする大型船にはニサイクル型の方、が多く採用されている。
20世紀に入ってから10年ほど経つと、ディーゼルの特許権を譲り受けた各国の造機会社は、それぞれに工夫を加えて逆転可能の船舶用ディーゼル・エンジンを生産しだした。この時期には、それらを搭載した船がフランス、ロシア、オランダ、イギリスその他の国で、少しずつではあるが建造され始めている。しかし、いずれも1000トンから2000トソ級の貨物船で、350馬力から800馬力止りの、近海使用のものばかりだった。
また同じくこの時期、ようやく実用価値がでてきた潜水艦にも、浮上航行用の主機関としてディーゼル・エンジンが付けられている。これは作動原理上、ボイラーを必要としないから潜水艦のような容積の点で大きな制約がある特殊な船には、うってつけであった。だからディーゼル・エンジンの改良、発達は潜水艦に負うところも大きい。逆にそれが発明されたからこそ、潜水艦の性能は飛躍的に向上した。それまでの潜水艦は、浮上中ガソリソ・エンジンで走るものが多かった。しかしそれは大きな危険を伴っていた。というのは、当時の潜水艦は燃料のガソリソが、貯蔵タソクから僅かずつながら常に蒸発して、狭い艦内に充満L、いつ爆発するかも知れないような、物騒た状態で行動していたのだ。ところがディーゼル機関の燃料、重油や軽油はガソリンと違って揮発性も爆発性も低い。これは潜水艦にとってまさに福音であった。以後、原子力潜水艦が開発されまで、ディーゼル・エンジンは潜水艦にとって、無二の動力源となったのである。
ルドルフ・ディーゼルのその後である。彼は自分の発明したエンジンが真価を認められ、世界各国に広まるようになって、大きな満足感を抱いたが、なおかつ一つの夢を持っていた。それは当時世界一の重工業国イギリスに、ディーゼル・エンジンの生産工場を建て、最高の技術と材料を駆使して最大のものを作ることだった。
やがて、それも叶えられる。イプスウィッチ(イングラソド南東部の中都市)に工場ができ、そのレセプションに出席するため彼は渡英することになった。1913年9月29目夕刻、アソトワープ(ベルギー)を出港するイギリス客船ドレスデン号に乗船した。ドーバー海峡を横切って、大陸とイギリスとを連絡する船だった。ディーゼルは迎えに来た工場幹部と、夜10時頃まで談笑していたという。しかし、ドレスデン号が翌朝早くハリッジ(イソグラソド南東部の港)に入港した時には、ディーゼルの姿はなぜか消えていた。そのことが判明すると、たいへんた騒ぎになった。船内はくまなく探されたが発見されなかった。ベッドには寝た形跡もなかった。もしや海に落ちたのではないかとして、海峡航行中のあらゆる船に手配され、大規模な捜索も行われたが全ては徒労におわった。
ルドルフ・ディーゼルは、このようにして忽然と消失せたのである。55歳の働き盛りだった。とにかく、20世紀最大の科学者の一人ともいえる人物の失踪である。一大センセーションを巻き起した。ある者は事業の失敗による自殺説を唱え、ある者は他殺を主張した。それも他国の謀略説と、才能を妬んだ者の凶行説とがあった。もちろん偶発的な海中転落も考えられた。しかし、死体どころか身に着けていたものの一片すらも発見されなかった。
こうして、デイーゼル失踪の真相は永遠の謎に包まれたままである。けれども彼の遺した業績は多くの研究家、技術者の手によってその後も着実な成長をとげ、デイーゼル・エンジンは現代では陸上に海上に広く用いられ、最も重要な原動機の一つとなっている。
(2)船舶用ディーゼル・エンジン
船にデイーゼル機関が搭載され、それがたんなる試用ではなく、本格的な実用価値をもったのは1910年頃からである。この年オランダのアムステルダムで一隻のタンカーが建造された。長さ約60m、1200トンばかりの船で、ヴァルカヌス号と名付けられた。これには6汽筒からなる四サイクル、500馬力のディーゼル・エンジンが備え付けられた。これもまたオランダの造機メーカーによって作られたものである。各シリンダーの直径は約40cmでストロークが約60cm。165rpmでもちろんスクリュー推進だった。それは満載で1300トンほどの石油を積むことができたが、この状態で8ノット(約15km/h)の速力を出せた。ヴァルカヌス号は、ポルネオで採掘された原油とその精製品を、東南アジアにあるオランダの植民地一帯に輸送する目的で建造されたもので、現代タンカーの元祖の一つでもある。1931年、船としての生命を終えるまでの約20年間、本国を遠く離れた海域で役目を無事に果し、最後までエンジンは健在であった。
1912年にはセランディア号というのがコペンハーゲンで造られた。これはいろいろな意味で多くの話題を提供した船だった。長さ約113m、幅が16m余で深さ、が8.3m、4950総トソの鋼製貨物船だった。造ったのはバーマイスター・アソド.ウェイン社(B&Wの略称で呼ばれることが多い)。デンマークの造船造機会社であるが、最も古くからディーゼル・エンジンを製作している、老舗の大メーカーの一つとして世界的に有名である。セランディア号は二基のディーゼル機関をもつ二軸のスクリュー推進船だった。出力は一基あたり1250馬力、四サイクル8汽筒でシリンダーの直径約53cm、ストローク約73cm。回転数140rpmである。これに積込まれたエンジンは、基本的にはもちろんディーゼルの発明したものだが、メーカー独自の改良を加えて、船舶用により好適なようにしていた。同年3月、完成と同時にロンドン、アントワープ間で試験航海を行い大成功を収めた。平均速力は11ノット(約20km/h)以上を出せた。その航海に招待された人々は、この船を初めて見た時、一様に奇異の感を抱いた。蒸気船につきものの煙突が全然見当らなかったからだ。主機関の廃ガスおよびボイラーの排気は、最後尾のマスト上都から空中へ放出されるようになっていた。一言つけ加えると、ディーゼル船でも発電機、ポンプ、ウインチその他雑用目的のためボイラーをもっているのは普通のことである。ただそれは主機関運転用のものよりは当然小さい。
セランディア号はコペンハーゲソ、バンコク問の定期航路に投入され、南洋材や雑貨を運び期待通りの好成績をあげた。最初の航海からしけの洗礼を受けたが、船体もエンジンもびくともしなかった。無補給で長距離を航海するには、二重底タンクに積込まれた重油燃料は、石炭と違い非常に好都合であった。建造後約20年経って、そろそろ老朽化が目立ちだした頃には売りに出されて、以後は転々と持主が変ったが、1942年、目本の御前崎沖で座礁、沈没している。しかしこの間、エンジンには大きな間題は起らなかったという。この船は新登場のディーゼル・エンジンを設備して、長距離を定期的に航海することに成功した、史上最初の大型船としてそれを造ったB&W社の名と共に、たいへん有名になった。
ヴァルカヌス号、セランディア号が立て続けに成功したため、海運関係者は大きた刺激を受け、その後急速にディーゼル船が増加した。ある統計によれぱ1914年には、全世界に存在する動力船のうち、ディーゼル船はわずか0.5%に過ぎなかったが、約20年後の1935年には18%に、1960年代の初めには蒸気機関の船とディーゼル船とが、ちょうど半々の比率になり、現在(1977年)では70%がディーゼル船となっている。
[補足説明]
21世紀の今日、大馬力のディーゼルエンジンが実用化されて船舶用ディーゼルエンジンの熱効率は50%を超えている。そのため船舶の動力としての蒸気タービンは姿を消しほとんどがディーゼルエンジンとなった。蒸気タービンの活躍の場は発電の分野が主になっている。
(3)煙突
さて、船の煙突の話である。現代のわれわれは大型船には煙突があるものと思っている。子供に船の絵を描かせれば、必ず煙突がついている。これがないと船としては様にならない感じさえある。しかし本質的な機能とコストの面からだけいえば、現代の船にはあのようた煙突はいらない。大型船の煙突の内部はがらんとしていて、何本かの細いパイプが走っているだけだ。それらを通じてエンジンまたはボイラーの排気が、大気中に放出される仕組みである。周りを大きく取り囲んでいる鋼の薄板の円筒を見て、われわれは「船の煙突」と呼んでいるわけだ。外側の円筒状の囲いを、正確には化粧煙突という。その船の所属会社のシソボルを描いたり、色を塗って目立たせたりして、いわぱ女性の化粧のような役割をしているからだ。
フルトンやスチヴソスの時代、すなわち蒸気船の発祥期には、煙突は欠かすことのできないものだった。まきや石炭をたき、もうもうたる黒煙を船外に追い出すためには、それは必需品だった。その時代に比べれぱ蒸気船が長足の進歩を遂げた19世紀末から20世紀前半にかけても、まだ船は大きな煙突から黒煙を吐いて走っていた。それは主として燃料の改善が遅れてきたことによる。重油を燃料としてシリンダーの内部で直接燃焼させる、ディーゼル機関はともかく、蒸気力で推進する船では、ボイラーの燃料に石炭を使う時代が、かなり長く続いていた。つまり、重油でポイラーをたくことは、初期の段階ではかなり技術的困難があり、また重油そのものの供給量も少かったのである。全世界の動力船のうち、石炭を燃料とLているものは1914年には約89%、第二次世界大戦の始った1939年になってさえも、約45%の船が石炭だきだったという。
だからこの時期、大西洋の定期客船には煙突の数を、必要以上につけた船が多かった。有名なモレタニア号、ルシタニア号、タイタニック号、オリンピック号などである。いずれも四本煙突だが、実質的には三本で充分だった。やや時代は下るが、フランス自慢の超豪華船ノルマンディー号は三本煙突だったが、これも最後部の三本目は機能上不要だった。しかし当時の世間には、蒸気船といえば煙突から煙を吐いて走るものであり、その数が多ければ多いはど強力な機関を備えて快速で走り、かつ安全な船の証拠でもある、という固定観念があった。そんなわけで人々は煙突の多い船を選んで乗る傾向もあった。だから船主は船客誘致策の一つとして、本来は不必要な煙突をつけてまで、堂々たる外観に仕立てあげたのである。船に命を預けて大海を渡る客の心理を巧みについた商法である。
このように本来不必要な煙突のことを擬煙突、英語でフォールス・ファンネルとかダミー・ファンネルとかいう。その内部は物置にされたり、犬を連れた乗客のための、犬小屋が設けられたりしていた。モレタニア号もノルマンディー号も、最後部の煙突の内部は犬小屋である。大部分の客はそれとは知らずに、煙突の多さに満足していたわけだ。こんな風潮があったからこそ、セランディア号の設計者は、“本船は煙突不要の最新式のディーゼル・エンジンを傭えつけているぞ”ということを誇示するために、意識的に化粧煙突を設けず、マストで代用していたのである。
(4)ディーゼル・エンジンの特徴
ディーゼル機関は、タービン推進を含む蒸気機関と比較して、次のようなメリットがある。第一に機関自身の重量が軽く、機関室の容積が小さくてすむこと、これは超大型のボイラーを必要としないからである。さらに燃料消費が蒸気タービンに比べて7割くらいの消費ですむことである。その上、始動に要する時問が短い。2、3万トン型の船同士で比較した場合、蒸気ターピンではウォミング・アップに10時間以上も要するのが、ディーゼル機関ではそれは2、3時間ですむ。逆に欠点は船体に震動が発生すること、および、高速カが得られないことである。
しかし近年になって機関製造と運転整備の技術の大きな進歩により、信頼性が著しく向上している。その結果大型化が可能になり、今では一基当り数万馬力のものまで作られている。発明された時点では、たかだか20馬カの能力だったが、約半世紀の間にここまで進歩したのである。従って高速力が出せないという欠点はほとんど解消したといえる。従来、ディーゼル・エンジンの唯一最大の泣き所は、一台当り一万馬力程度のものしか製作できない点であった。だから大きた出力を必要とする場合には、機関の台数を増やしプロペラの軸数を多くしなければならなかった。内燃機関のもう一方の雄にガソリン・エンジンがあるが、これは大型船推進に用いられることはほとんどない。
4.まとめ(P233〜238)
(1)主機関の変遷
主機関の変遷について説明する。帆走から外車へ、これで無風でも走行できる船を人類は手にした。しかし主機関の馬力、信頼性、燃料貯蔵能力などが不充分だった時代には、風と帆にまったく頼らないというわけにはいかなかった。発祥期はおろか、船体が大型化し大洋での定期サーピスが可能になってからでさえも、外車蒸気船は帆船の影を色濃く引きずっていたのである。1860年代に入って、中、大型船の外車推進がほぼ終りスクリュー推進になってもまだそれは続く。1万トンで1万馬力以上の蒸気船から完全に帆が取り去られるのは19世紀のほとんど末であった。もっとも大西洋定期航路の場合は、客に安心感を与えるために実際には必要でない帆走設備を持っていたふしがなくもない。逆にいえば一都に帆を残している蒸気船でなけれぱ、客が寄りつかなかったことを示すもので、新参の蒸気船は、なかなか信用してもらえたかったのである。ちようど20世紀に入る前後から、帆や長いマストも不要となり、現代の汽船にかなり近い型となる。
それは、往復動蒸気機関が発達して大きな能力を発揮するようになったからだ。たった一汽筒のシンプル・エンジンから出発して、複数のシリンダーで蒸気の膨張力を何段階にも分けて利用する連成機関が船に備えつけられるまで、約50年の歳月を必要とした。この段階で蒸気船の燃料消費は一段と少くなったのである。
一方、蒸気利用には違いないが全然別の作動原理にもとずく原動機、蒸気タービンが発明され、それが中型船に用いられたのが19世紀末、ところが20世紀に入るとわずか10年ほどで、その能力は一気に向上し、信頼性、大出力、高能率の故に軍艦を含む大型船、快速船には欠かせない存在となったのである。
これらの主機関に蒸気を供給するボイラー、仕事を終えた蒸気を冷やして水に還元するコンデンサーその他も、主機関の向上とあいまって進歩したことはいうまでもない。五右衛門風呂スタイルや銅の湯沸かし式から、銅製箱型の大きなものとなり、さらに材質の点では鉄、鋼へと進歩、形式も煙管缶、水管缶となったのがボイラーの変遷だ。
また、ボイラーの内部に溜った塩を取除く重労働と非能率から解放されたのは1860年頃からである。船体が大型化し水の貯蔵能力が向上したところへ、表面復水器が改良されて実用価値をもったからである。これによって缶水に海水が混入する心配はなくなった。サミュエル・ホールによるこの発明は、船舶用機関の歴史上特筆すべきことであった。
(2)燃料の変遷
燃料について述べてみる。最初は薪。ついで石炭、重油となり、現在は原油生だきやLNGのベイパー・ガス(蒸発ガス)もある。発祥以来蒸気船の歴史は約170年(1977年時点)に及ぶが、その問に燃料として石炭を使っていた時期が100年以上もあった。
蒸気船が登場する以前は帆船ばかりだったから、それに乗組む船員も航海、甲板関係者と炊事係に医者ぐらいだった。しかし、蒸気船では主機関およびその付属装置を運転し、整備保守する人問が当然必要となる。ところがそれらを教育、養成する専門機関が、最初からあるわけがなく、機関要員を確保することは一大苦労であった。そこで初めは時計職人、メツキ職人、鍛冶屋、印刷工、水車大工などの多少なりとも機械をいじくったことのある者を、職場から引抜いたり募集したりして船に乗せていた。昨目まで村外れの仕事場で馬の蹄鉄を打ち、荷車の轍(ワダチ)をはめ直していた鍛冶屋の親爺が、今日は2千トン級の外国航路の船舶機関士におさまることも別段不思議ではなかったのだ。
専門教育を受けた機関運転の技術者が、安定的に供給されるようになるのは、19世紀の後半に入ってからである。ヨーロッパ各国海軍が増大する蒸気軍艦に対応するために、学校を設立、機関科兵を養成し始めたのが1850年代のことだ。
石炭だきポイラーの場合、それに投炭するのは機関部員の仕事の中でも、最も重要で最も重労働の一つだ。これに当るのを火夫と呼ぶ(日本の海運界には、現在この名称はないが便宜上これを使う)当直中の火夫はずらりと並んだボイラーのたき口の前に陣取って、燃え具合を見ながら石炭を巧みに投げ込み、燃え殻や灰を掻出し、蒸気をあげるのが役目である。彼らに助手として石炭夫がつく。これはコール・バンカーから繰出した石炭を、手押し車に積んで必要なたき口へ配って回り、灰や石炭殻を捨場から船外へ投棄するのが仕事である。
航海中、蒸気は常に安定供給されなければならない。それは至上命令である。ボイラー・ルームは50度以上にも上る室温と、もうもうたる石炭のほこりや灰、騒音で充満している。こん場所で仕事をするのだから、火夫はよほど強壮な体力と知識経験がなければつとまらない。
人力による石炭だきは、火夫の技量により蒸気のでき方にむらがある、という欠点がある。それに何よりも奴隷労働的な作業から、人間を解放するために石炭をボイラーへ自動的に補給する、給炭装置が工夫されたこともある。これをメカニカル・ストーカーと呼ぶ。20世紀前半くらいには、外国でも日本でもかなり使われていたようだが、重油だきに改められなけれぱ、根本的解決にはなり得なかった。軍艦はどこの国でも優先的に重油だきボィラーを採用していたが、一般商船まで洩れなくそうなったのは第二次大戦後のことだ。だから戦時中の目本商船には、これに関する苦労話も山はどある。
20世紀半ばになると、新登場の船舶用ディーゼル機関を装備した船も、だんだん増え始めた。第二次大戦以後は技術的進歩により、“C”重油と呼ばれる低質の重油もディーゼル・エンジンの燃料として使えるようになり、特に商船のディーゼル化は世界的な規模で進んだ。“熱効率”という言葉があるが、これは“何グラムの燃料を燃して何カロリーの熱量が得られ、その内で動力に変った熱量がどのくらいの割合であるか”を意味する。船の推進主機関について見た場合、熱効率はディーゼル機関が35〜40%。最も有効に造られた蒸気タービンで30%程度、往復動蒸気機関では約16%である。収益を重んじる商船のディーゼル化が進む理由もここにある。
ディーゼル機関の燃料は、現在のところ軽油と重油に限られている。前者は船舶用にはほとんど使われず、トラックなどの大型陸上交通機関の燃料となっている。しかしその作動原理だけからすれば細かく砕いた石炭(微粉炭)も燃料として使用可能のはずだ。現にディーゼル・エンジンの生みの親、ルドルフ・ディーゼルは微粉炭を使う研究もしていた。しかし、現時点まではそれに成功したという語は聞いていない。世界的に石油資源の不足と公害発生が叫ぽれている今日、船舶推進用その他に全盛を極めているデイーゼル機関はどうなるのだろう。