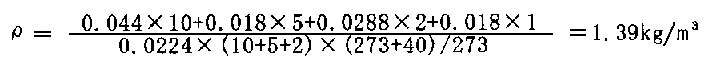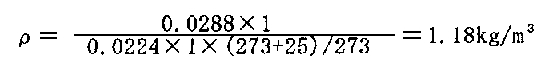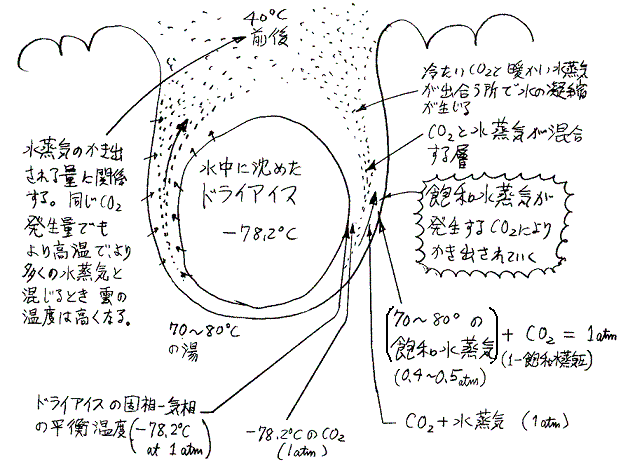俛俙俠俲丂丂丂俫俷俵俤丂丂丂俶俤倃俿
俆丏僪儔僀傾僀僗偵傛傞塤偺敪惗(侾俋俋俋擭)
丂
偼偠傔偵
丂
丂僪儔僀傾僀僗偼侾kg偑係侽侽墌偔傜偄偱妱偲庤寉偵庤偵偼偄傝丄偦傟偱嶌傞塤偼暥壔嵳傪惙傝忋偘傞戝愗側彫摴嬶偱偡丅擔崰偺宱尡偐傜偄偭偰敪惗偡傞塤偺検偼婥壔偟偨僪儔僀傾僀僗偺検偵斾椺偡傞條偵尒偊傑偡偟丄僪儔僀傾僀僗傪堦婥偵婥壔偝偣傞偵偨傞偩偗偺擬検傪帩偭偨搾検偺弨旛偑戝愗偺傛偆偱偡丅搾検偺尒愊傕傝傪偟偭偐傝傗傝丄搾傪娙曋偵弨旛偡傞憰抲傪偮偔傟偽奆傪傾僢偲尵傢偣傞偙偲偑偱偒傑偡丅
丂丂偨偩偟丄偙偺偲偒敪惗偡傞戝検偺擇巁壔扽慺偼丄椻偨偔廳偄偺偱幚尡幒偺彴偵懾棷偟傑偡丅偦偺偨傔丄幚尡偟偨屻偵嫵幒偺憢傪奐偗偰廫暘偵姺婥偝傟偰壓偝偄丅
丂
丂
丂
丂600倂偺僯僋儘儉慄傪俀杮暲楍偵偮側偄偱1200倂偺悈偺夁擬婍傪嶌惉丅乮幨恀5-2乯
侾俁俈儕僢僩儖梡偺億儕僄僠儗儞梕婍(3700墌乛屄)俀屄梡偄傞丅忋偵廳偹偰憓擖偡傞梕婍偼掙偵戲嶳寠偑奐偗偰偁傞丅(幨恀5-1)
丂僪儔僀傾僀僗傪擖傟偰憓擖偡傞嵺丄忋偺梕婍偵傆偨傪晅偗僄傾乕僟僋僩傪偮偗傞偲塤傪擟堄偺応強偵摫偗傞丅傾儖儈惢偺幹暊宆偺儂乕僗(捈宎俀侽cm)偱侾倣偺挿偝偑幹暊傪怢偽偡偲嵟挿係倣傑偱怢傃傞傕偺偑侾杮3900墌掱搙(搶梞壔妛姅幃夛幮僩儓僟僋僩僄傾乕儘乕僪)偱庤偵偼偄傞
丂
幨恀5-1丂僪儔僀傾僀僗塤敪惗憰抲
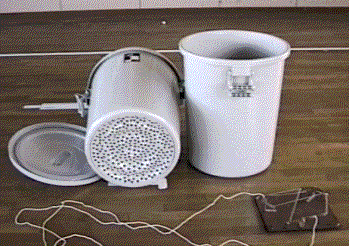
丂
幨恀5-2丂丂悈拞偵愝抲偟偨壛擬婍
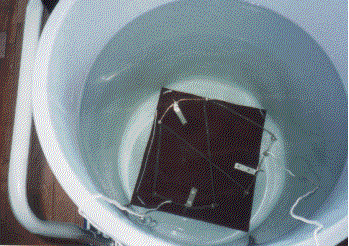
丂
丂
幚尡侾丏(侾俋俋俋擭俋寧)
丂壛擬婍偺惈擻傪帋偡梊旛幚尡傪偟偰傒偨丅悈俇俆儕僢僩儖傪億儕梕婍偵擖傟偰壛擬丅俁侽暘娫偱俈亷悈壏偑忋徃丅偙偺抣偐傜儚僢僩悢傪寁嶼偟偰傒傞偲
乮65000乵倗乶×7乵俲乶×4.2乵俰乛g丒K乶乯乛乮30×60乵倱乶)亖1062倂
偲側傝丄椻媝懍搙傕娷傔偰偩偄偨偄傕偔傠傒捠傝偺壛擬惈擻偩偭偨丅
丂
丂
丂
幚尡俀丏(侾俋俋俋擭俋寧)
丂俆俈亷丄俉俈儕僢僩儖(怺偝係俇cm)偺搾偵丄俁cm妏掱搙偵偔偩偄偨僪儔僀傾僀僗栺俆kg乮惓妋偵寁偭偰偄側偄乯傪壛偊傞偲侾侾倣巐曽掱搙偺嫵幒偵旼壓偔傜偄偺怺偝偺塤偑敪惗偟偨丅偦偟偰悈壏偼侾俇亷崀壓偟偰俆俈亷偵側偭偨丅
丂悈壏傪俀俆亷偐傜俈係亷偵偡傞偺偵壛擬婍偵揹棳傪棳偟偰俈帪娫傪梫偟偨丅暯嬒壛擬懍搙偼乮87000乵倗乶×49乵俲乶×4.2乵俰乛g丒K乶乯乛乮7×60×60乵倱乶)亖710倂
偱椻媝偵傛傞儘僗偑偆偐偑偊傞丅
幚尡俁丏(俀侽侽侽擭俉寧)
丂俈俇.係亷偺搾俋俉儕僢僩儖(怺偝俆俀cm)偵丄俁噋妏偵嵱偄偨僪儔僀傾僀僗侾俀.俀俆kg(幨恀5-3)傪壛偊傞偲侾俀倣×侾俁倣巐曽偺寱摴応偵怺偝俀侽乣俁侽cm掱搙偺塤偑敪惗偟偨丅(幨恀5-4丄5-5丄5-6)偦偺偲偒悈壏偼俀俈.侾亷崀壓偟偰係俋.俁亷偵側偭偨丅塤壏搙係侽亷丠掱搙丅
丂悈傪俀俉.俈亷偐傜俈俇.係亷偵偡傞偺偵丄壛擬婍偵揹棳傪棳偟偰俇帪娫傪梫偟偨丅暯嬒夁擬懍搙偼乮98000乵倗乶×47.7乵俲乶×4.2乵俰乛g丒K乶乯乛乮6×60×60乵倱乶)亖909倂
偱幚尡俀傛傝傕夁擬岠棪傛偄偑丄偙傟偼恀壞偵丄掲傔愗偭偨婥壏偺崅偄奿媄応偱壛擬偟偨偺偱椻媝岠壥偑彮側偐偭偨偨傔偩傠偆丅
丂
恀5-3丂嵱偄偨侾俀.俀俆僉儘偺僪儔僀傾僀僗

丂
價僨僆塮憸傪偛棗偵側傝偨偄曽偼壓婰儕儞僋傪僋儕僢僋偟偰壓偝偄丅
丂丂丂敪惗憰抲偲弨旛偺價僨僆乮39.42MB丂俀暘俁侾昩乯
丂丂丂塤敪惗幚尡偺價僨僆乮45.83MB丂俀暘俆俇昩乯
偙傟偼Windows昗弨偺WMV8僐乕僨僢僋偺僼傽僀儖偱偡丅
幨恀5-4丂僪儔僀傾僀僗傪擖傟偨梕婍傪憓擖拞

丂
幨恀5-5丂塤敪惗偺嵟惙婜

丂丂
幨恀5-6丂塤敪惗偺屻婜

丂
丂
丂
丂埲壓偺幚尡偱偼丄塼懱擇巁壔扽慺傪梡偄偨惢憿憰抲(幨恀5-7丄5-8)偱嶌偭偨僪儔僀傾僀僗傪梡偄偨丅
丂
幚尡係乣俉丏(俀侽侽侽擭俋寧俀俇擔)
丂検揑側娭學傪應掕偡傞偨傔偺塤検應掕梕婍(幨恀5-9丄5-10)傪抜儃乕儖敔偱嶌偭偨丅俉侽亷慜屻偺搾侾.侽乣侾.俆kg偵侽.侾侽乣侽.俀侽kg偺嵶偐偔嵱偄偨僪儔僀傾僀僗傪擖傟偰塤敪惗検丄塤偺婥壏丄搾偺壏搙崀壓検傪應掕偟偨丅(幨恀5-11丄5-12)
丂幚尡係偼僪儔僀傾僀僗偑悈柺偵晜偐傫偱偟傑偄塤偺敪惗偑彮側偐偭偨偺偱丄幚尡俆乣俉偱偼嬥栐傪梡偄偰僪儔僀傾僀僗傪捑傔偰悈拞偱徃壺偝偣傞偙偲偵偟偨丅幚尡係偼梫椞偑埆偔丄傑偨幚尡俆偼塤偑梕婍偐傜堨傟偰懱愊應掕偵幐攕偟偨丅傑偨敪惗偟偨塤偺壏搙傕應掕偑偄偄壛尭偩偭偨偨傔偵偐側傝岆嵎偑偁傞偲巚傢傟傞丅
幚尡俋乣侾侾丏(俀侽侽侽擭俋寧俀俇擔)
丂忋婰偺幚尡偱搾偺尭彮検傪寁傝朰傟偨偺偱丄偼偐傝偺忋偱摨條偺幚尡傪偟偨傕偺丅偨偩偟崱夞偼偡傋偰僪儔僀傾僀僗偼悈柺忋偱徃壺偟偨丅
丂
幚尡侾俀乣侾俇丏(俀侽侽侽擭侾侽寧俁擔)
丂幚尡俋乣侾侾偺壏搙尭彮検偑幚尡係乣俉偵斾妑偟偰偐側傝彮側偐偭偨丅偙傟偼幚尡俋乣侾侾傪僪儔僀傾僀僗偺徃壺傪悈柺忋偱偟偨偨傔偲婥偯偒丄嵞搙丄幚尡俆乣俉偲摨偠庤弴偱峴偄丄偦偺忋偱塤偺敪惗偵敽偭偰尭彮偟偨價乕僇乕拞偺悈偺検傪應掕偟偨丅
丂
幨恀5-7丂僪儔僀傾僀僗惢憿憰抲
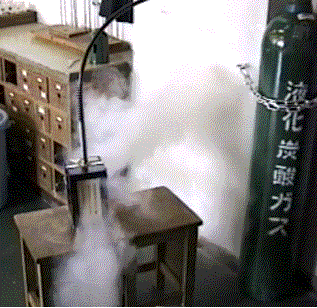
丂
幨恀5-8丂偱偒偨僪儔僀傾僀僗

丂
幨恀5-9丂搾傪擖傟傞梕婍

丂
幨恀5-10丂塤検應掕梕婍
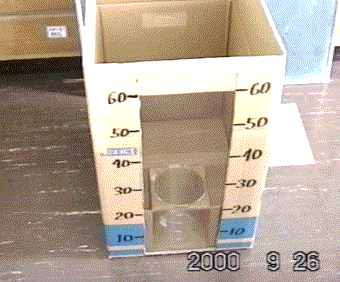
丂
幨恀5-11丂幚尡拞偺條巕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂
幨恀5-12丂塤偺忋柺偺條巕
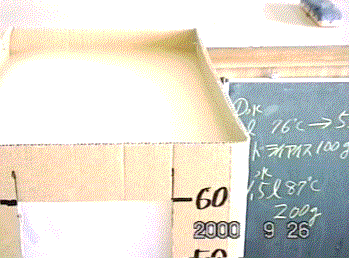
丂
丂
丂
丂
婎杮僨乕僞
俠俷俀偺徃壺擬
丂25.23kJ乛mol亖573×10俁J乛kg(侾婥埑丄195K)
丂
悈偺忲敪擬丂2259×10俁J乛kg(侾婥埑丄373K)
丂丂丂丂丂丂2444×10俁J乛kg(0.0315婥埑丄298K)
丂
俠俷俀偺掕埑斾擬丂0.8×10俁J乛K丒kg
悈忲婥偺掕埑斾擬丂1.8×10俁J乛K丒kg
嬻婥偺掕埑斾擬丂1.0×10俁J乛K丒kg
丂
丂
恾5-1丂俠俷俀偺忬懺恾

丂
丂
悈偺忲婥埑
| 壏搙乮亷乯 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
| 婥埑乮倎倲倣乯丂 |
0.04丂 |
0.07丂 |
0.12丂 |
0.19丂 |
0.31丂 |
0.47丂 |
0.69丂 |
丂
丂
幚尡俀乣侾俇偺應掕抣傪
昞5-1偵帵偡丅崁栚偺堄枴偼壓婰偺捠傝偱偁傞丅
乵幚尡斣崋乶亖杮暥拞偺幚尡斣崋
乵幐傢傟偨擬検乶亖悈偺壏搙崀壓検偐傜寁嶼偟偨僪儔僀傾僀僗偺徃壺偵敽偭偰徚旓偝傟偨擬検乵悈偺婥壔擬乶亖乵幐傢傟偨擬検乶亅乵僪儔僀傾僀僗偺徃壺擬乶
乵塤偺敪惗検乶亖應掕梕婍偱偺懱愊應掕抣
乵敪惗悈忲婥懱愊乶亖乵悈偺婥壔擬乶÷乮侾kg偺悈偺婥壔擬乯
乵敪惗偟偨塤偺婥懱壏搙乶亖應掕梕婍偵偨傑偭偨塤偺拞怱晹偱偺壏搙
偙偺昞偐傜撉傒偲傟傞偙偲
丂
侾丏偳偺幚尡偱傕僪儔僀傾僀僗偺徃壺擬偺侾.俀乣俀.侽攞偺擬偑扗傢傟偰偄傞丅僪儔僀傾僀僗偺徃壺擬埲奜偵扗傢傟偨擬偼悈偺婥壔偵梡偄傜傟偨偲巚傢傟傞丅偦偺嵺塤偺拞偵悈揌偲偟偰娷傑傟傞悈偼丄偨偲偊堦搙婥壔偟偰偄偨偲偟偰傕婥懱偺忬懺偐傜嵞傃嬅弅偡傞偺偱丄偙偺梋暘偺扗傢傟偨擬偵偼娭學偟側偄偩傠偆丅偩偐傜乵幐傢傟偨擬検]亅[僪儔僀傾僀僗偺徃壺擬乶亖乵婥壔偟偰婥懱偲偟偰懚嵼偡傞悈忲婥偺婥壔偵旓傗偝傟偨擬検乶偲峫偊偰椙偄偩傠偆丅昞拞偺崁栚俴丄俽偼偦偆偟偰媮傔傜傟偰偄傞丅偦偺傛偆偵偟偰摫偐傟偨乵悈忲婥偲擇巁壔扽慺懱愊偺榓俼乶偲乵塤偺敪惗検偺幚應抣俶]偺斾棪倂傪尒傞偲丄忦審曄壔偵傛傝塤偺敪惗検偑戝偒偔曄摦偡傞偵傕偐偐傢傜偢丄傎偲傫偳堦掕偺倂佮侾.俀晅嬤偺抣偵廂傑偭偰偄傞丅偙偺偙偲偼傑偝偵乵幐傢傟偨擬検]亅[僪儔僀傾僀僗偺徃壺擬乶偑悈偺婥壔擬偵側傝丄偦偺婥壔擬偵憡摉偡傞悈忲婥偑敪惗偡傞帠傪堄枴偟偰偄傞傛偆偱偁傞丅
丂
俀丏偙偺嵺乵俠俷俀亄悈忲婥偺懱愊乶傛傝傕乵塤偺敪惗検乶偺曽偑偡偙偟懡傔偵側傞偺偼塤偑梕婍偐傜悂偒弌偡偲偒廃埻偺嬻婥傪塤偺拞偵姫偒崬傫偱偄偔偨傔偲巚傢傟傞丅倂佮侾.俀偐傜峫偊偰丄姫偒崬傓嬻婥偺検偼敪惗婥懱偺俀.侽妱掱搙偱偁傞丅偨偩偟丄幚尡俁偺侾俀kg偺僪儔僀傾僀僗傪梡偄偨幚尡偱偼倂亖侾.俆俀偲偐側傝戝偒側抣偵側傝丄敪惗婥懱偺俆妱掱搙偺嬻婥傪姫偒崬傫偱偄傞丅偙傟偼價僨僆榐夋偺塤敪惗偺條巕偐傜傕暘偐傞傛偆偵丄梡偄傞僪儔僀傾僀僗検偑懡偄傎偳嫬奅柺偑寖偟偔姫偒崬傒廃埻偺嬻婥傪傛傝懡偔娷傫偱偄偔偨傔偱偁傠偆丅
丂
俁丏乵僪儔僀傾僀僗傪悈柺偱徃壺偝偣傞偐丄悈拞偵捑傔偰徃壺偝偣偨偐乶偲乵崁栚俬丄俰丄俶乶傪斾妑偟偰傒傟偽夝傞傛偆偵丄塤偺敪惗検偼悈拞偵捑傔偨応崌偑俀乣俁妱懡偄丅(幚尡俈丄俉丄侾俀偲幚尡俋丄侾侽丄侾俇傪斾妑乯傑偨乵嵟弶偺悈壏俧乶偲乵崁栚俬丄俰丄俶乶傪斾妑偡傞偲嵟弶偺悈壏偑崅偄傎偳壏搙偺崀壓検偑戝偒偔塤偺敪惗検偑懡偄帠偑暘偐傞丅乮幚尡俈丄俉丄侾俀丄侾俁丄侾係丄侾俆傪斾妑乯
丂偙傟傜偺帠幚偼埲壓偺帠忣偵傛傞偲巚傢傟傞丅
- 僪儔僀傾僀僗偲搾偺愙怗柺愊偺堘偄偑徃壺僗僺乕僪偺寖偟偝偺堘偄傪惗傒丄偦傟偑乵俠俷俀偑憕偒弌偡悈忲婥検乶偺堘偄傪惗傒偩偟乵幐傢傟傞擬検乶偺堘偄偑惗偠傞丅
- 僪儔僀傾僀僗壏搙偲搾偺壏搙嵎偑戝偒偄傎偳丄擬揱摫搙偑戝偒偔側傝傛傝寖偟偔徃壺偑峴傢傟丄傛傝懡偔偺悈忲婥偑憕偒弌偝傟丄傛傝懡偔偺悈偑忲敪偡傞丅
- 搾壏偑崅偄偲朞榓忲婥埑偑崅偔側傝傛傝懡偔偺悈忲婥偑俠俷俀偵崿崌偟偰偄傞丅偦傟偑憕偒弌偝傟傞偨傔忲敪擬偑懡偔側傞丅
丂搾壏俉侽亷偱悈拞偱僪儔僀傾僀僗傪徃壺偝偣偨応崌丄憕偒弌偝傟傞悈忲婥検偼敪惗俠俷
俀検偺俆乣俇妱掱搙偱偁傞偑丄搾壏傪壓偘偨傝悈柺偱徃壺偝偣偨傝偡傞偲侾乣俀妱掱搙傊尭彮偡傞丅
丂
係丏乵嵟弶偺悈壏俧乶丄乵敪惗悈忲婥懱愊俽乶偲乵塤偺婥壏俷乶傪斾妑偟偰傒傞偲丄悈壏偲憕偒弌偝傟偨悈忲婥偺懱愊偑丄悈忲婥偲俠俷俀偑崿偠傝崌偭偨塤偺嵟廔揑側婥壏傪寛傔傞偙偲偑暘偐傞丅偦偺嵺摨偠俠俷俀敪惗検偱傕悈忲婥偺壏搙偑崅偔側傞崅悈壏偺応崌傖丄憕偒弌偝傟傞悈忲婥検偑懡偔側傞応崌乮偙傟偼搾壏偲愙怗柺愊偵傛傞乯偵搾偐傜懡検偺擬偑僪儔僀傾僀僗塤偵揱偊傜傟塤壏搙偼傛傝崅壏偵側傞條偱偁傞丅帠幚搾壏偑俉侽亷掱搙偩偲塤偺壏搙偼係侽亷傪挻偊偨丅偙傟偼僪儔僀傾僀僗塤偺僀儊乕僕偐傜偡傞偲堄奜側帠幚偱偁偭偨丅
丂
俆丏乵搾偺尭彮検偺幚應抣俵乶偲乵嘆偺壖掕偵婎偯偔敪惗悈忲婥幙検偺寁嶼抣俼乶傪斾妑偟偰傒傞偲壗傟傕俵亜俼偲傞丅偙偺嵎乮俵亅俼乯偑悈揌偲偟偰塤傪峔惉偡傞悈偺検偵側傞偲巚傢傟傞丅忬嫷偵傛傞偑敪惗偡傞悈忲婥検偺俀乣俉妱偺條偱偁傞丅幚尡俁偱偼俵偲俽偐傜偡傞偲偡傞偲敪惗悈忲婥検偵旵揋偡傞悈揌偑偱偒偨偙偲偵側傞丅偙偙偺搾偺尭彮検偺應掕抣偼偐側傝岆嵎偑懡偄傕偺偩偭偨偑丄婯柾偺岠壥偑偁傞偺偐傕偟傟側偄丅
丂
俇丏埲忋偺寢榑傪傆傑偊偰乵敪惗偟偨俠俷俀乶丗乵敪惗偟偨悈忲婥乶丗乵姫偒崬傑傟偨嬻婥乶丗乵悈揌偲偟偰懚嵼偡傞悈乶偺儌儖斾傪侾侽丗俆丗俁丗俀.俆偲偟丄塤偺婥壏係侽亷丄侾婥埑偲偟偰塤婥懱偺暯嬒枾搙傪媮傔偰傒傞丅婥懱偼壗傟傕棟憐婥懱偲偟悈揌偺懱愊偼柍帇偡傞偲
丂
丂
堦曽傑傢傝偺嬻婥偺枾搙偼婥壏俀俆亷丄侾婥埑偲偟偰
丂
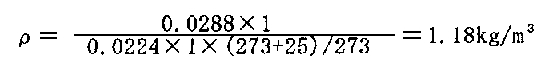
丂
偲側傝丄僪儔僀傾僀僗塤偺曽偑枾搙偑戝偒偔丄塤偑彴偵懾棷偡傞偙偲傪棤晅偯偗傞丅
丂
丂
丂
埲忋偺峫嶡偐傜僪儔僀傾僀僗偼壓恾偺條側儊僇僯僘儉偱塤傪嶌傞偲巚傢傟傞丅
俛俙俠俲丂丂丂俫俷俵俤丂丂丂俶俤倃俿
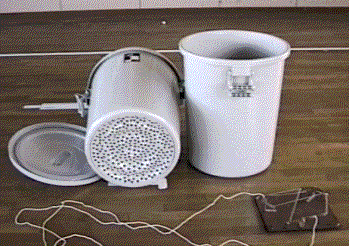
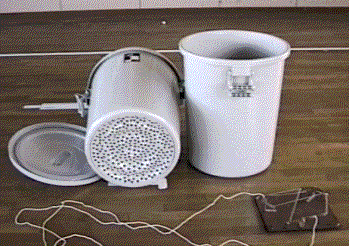
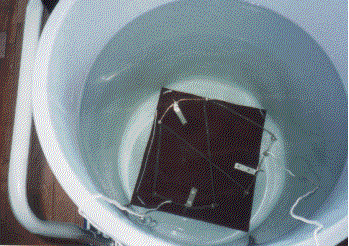




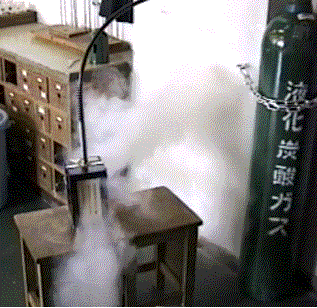


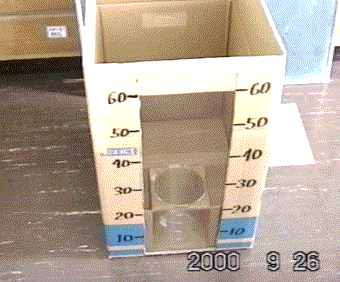

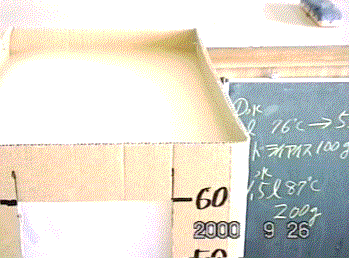

.gif)